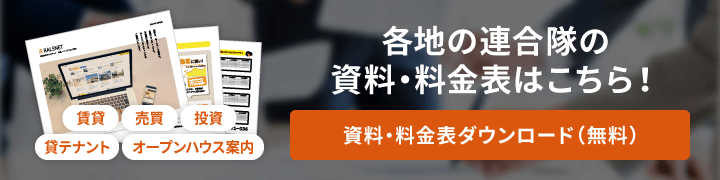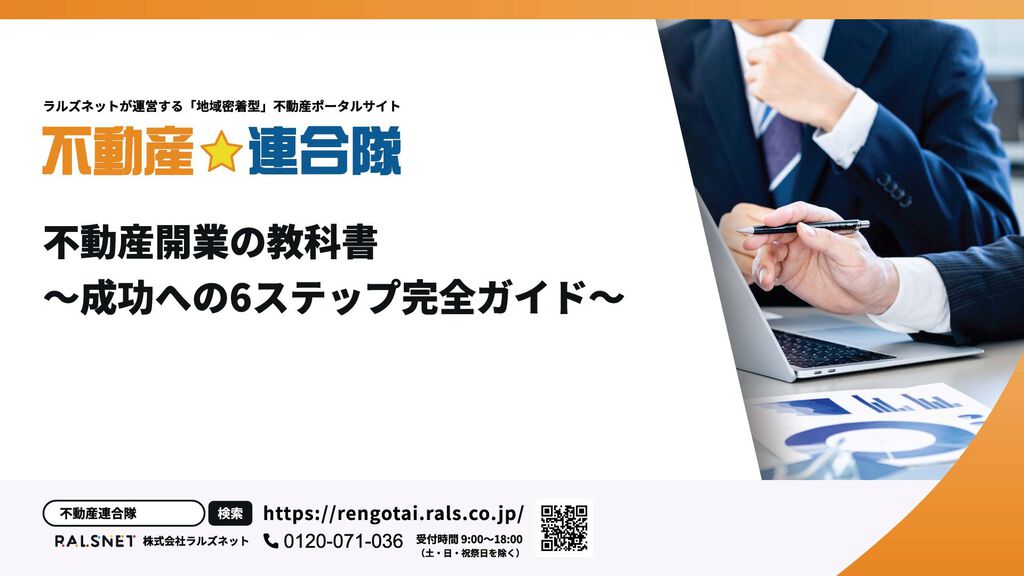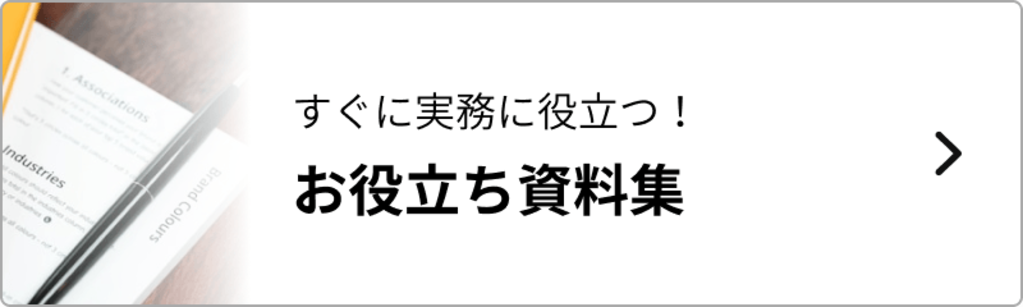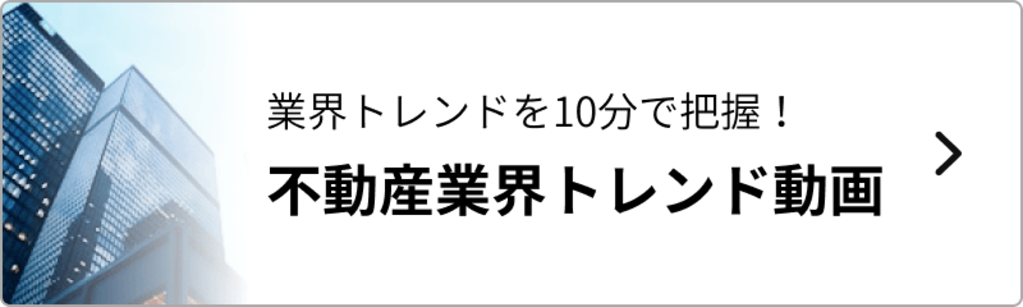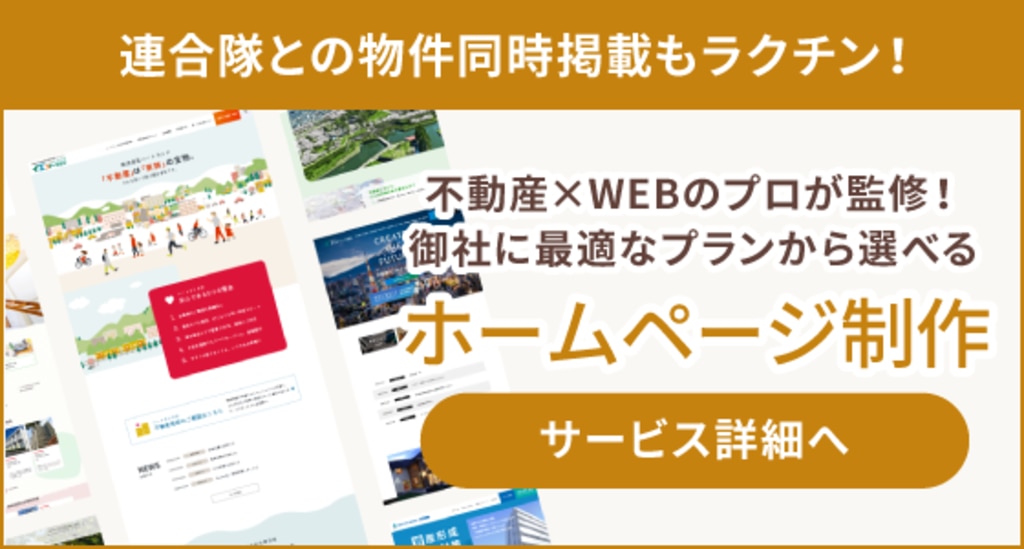2025年区分所有法改正|重要なポイントと対応策をわかりやすく解説!
マンションに住む人や、管理する立場の方にとって「区分所有法」は欠かせない法律です。とくに建物が老朽化し始める築30年、40年を超えたあたりから、 管理や修繕、建て替えに関する課題が表面化します。2025年には、そうした課題をふまえて「区分所有法」が大きく改正されます。
「区分所有法はどのように改正されるの?」
このようにお悩みの方も多いでしょう。そこで本記事では、 区分所有法改正の背景から具体的な変更点、対応策まで、わかりやすく解説します。管理会社や組合の方の参考になる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次[非表示]
- 1.区分所有法とは?マンション管理と密接な法律
- 2.区分所有法の改正が必要な理由|背景にある問題とは?
- 3.区分所有法改正のポイント総まとめ【2025年】
- 3.1.所有者不明問題に対応する新たな仕組み
- 3.2.出席者多数決による合意形成の柔軟化
- 3.3.管理不全建物への対処制度の創設
- 3.4.管理計画や規約の見直しがより重要に
- 3.5.共用部分の変更決議ハードル緩和
- 3.6.建て替え・一括売却の要件緩和と新ルール
- 3.7.一棟リノベーションも多数決で可能に?
- 3.8.賃借権の処理で工事をスムーズに
- 3.9.被災マンション・団地への特例と支援策
- 4.区分所有法の改正履歴から見る流れ|これまでとの違い
- 5.区分所有法改正への対応策|管理会社が今やるべきこと
- 6.区分所有法改正を追い風に!管理と集客の両立を図るには?
- 7.区分所有法改正をチャンスに!管理・集客を支える「不動産連合隊」
- 8.よくある質問|区分所有法の改正の疑問を解決!
区分所有法とは?マンション管理と密接な法律

「区分所有法」は、正式には「建物の区分所有等に関する法律」と呼ばれ、 分譲マンションの管理や運営に欠かせないルールです。住戸ごとに所有者が異なりながらも、廊下やエレベーターなどの共用部分は全員で管理する必要があるため、その調整や手続きを法律で支えています。
たとえば、共用部分の修繕工事や建て替え、大規模な改修を行う場合で考えてみましょう。区分所有法に基づいて区分所有者全体で話し合い、合意を得る流れになります。また、管理組合の運営や、規約の見直しなども、区分所有法の枠組みの中で行われています。
マンションの老朽化が進む今、区分所有法の果たす役割はますます重要になるでしょう。
区分所有法の改正が必要な理由|背景にある問題とは?

2025年の区分所有法改正は、単なる制度の見直しではありません。今まさに全国のマンションが抱えている「深刻な課題」に向き合うための、大きな一歩です。
ここでは、法改正に至った背景として、とくに重要な4つの問題を見ていきましょう。
築40年超えが急増!老朽化マンションの現状
日本のマンションは急速に老朽化しています。 国土交通省によると、 築40年を超えるマンションは2023年時点で約136.9万戸でした。2033年には約274.3万戸に倍増すると予測されています。
築年数が進むと、建物の劣化や設備の不具合、外壁のひび割れなどが目立つようになります。とくに深刻なのが、以下のような問題です。
|
こうした状況に対応するには、現行の制度だけでは限界があります。そのため、柔軟かつ実行可能なルールが求められています。
▼関連記事はこちら
所有者不明・非居住化による合意形成の困難
もうひとつの大きな課題が、「 所有者が誰かわからない部屋」が増えていることです。
相続登記がされないまま放置された住戸や、長期間連絡の取れない所有者が、全国的に増加傾向です。
さらに所有者がいても実際には住んでおらず、賃貸や空き家となっているケースも多く見られます。マンションでは、修繕や建て替えなど大事なことを決める時に、住民の話し合いや賛成が必要です。この「みんなで決めるプロセス」のことを合意形成(ごういけいせい)といいます。
しかし、 所有者不明や非居住の住戸が増えると、合意形成そのものが困難になります。とくに問題となるのが、以下のような決議です。
|
合意形成のハードルが高いままだと、老朽化した建物を適切に維持できません。 この問題に対応するためにも、区分所有法の見直しは急務となっています。
被災マンションの再建が進まない現実
地震や水害などの災害によって、 大きな被害にあったマンションの再建が進まないという問題もあります。建物が全壊や半壊しても、再建のためには所有者全員の合意、または高い賛成率が必要です。しかし、現実には以下のような壁が立ちはだかります。
|
たとえば、2016年熊本地震や2011年東日本大震災の際にも、多くの被災マンションで再建が遅れたり、断念されたケースがありました。このような非常時に備えて、迅速に意思決定できる制度が必要とされています。
国と法務省・国交省の動き|改正への流れ
こうした課題に対処するため、国も本格的に動き始めました。2023年には、法務省と国土交通省が合同で「 今後のマンション政策のあり方に関する検討会」を開催。その中で、以下の方向性が示されました。
|
そして2024年に改正要綱案が取りまとめられ、2025年の通常国会での法改正へとつながっていきます。今回の改正は「今ある現実」に対応し、これからのマンション管理を支えるためのものです。
参照| 国土交通省:マンション管理・再生の円滑化等のための改正法案
区分所有法改正のポイント総まとめ【2025年】

今回の2025年の改正では、これまで問題視されていた「合意形成の難しさ」や「管理不全マンションの放置」などに対し、実効性のある対応策が盛り込まれました。
現場の声に耳を傾け、法律としての現実的な運用を目指した内容です。ここでは、とくに注目したい9つのポイントをわかりやすく紹介します。
所有者不明問題に対応する新たな仕組み
登記がされないまま放置された住戸や、相続後の手続きを行わず所有者が不明な状態が長く続くと、管理がしづらくなります。そうしたケースに対応するための新しい仕組みが導入されます。
とくに注目すべきは、 所在などが不明な所有者を総会の決議の母数から除外できる制度が設けられる点です。これにより、必要な決議で実際に参加ができない所有者を加味せずに意思決定ができるようになります。
ただし、管理組合が勝手に判断して除外できるわけではなく、裁判所への申し立てと正式な 裁判手続きが必要です。裁判所が認定して初めて、総会の招集通知も不要となり、除外が適用されます。
このような制度の整備により、意思決定の停滞を防ぎ、スムーズな管理運営が実現しやすくなるでしょう。
出席者多数決による合意形成の柔軟化
従来、重要な決議は「 全所有者の4分の3以上が賛成」など、高いハードルがありました。しかし、出席者が少ない場合、何も決められない状態になるケースもありました。
今回の区分所有法改正では、 総会に出席した区分所有者の中だけで意思決定を可能にする規則が検討されています。これは、全員の合意が必要な決議とは異なり、管理に関する一部の事項などに限定して、出席者の多数決で決議できるようにするものです。
たとえば、通常総会での出席者が限られる中でも、 一定の条件を満たせば出席者の多数決によって合意を形成できるようになり、管理の停滞を防げます。
管理不全建物への対処制度の創設
管理組合が機能せず、修繕も長年行われていない「管理不全マンション」が全国で増えています。今回の区分所有法改正では、このような管理不全状態に対して、 第三者の関与によって改善を促す新たな制度の創設が検討されています。
具体的には、次のような対応が可能になる見込みです。
|
所有者の不在や無関心によって適切な管理ができないマンションにも、法的手続きを経て外部の専門家が関与し、建物の安全性や住環境を回復することが可能になります。
管理計画や規約の見直しがより重要に
2025年の区分所有法改正では、合意形成をスムーズに行うための規則が新設され、多数決で決議できる範囲も一部拡大される見込みです。一方で、多数決による決議が可能になる分、 あらかじめ「何を・どう決めるか」を管理規約で明確にしておくことの重要性が増しています。
たとえば、次のような内容を事前に管理規約に定めておくことで、総会や緊急時の対応がスムーズになります。
|
また、国土交通省が推進する「 マンション管理計画認定制度」とも連携し、適切な維持管理を行うためには、管理計画の策定と定期的な見直しがこれまで以上に求められます。
今回の改正は、単に法律のルールが変わるだけでなく、各マンションが自らの実情に合わせて、規約や管理体制を整える“きっかけ”にもなる重要な機会です。
自分たちのマンションにとって「何が必要か」を見直し、規約をアップデートすることが、今後の持続可能な管理運営に直結していきます。
共用部分の変更決議ハードル緩和

これまで、エントランスやエレベーターなどの共用部分を変更・改修するには、 区分所有者全体の厳格な賛成要件(通常3/4以上)を満たす必要がありました。このため、バリアフリー化や防犯カメラの設置など、住民の利便性や安全性を向上させる合理的な改善であっても、合意が得られず実施できないケースも数多く存在しました。
2025年の区分所有法改正では、共用部分の変更に関して、合理的な理由がある場合に限り、決議要件を緩和する制度が導入される予定です。
たとえば、住民の高齢化や治安の不安などの状況に応じて、早急に対応すべき改修や設備の追加を、従来よりも少ない賛成数で決められるようになります。次のような改善がよりスムーズに進められるようになるでしょう。
|
これらが 過半数や出席者の多数決など、より現実的なラインで決議可能になる予定です。生活の質や安全性を向上させる改修が、スムーズに進められるようになると期待されています。
建て替え・一括売却の要件緩和と新ルール
建物が老朽化し、安全性が確保できなくなった場合、建て替えや一括売却も選択肢になります。しかし、これまでの制度では「 全体の5分の4以上が賛成」が必要で、合意形成が難しい状況でした。
たとえば、建物が被災した場合や、著しい老朽化によって「現に安全な使用が著しく困難である」と判断されるケースでは、 合意要件を緩和し、建物の再生を現実的に進めやすくなります。
具体的には、以下のような新ルールが導入される予定です。
|
合意形成が難航しやすい老朽マンションでも、円滑な再生の道筋をつけやすくなり、安全で快適な住まいへの転換が進めやすくなります。
一棟リノベーションも多数決で可能に?
老朽化マンションの再生手段として、近年注目されているのが「建て替え」ではなく、既存の建物の構造を活かしつつ、内外装・設備を全面的に改修する手法です。
しかし、これまでは 大規模な共用部分の改修には所有者全員の賛成が必要で、実施が難しい状況でした。
今回の2025年の法改正では、こうした中間的な再生手法にも対応できるよう、 共用部分の大規模改修を「5分の4以上の賛成」で決議可能とするルールの整備が予定されています。
具体的には、建物の構造体を残したまま設備や内装、外壁などを大幅に刷新する場合であっても、従来の建て替えと比べて緩やかな要件で住民の合意を形成しやすくする制度が導入される見込みです。
これにより、次のようなメリットが期待されます。
|
今回の改正は、「壊して建て直す」だけではない、“再生の選択肢”を広げる大きな転機となるでしょう。
賃借権の処理で工事をスムーズに
マンションの建て替えや一棟リノベーション、大規模な改修工事を行うのに「 借主(賃借人)」の存在が大きな壁でした。
たとえば、区分所有者が賃貸に出している住戸に借主が住んでおり、退去に応じない場合で考えてみましょう。この場合、工事そのものが進められず、 再生計画全体が頓挫してしまうケースもこれまで多く見られました。
2025年の法改正では、この課題の解決策として、建物全体の再生に伴う賃借権の処理に関する新たな制度が導入されます。具体的には、建て替えや一括売却が多数決で決議された場合に、以下のような対応が可能になります。
|
「賃借人がいるから建て替えができない」というボトルネックを解消し、マンション全体の再生をより現実的かつ円滑に進められるようになると期待されています。
被災マンション・団地への特例と支援策
地震や水害などの大規模災害によって深刻な被害にあったマンションや団地では、早急な判断と対応が求められます。一方で、従来の制度では合意形成や手続きに時間がかかり、 復旧や再建が大幅に遅れるケースが少なくありませんでした。
2025年の区分所有法改正では、こうした災害時に対応できるよう、 特別な支援措置と柔軟な決議手続きが盛り込まれています。たとえば、次のような制度が導入される予定です。
|
これらの措置により、被災マンションの再建や処分をより迅速かつ現実的に進められるようになり、住民の生活再建や地域の復興を支援する制度となるでしょう。
参照| 国土交通省:新旧対照条文
区分所有法の改正履歴から見る流れ|これまでとの違い

2025年に予定されている区分所有法の改正は、過去の改正と比べても「踏み込んだ対応」が特徴です。これまでの改正は、どちらかといえば制度の整理や部分的な見直しが中心でした。しかし、今回はマンションの「老朽化」「災害」「管理不全」などの現実的な問題に、より実践的に切り込んでいます。
まずは、これまでの改正の流れを年表で振り返ってみましょう。
年代 | 改正内容 |
1962年 | 区分所有法の制定(建物の区分所有等に関する法律) |
1983年 | 管理組合の法人化が可能に |
1991年 | 土地共有者の議決権明確化、議決要件の合理化 |
2002年 | 区分所有法とマンション管理適正化法が連動 |
2013年 | 建て替え決議の要件緩和(耐震性不足の建物に対して、5分の4→4分の3) |
2020年 | 所有者不明土地問題と連動する議論が本格化 |
2025年(予定) | 合意形成の柔軟化、管理不全マンション対策、所有者不明住戸対応、 |
今回の改正は、単に法律を「使いやすくする」だけではありません。むしろ、 今後10年〜20年のマンションの“生存戦略”を左右する基盤とも言える内容です。法律が変われば、できることが増え、選択肢も広がります。
この大きな流れを正しく理解し、自分たちの管理・運営にどう活かすかが重要です。
参照| 国土交通大臣:これまでの主な取組
区分所有法改正への対応策|管理会社が今やるべきこと

2025年の区分所有法改正は、マンション管理の現場にも大きな影響をもたらします。
ここでは、管理会社が今から備えておきたい対応策を解説します。どれも難しいものではありませんが、早めの準備が後の大きな差につながるでしょう。
今のうちに管理規約を見直しておくべき理由
法改正により、合意形成のルールや管理に関する判断基準が見直されます。その結果、既存の管理規約と改正後の制度との間に「ズレ」が生じる可能性があります。
たとえば、次のような項目は、とくに注意が必要です。
|
法改正の内容をふまえたうえで、「今の規約は実際の運用とズレていないか」をチェックし、必要に応じて修正を提案しましょう。
所有者不明問題を想定した合意形成の準備
今回の改正では、 所有者不明住戸がある場合の意思決定にも、新たなルールが整備されます。しかし、制度が整うだけでは合意形成が進みません。
管理会社としては、以下のような対応を今から準備しておくと安心です。
|
たとえば、突然建て替えの話が持ち上がった時、「 誰に確認すればいいのかわからない」という状態では、住民の不安も大きくなります。今のうちに準備しておけば、説得力を持って住民に説明できます。
組合向け説明資料の整備と研修
制度が変わると、管理組合や区分所有者からも「何がどう変わるの?」という疑問が増えてきます。そうした声に対応できるよう、 社内・社外両方への情報提供体制を整えておくことが求められます。具体的な対応は、以下のとおりです。
|
住民や理事会の信頼を得るには、「わかりやすく伝える力」が鍵になります。あらかじめ資料を整えておけば、短い打ち合わせ時間でも的確に説明できます。
行政や外部専門家との連携
今回の改正では、「 裁判所の関与」や「 外部専門家の利用」が選択肢として広がる予定です。つまり、管理会社単独で対応できないケースが今後は増える可能性があります。そのため、以下のような外部連携の準備が大切になります。
|
とくに所有者不明住戸の扱いや、災害時の緊急決議の対応は、法律の知識が欠かせません。 いざという時に相談できるネットワークを持っておくことが、管理の質を左右します。
区分所有法改正を追い風に!管理と集客の両立を図るには?

2025年の区分所有法改正は、単に管理の負担が増えるだけではありません。むしろ、先回りして備えることで、 管理品質の向上と集客力アップの両方を実現できるチャンスになります。
多くの管理組合が「何をすればいいのかわからない」と感じている今だからこそ、制度を正しく理解し、的確な提案ができる管理会社には信頼が集まります。これは、競合との差別化にも直結する重要なポイントです。
たとえば、次のような対応策は、管理品質と営業力の両面で効果があります。
|
こうした提案を通じて、「頼りになるパートナー」としての存在感を高められます。結果的に、管理契約の継続率アップや紹介による新規獲得にもつながるでしょう。
区分所有法改正をチャンスに!管理・集客を支える「不動産連合隊」

今回は、 2025年の区分所有法改正のポイントと管理会社として取るべき対応策をご紹介しました。制度が大きく変わる今は、管理品質を見直し、組合からの信頼を高める絶好のチャンスになります。
そしてもうひとつ、今後の経営に欠かせないのが「 集客力の強化」です。
その対策としておすすめなのが、ラルズネットが提供する「不動産連合隊」の活用です。地域密着のネットワークと高い集客力で、 物件の認知度向上や問い合わせ数の増加に貢献します。さらに、自社サイトとの連携や、購入・契約意欲の高いユーザー層へのアプローチ強化も可能です。
これからの時代は、良いサービスを持っているだけでなく、「選ばれる仕組み」を持つことが重要です。管理と集客の両立を目指すなら、ぜひ「不動産連合隊」のサポートをご検討ください。
よくある質問|区分所有法の改正の疑問を解決!
区分所有法の改正案はいつ国会で成立しましたか?
現時点(2025年3月末)では、成立されていません。2025年3月4日、政府は「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 現在開会中の国会で審議中であり、成立すれば2026年4月の施行を目指しています。
マンションの建て替え円滑化法も改正されたのですか?
はい、並行して見直しが行われました。区分所有法と連動して、建て替えをしやすくするためのルールが整理・強化されました。とくに合意形成の要件が一部緩和されています。
区分所有法改正要綱案って何ですか?
法改正の前に発表される「改正の方向性を示した案」のことです。今回の改正でも、2023年に法務省が改正要綱案を公表し、それをもとに国会審議が行われました。
区分所有法の改正条文を解説してほしい
条文は法務省の公式サイトで公開されています。ただし、専門用語が多いため、実務上は要点をまとめた解説記事などを参考にするのが安心です。
マンションに関係する区分所有法の改正は管理会社に関係ありますか?
はい、大きく関係します。管理規約の見直しや、合意形成の支援など、管理会社の担う役割が増える内容です。対応力が今後の信頼や選ばれる理由になります。
▼関連記事はこちら