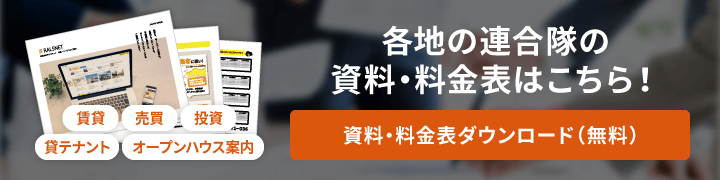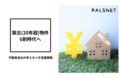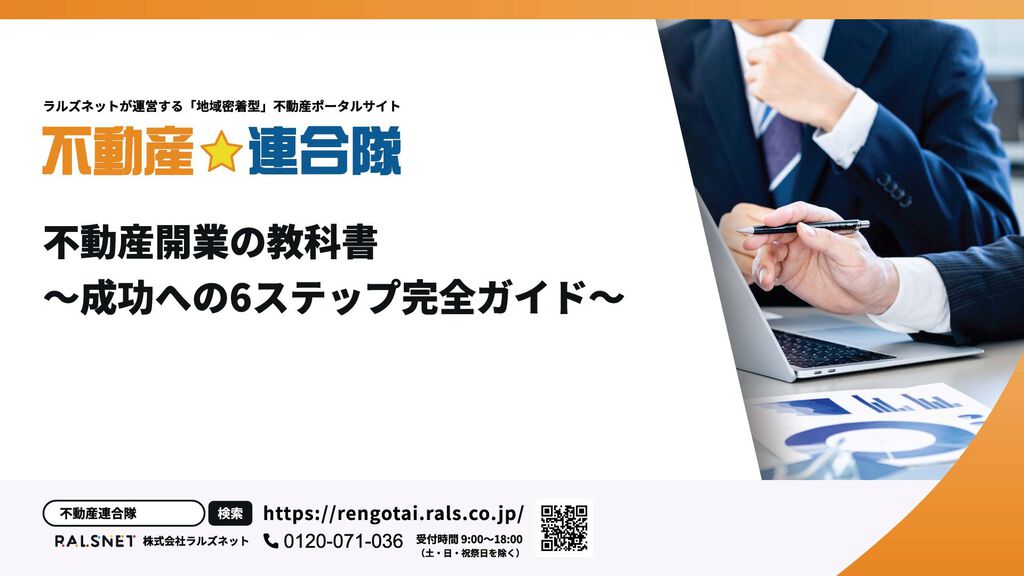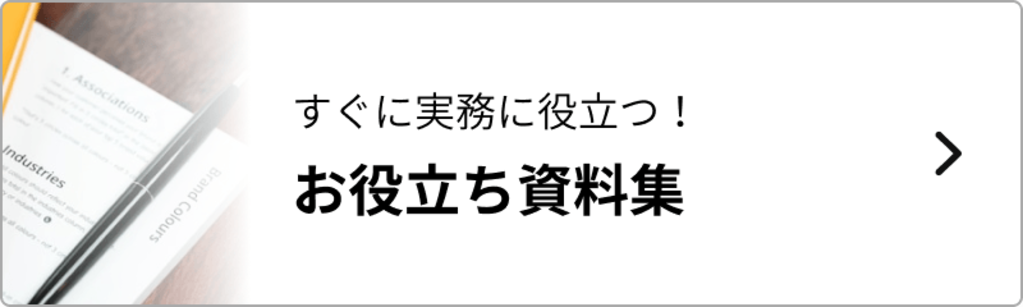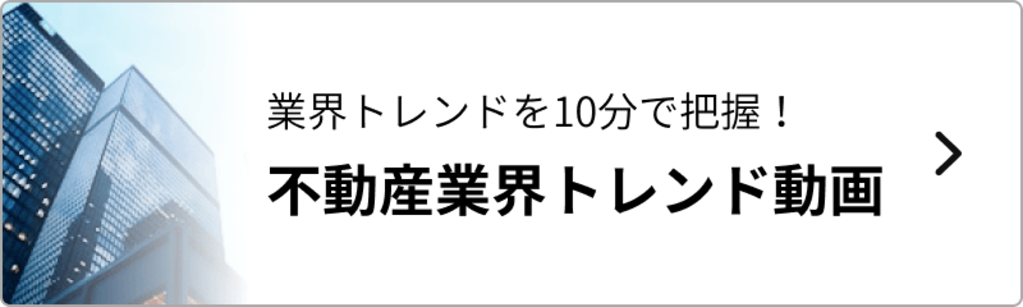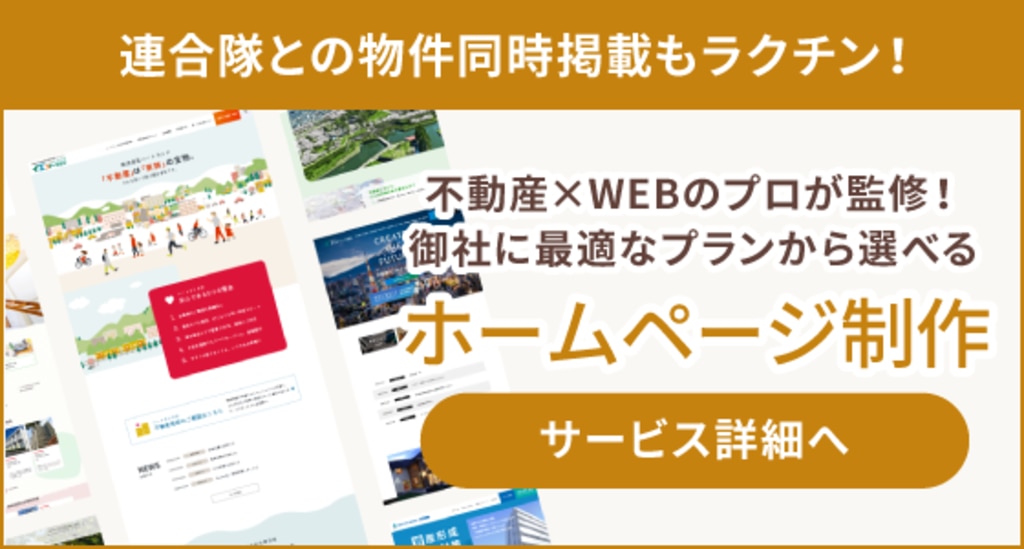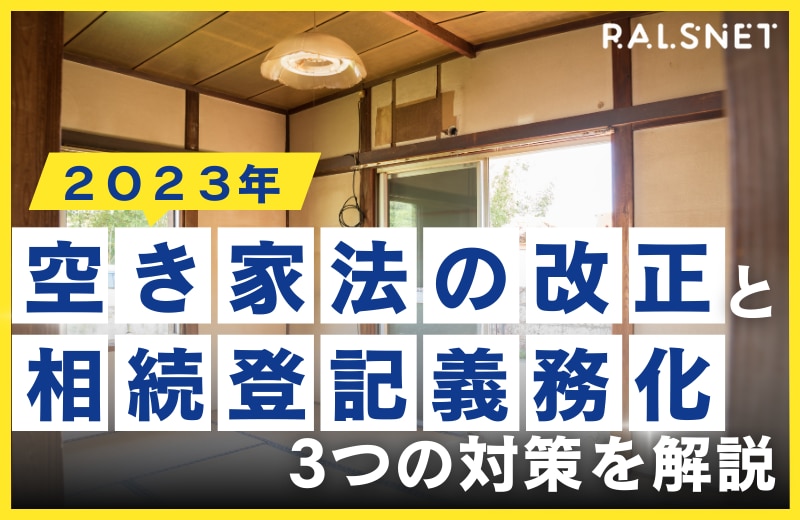
空き家法の改正(2023年)と相続登記義務化|3つの対策を解説
空き家に関連する重要な法改正が、2023年と2024年に相次いで施行されたのをご存じでしょうか。2023年には空き家法(空家等対策特別措置法)が改正され、 「管理不全空家」の新設や固定資産税の見直しなど、所有者への規制が強化されました。
さらに2024年には 相続登記の義務化が施行され、相続された不動産の放置にも法的な対応が求められるようになっています。不動産業者がこれらの変化に対応できないと、 固定資産税の大幅増や売却の長期化、顧客からの信頼喪失といったリスクが生じる可能性もあるでしょう。
本記事では、「空き家に関連する法改正のポイント」を整理し、2023・2024年に施行された改正内容と、不動産業者が実践すべき対策3つを丁寧に解説します。
空き家法改正への対応力は、いまや業者としての信頼を高める重要な武器です。法改正をチャンスに変えるための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
目次[非表示]
空き家法が改正された流れ|背景にある社会問題と今後の課題

空き家の放置が地域の安全や景観に影響し、大きな社会課題となっています。こうした問題に対応するため、空き家に関する法律が2023年と2024年に大きく改正されました。ここでは、その改正の背景と今後の課題をわかりやすく解説します。
増え続ける空き家と社会課題
令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は 約900万戸にのぼります。全住宅の13.8%が空き家であり、深刻な状況といえます。中でも、問題視されているのは「管理されていない空き家」です。倒壊の危険や害虫の発生、ゴミの不法投棄といったトラブルが起きやすく、地域住民からの苦情も後を絶ちません。
空き家がもたらす主なリスクは以下のとおりです。
|
とくに都市部だけでなく、 地方や郊外でも同様の問題が深刻化しています。所有者が高齢で対応できない、相続人が遠方にいて管理されない、といったケースも少なくありません。今後、空き家が放置されればされるほど、地域全体に悪影響が広がっていきます。
そこで国は、空き家の増加に歯止めをかけ、早期に対応を促す仕組みを整備する必要に迫られました。
空き家法のこれまでと改正の必要性
「空き家法」の正式名称は「 空家等対策の推進に関する特別措置法」です。この法律は2015年に施行され、一定の空き家に対して行政が調査・指導・勧告を行うための枠組みを定めました。
しかし、現行の空き家法には次のような課題がありました。
|
その結果、 老朽化が進む前に対策することが難しく、地域住民の不安が解消されないままになっていたのです。こうした背景を受けて、2023年に空き家法が改正されました。さらに、2024年には相続登記の義務化という大きな制度変更もスタートしています。
これらの空き家法改正は、不動産所有者だけでなく、業者側にとっても大きなターニングポイントとなるでしょう。
【2023年】空き家法の改正内容|管理不全空家の新設

2023年の法改正では、空き家対策がより早期に、そして効果的に行えるよう法律の枠組みが見直されました。とくに注目すべきポイントは、「管理不全空家」の新設と、それにともなう税制や行政の権限強化です。
ここでは、2023年の改正内容を詳しく見ていきましょう。
管理不全空家とは?特定空家との違い
従来の法律では、行政が対応できる空き家は「特定空家」に限定されていました。特定空家とは、すでに倒壊や火災の危険があるなど、著しく保安上・衛生上問題のある建物を指します。しかし実際には、 「 そこまで深刻ではないが放置すれば危険になる空き家」が全国に数多く存在しています。
そこで2023年の改正では、「管理不全空家」という新たな分類が導入されました。これにより、以下のような段階的な対応が可能になりました。
分類 | 状況の目安 | 行政の対応 |
管理不全空家 | 屋根や外壁が劣化、雑草やゴミが放置されている | 指導・助言・勧告など |
特定空家 | 倒壊や火災の危険が高い | 勧告・命令・強制撤去 |
つまり、 特定空家に指定される前から行政が対応できるようになりました。2023年の改正によって空き家の悪化を防ぎやすくなり、地域への悪影響を抑えることが期待されています。
固定資産税の特例解除で負担が増える?
空き家を持つ所有者にとって、とくに大きな影響を与えるのが固定資産税の特例解除です。これまで 住宅が建っている土地には、固定資産税が最大6分の1に軽減される特例が適用されていました。しかし今回の法改正により、「管理不全空家」に対して自治体から勧告を受けると、 この特例が解除されるようになりました。
その結果、土地の固定資産税が最大6倍に増える可能性があります。この制度変更の意図は明確で、「空き家を放置してはいけない」という強いメッセージを込めたものといえるでしょう。なお、勧告が出された場合、税制だけでなく「補助金の対象外になる」といった影響もあるため、所有者への丁寧な説明が必要です。
自治体の活用促進区域・指導権限の強化
2023年の改正では、空き家の利活用を後押しする制度も新たに追加されました。具体的には、各市区町村が「 空き家等活用促進区域」を設定し、その区域内の空き家に対して活用を促す取り組みが可能になりました。たとえば以下のような制度が運用できます。
|
また、空き家に関する調査や指導に必要な 所有者情報の取得権限も強化されました。これにより、名義が不明な物件への対応も進みやすくなっています。このように、空き家法は「管理だけでなく活用も支援する」方向へとシフトしています。不動産業者にとっては、空き家ビジネスの可能性が広がるチャンスともいえるでしょう。
【2024年】空き家に関連する法改正|不動産相続登記が義務化

2024年4月1日から、「不動産の相続登記」が義務化されました。空き家法そのものの改正ではありませんが、空き家が放置される大きな原因と深く関係しています。とくに相続後に登記がされず所有者が不明なままの空き家が、全国で問題となってきました。
ここでは、相続登記義務化の概要と実務への影響についてわかりやすく整理します。
不動産相続登記の義務化とは?罰則や期限
これまで不動産を相続しても、登記は「任意」でした。そのため、登記がされないまま放置され、所有者が誰かわからなくなるケースが多数発生していました。新制度では、 不動産を相続した人に対し、「3年以内の登記申請」が義務化されます。
これを怠ると、 最大10万円の過料(行政罰)が科される可能性があります。
内容 | 詳細 |
|---|---|
義務の対象 | 相続で不動産を取得した個人や法人 |
登記申請の期限 | 相続を知った日から3年以内 |
罰則 | 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料 |
とくに相続人が複数いて手続きが遅れている場合や、話し合いが進まないまま放置されているケースには注意が必要です。不動産の所有者が不明確なままだと、売却も活用もできず、空き家として放置されてしまうリスクが高まります。
所有者不明土地・空き家問題への対策
不動産の登記義務化の背景には、「 所有者不明土地・空き家」の増加があります。たとえば、祖父母が亡くなって何十年も経った実家が登記されないまま残され、誰が所有しているかわからない、といったケースが全国に広がっているのです。
このような土地や空き家は、次のような問題を引き起こします。
|
国はこうした課題を解決するために、相続登記の義務化を進めました。また、同時に「所有者申告登記」という新制度も導入され、 登記名義人の変更(氏名・住所)も義務化されています。
不動産を相続したらどうすればいい?
相続した不動産がある場合、次のようなステップで手続きを進めましょう。
|
とくに名義変更や共有名義になっている場合は、司法書士や弁護士への相談をおすすめします。不動産業者としては、お客様からの相談に備え、 相続登記の基本的な流れや必要書類についての知識を身につけておくことが重要です。また、相続物件をどう活用するかの提案力も、今後ますます求められていきます。
空き家法改正の対策|不動産業者が押さえるべきポイント

空き家法の改正により、放置空き家への対応がこれまで以上に厳しく、そして早期化しています。不動産業者としては、所有者への啓発だけでなく、空き家活用の提案や相続関連の対応力も求められるようになるでしょう。
ここでは、不動産のプロが押さえておきたい実務的な対策を3つに絞ってご紹介します。
対策1 管理不全空家指定を防ぐための所有者サポート
「管理不全空家」に指定されると、 行政から勧告を受けたり、税制上の特例が外れたりするリスクが生じます。こうした事態を防ぐためには、所有者が“指定されないように管理する”サポートが重要です。
具体的には、以下のようなアプローチが効果的です。
|
所有者の中には、「税金が上がるなんて知らなかった」「特定空家まで放置しても問題ないと思っていた」という方も少なくありません。丁寧にリスクを説明し、「今すぐできる小さな対応」から提案していくことが信頼につながります。
対策2 売却・賃貸・再活用の選択肢を広げる提案力
空き家対策には「活用」が欠かせません。ただ解体を勧めるだけでなく、 売却・賃貸・リノベーションといった多様な提案が強みになります。
とくに近年は以下のような支援制度も整いつつあります。
|
たとえば、「駅から遠くて売れない」と思われていた物件でも、リノベーションして賃貸住宅として活用されるケースもあります。 地域の事情や支援制度をよく理解し、選択肢を提示できることが顧客満足度の向上につながります。
対策3 相続・登記対応の体制づくりとアドバイス
2024年から始まった相続登記の義務化は、空き家問題の根本対策とも言われています。不動産業者としては、 相続関連の基礎知識と連携体制を整えておくことが大切です。
|
とくに地方では、「登記名義が亡くなった親のまま」という空き家が非常に多く存在します。 登記変更が進まなければ、売却もリフォームも実現できません。そのため、物件相談を受けた際に「相続登記は済んでいますか?」という一言を添えるだけでも、専門性のある不動産業者としての印象が大きく変わります。
空き家法改正(2023年)をチャンスに変えよう!

今回は、 2023年の空き家法改正と、2024年に施行された相続登記の義務化、そして不動産業者が実践すべき3つの対策について解説しました。空き家の管理や相続への関心が高まる中、法改正はリスクだけでなくチャンスにもなります。
所有者に寄り添った提案や、 空き家の活用提案ができれば、信頼と集客の両方につながります。
空き家法2023・2024年のよくある質問
空き家法の改正はいつから適用されますか?
2023年改正分は、2023年12月13日から施行されています。管理不全空家の指定や特例解除などがこの日以降、各自治体で運用開始されました。一方、相続登記の義務化は2024年4月1日からスタートしています。それ以前の相続案件も対象となるため、過去の名義変更漏れがないか確認が必要です。
空き家法の改正で固定資産税は上がるの?
はい、管理不全空家に指定され勧告を受けた場合は、住宅用地の固定資産税特例が解除されます。この特例がなくなると、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
「空き家をそのまま放置すると税金が高くなる」と所有者に伝えることが、実務対応でも重要です。
空き家対策特別措置法のガイドラインって何ですか?
ガイドラインは、国土交通省が発行している空き家の判定や指導に関する基準です。自治体はこれをもとに、空き家の状況調査や「管理不全空家」指定の判断を行っています。具体的には、屋根や壁の損傷状況、草木の繁茂、衛生状態などが細かく定められています。
相続放棄しても空き家の管理義務はありますか?
基本的には、相続放棄をしていれば法律上の管理義務はなくなります。ただし、家庭裁判所で正式に放棄が認められるまでの間は、管理責任を問われる可能性があります。また、放棄後も近隣住民との関係やトラブル回避の観点から、適切な対応を勧めることもあるでしょう。
空き家法改正で、不動産相続登記の義務も関係ありますか?
はい、2024年から施行された相続登記の義務化は、空き家の所有者確定を目的とした制度です。相続によって名義変更のされていない空き家が、放置される原因となっていたため、強制力をもたせた改正といえます。
相続登記を怠ると10万円以下の過料が科されるため、注意が必要です。
空き家を解体・売却すると補助金はもらえますか?
多くの自治体では、老朽化した空き家の解体費用や、リフォーム・活用のための補助金制度を設けています。たとえば「空き家除却補助金」や「空き家活用改修助成金」などがあります。補助額は地域によって異なるため、物件所在地の自治体の制度を確認し、所有者に提案するのがおすすめです。