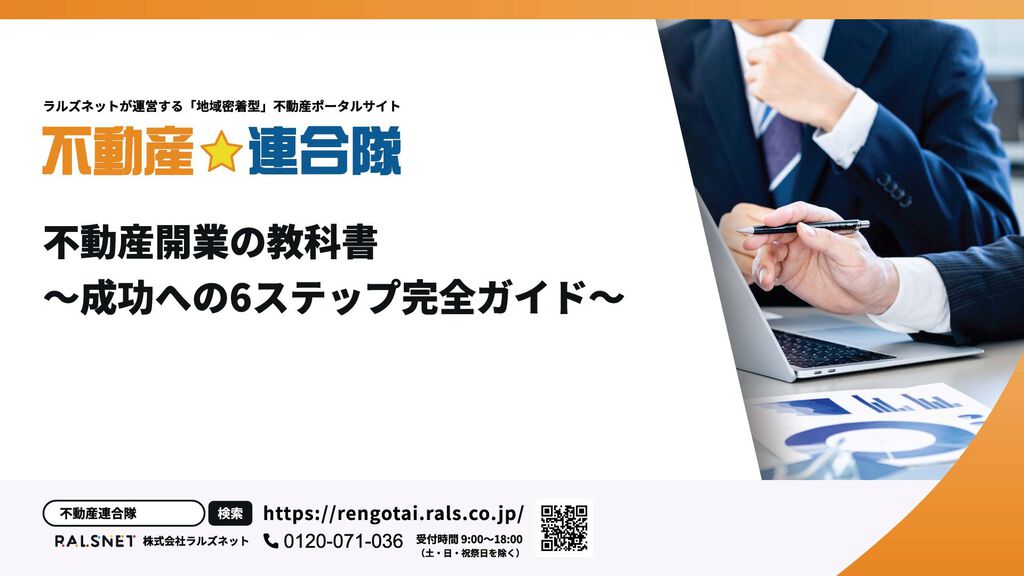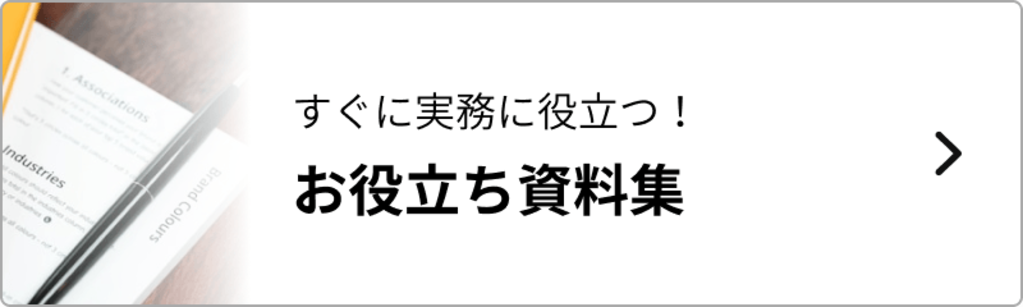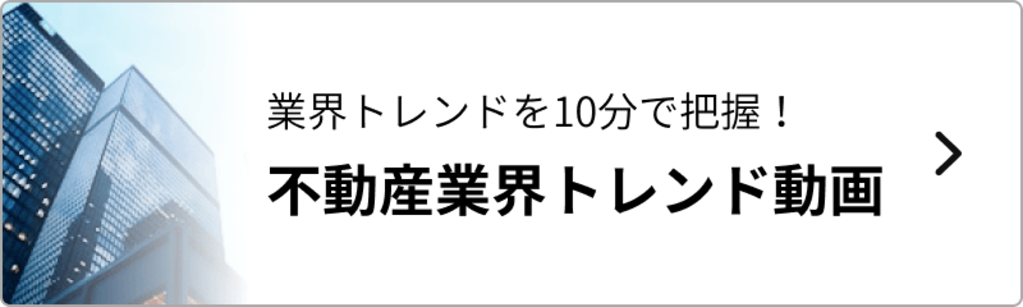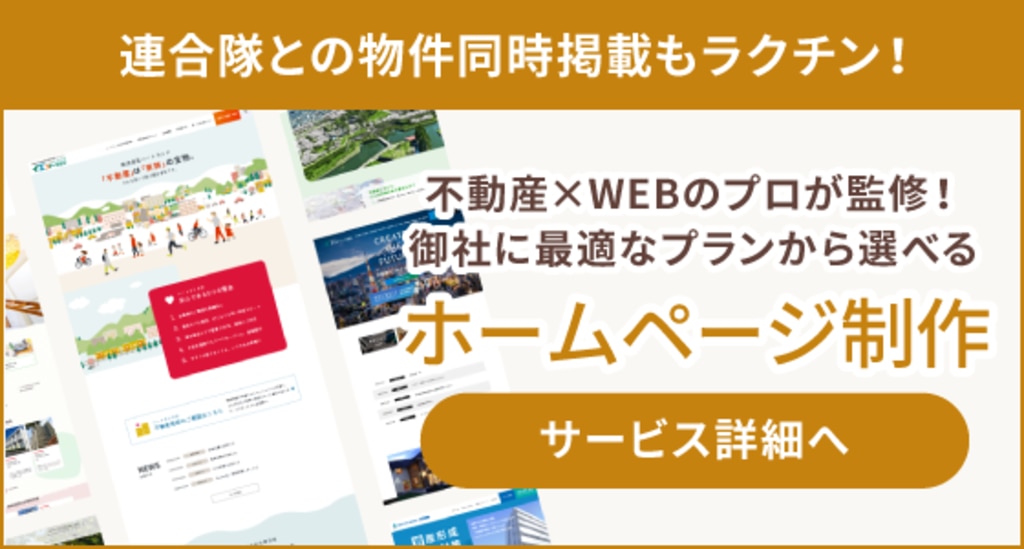2025年建築基準法改正のポイント|不動産業界への影響をわかりやすく解説!
2025年4月に施行される建築基準法の改正は、建築・不動産業界に大きな影響を与える重要な変更です。とくに建築確認申請の厳格化や省エネ基準の義務化など、多くのポイントでルールが変わります。
「どんな改正があるの?」
「不動産業界にはどんな影響があるの?」
このように疑問に思う方も多いでしょう。
そこで本記事では、2025年の建築基準法改正のポイントと不動産業界への影響をわかりやすく解説します。
建築に関わる方はもちろん、住宅を購入予定の方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
目次[非表示]
- 1.建築基準法とは?まずは基本をおさらい!
- 2.2025年の建築基準法改正の重要ポイント
- 2.1.4号特例の縮小|小規模建築の確認申請が必要に
- 2.2.木造建築の構造計算義務化|適用範囲が500㎡超→300㎡超に縮小
- 2.3.耐火性能の基準変更|木造ビルやマンション建築に影響大
- 2.4.中層木造建築の耐火基準が合理化|5〜9階建ての建設が簡単に
- 2.5.既存不適格建築の扱い|違反建築物のルール緩和はある?
- 2.6.省エネ基準の適合義務化|すべての新築建築物に適用
- 2.7.壁量計算の強化|必要壁量が約1.6倍に増加
- 3.2025年の建築基準法改正が必要な理由
- 4.2025年の建築基準法改正で不動産業界はどう変わる?
- 5.建築基準法の改正履歴は見れる?|過去の改正をチェック!
- 6.まとめ
建築基準法とは?まずは基本をおさらい!

建築基準法は、安全で快適な建築物をつくるためのルールを定めた法律です。
耐震・防火・採光・換気などの基準を設け、人々が安心して暮らせる環境を整えることを目的としています。
1950年に制定されて以来、大地震や火災などの災害を受けて改正が繰り返されてきました。
たとえば、1981年の「新耐震基準」導入や、1995年の阪神・淡路大震災後の「耐震補強の義務化」などがあります。
2025年の改正では、耐震性能の強化・省エネ基準の適合義務化・小規模建築物の確認申請厳格化が行われます。
これにより、より安全で環境に優しい建築物が増えることが期待されますが、設計や施工への影響も避けられません。
法改正の内容を理解し、適切に対応していくことが重要です。
2025年の建築基準法改正の重要ポイント

2025年の建築基準法改正では、主に建築物の安全性向上や環境負荷の低減を目的とした変更が行われます。
とくに4号特例の縮小や省エネ基準の適合義務化などが注目されており、不動産業界にも大きな影響があります。
具体的な改正内容について、詳しく見ていきましょう。
4号特例の縮小|小規模建築の確認申請が必要に
4号特例とは、小規模な建築物に対する建築確認申請の審査を簡略化する制度です。
具体的には、「木造2階建て以下かつ延床面積500㎡以下の住宅」や「平屋かつ鉄骨造・RC造で200㎡以下の建築物」などが対象で、これまでは建築士の責任で設計・施工が進められました。
しかし、2025年の建築基準法改正により、この4号特例が縮小され、新たに2号または3号に分けられます。
区分 |
定義 |
建築確認 |
|---|---|---|
4号建築物 |
・木造2階建て以下かつ延床面積500㎡以下の住宅 |
原則不要 |
新2号建築物 |
・木造2階建て |
必須 |
新3号建築物 |
・木造平家建てかつ述べ面積200㎡以下の建物 |
必須 |
改正後は「構造」や「防火」に関する審査が厳格化され、建築士の設計だけではなく、行政の審査が必要になるケースが増えます。
4号特例の縮小による影響は、以下のとおりです。
- これまで確認申請が不要だった小規模建築物も対象に
- 設計者の業務負担が増加し、建築コストが上昇する可能性
- 施工期間が長期化する可能性がある
確認申請の対象が広がることで、設計や申請業務の負担が増えるのは避けられません。
ただ、その分安全性や耐震性が向上し、より信頼できる建築物が増えるというメリットもあります。
木造建築の構造計算義務化|適用範囲が500㎡超→300㎡超に縮小
2025年の建築基準法改正により、木造建築の構造計算が義務化され、適用範囲も縮小されます。
構造計算とは、建物が安全に建てられるかをチェックするための計算のことです。
たとえば、これまで延べ面積500㎡超の木造建築物に構造計算が求められていましたが、改正後は300㎡超の建築物にまで適用範囲が広がります。
詳細は、以下のとおりです。
| 項目 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
構造計算が 必要な延べ面積 |
500㎡超 |
300㎡超 |
高層木造建築物の構造計算 |
高さ13m(軒高9m)を超える高層木造建築物 |
3階以下かつ高さ16m以下の木造建築物 |
設計・工事監督 |
一級建築士のみ可能 |
二級建築士も設計可能 |
「小さな建物も対象になるの?」と思うかもしれませんが、安全性を考えれば必要な改正とも言えるでしょう。
影響を受けるポイントは、以下のとおりです。
- 木造中層ビルやマンションの建設コストが上昇
- 耐震・耐風性能の強化が求められる
- 木造建築の設計の自由度が一部制限される可能性
一方で、木造建築の構造計算義務化により、耐震基準が強化され、安全性の高い建物が増えることは大きなメリットです。
また、災害リスクの低減に加え、長期的な維持管理コストの削減につながる可能性もあります。
耐火性能の基準変更|木造ビルやマンション建築に影響大
2025年の建築基準法改正により、木造建築物の耐火性能基準が見直されます。
とくに大規模な木造建築物の防火規定が変更され、これまで難しかった木造での建設が容易になるでしょう。
項目 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
木造大規模建築物の耐火規定 |
・3,000㎡毎に耐火構造体で区画または壁 ・柱などを耐火構造とする |
構造木材をそのまま見せる「あらわし」が使用可能 |
改正前は主要な木造箇所を不燃材料で保護する必要がありましたが、改正後は温かみのある木造箇所をそのまま見える状態に設計できます。
これは、木材利用の促進を目的とした規制緩和の一環です。
一方で、耐火性の高い建材の使用が求められるため、建築コストの上昇や設計の見直しが必要になる可能性もあります。
中層木造建築の耐火基準が合理化|5〜9階建ての建設が簡単に
2025年の建築基準法の改正により、5〜9階建ての建設がより簡単になります。
これまでは厳しい基準がありましたが、以下の表のとおり改正されます。
改正前 |
5階~14階建ての建築物→120分の耐火性能が必要 |
|---|---|
改正後 |
5階~9建て以下の建築物の最下層→90分の耐火性で設計が可能へ |
これにより、これまで技術的・コスト的な時間が高かった木造中高層建築のハードルが下がるでしょう。
また、木材の地域活用などの観点から、公共施設や商業における木造の導入が拡大する可能性が高いです。
既存不適格建築の扱い|違反建築物のルール緩和はある?
2025年の建築基準法改正により、既存の不適格建築物が直ちに違反となることはありません。
既存不適格建築物とは、建てられた当時のルールでは違反していなかったが、改正された建築基準法には適さない建物のことです。
しかし、増改築や用途変更を行う際には、新基準に適合させる必要があります。
たとえば、耐震基準や省エネ基準が厳しくなるため、リフォーム時に補強工事が求められる可能性があります。
また、建て替え時には現行の建ぺい率や容積率が適用され、以前より小さな建物しか建てられないケースもあるでしょう。
将来的な売却にも制約が生じる可能性があるため、事前に確認することが大切です。
省エネ基準の適合義務化|すべての新築建築物に適用
2025年の改正では、すべての新築建築物に省エネ基準の適合が義務化されます。
省エネ基準とは、建物がエネルギーを効率よく使うために必要なルールのことです。
これまでは、延床面積300㎡以上の建築物が対象でしたが、小規模な住宅も対象になります。
省エネ基準適合義務化の影響は、以下のとおりです。
- 新築住宅の断熱性能やエネルギー効率が向上
- 建築コストが上がるが、光熱費の削減につながる
- 環境に優しい住宅が普及する
省エネ基準の義務化により、住宅の光熱費が削減され、環境にも優しい住宅が増えると期待されています。
しかし、建築物の省エネ性能の計算結果を行う手間があり、施工計画に時間がかかる可能性があるでしょう。
壁量計算の強化|必要壁量が約1.6倍に増加
今回の改正では、耐震性をより高めるために、必要な壁の量が従来の1.6倍に増えることになりました。
壁量計算とは、建築物の耐震性を確保するために、必要な壁の量を算出する計算方法です。
とくに木造建築では、耐力壁(地震や風の揺れに耐えるための壁)の適切な配置が建物の強度を決める重要な要素になります。
「壁の量が増えると、部屋が狭くなるのでは?」という懸念があるかもしれません。
しかし、壁の配置や設計の工夫により、室内空間を有効に活用できます。
また、耐震性が向上することで、安全で安心な住まいを実現できるでしょう。
参考:国土交通省|建築基準法等に関する解説資料とQ&A
2025年の建築基準法改正が必要な理由

建築基準法改正は、災害対策と環境問題への対応という2つの大きな理由から実施されます。
日本は地震や台風が多く、建築物の耐震性や防火性能を高めることは命を守るために欠かせません。 また、世界的な環境対策の流れを受け、エネルギー消費の少ない建物を増やすことが急務となっています。
熊本地震では旧耐震基準の建物が大きな被害を受け、多くの家屋が倒壊しました。
この経験をもとに、より強い耐震基準が求められるようになり、建築物の構造計算や壁量計算が厳格化されることになりました。
近年の異常気象による大規模火災を防ぐために、木造建築の耐火基準も見直されます。
さらに、政府は2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、すべての新築建築物に省エネ基準の適合を義務化します。
これにより、断熱性能が向上し、高効率な設備の導入も進みます。
その結果、環境に優しい住宅が広まる未来が、すぐそこまで来ているかもしれませんね。
ただし、今回の改正により建物の安全性と快適性が向上する一方で、建築コストの増加や設計の自由度の制限が課題となります。
新基準に対応するために、事前の準備と慎重な計画を立てましょう。
2025年の建築基準法改正で不動産業界はどう変わる?

2025年の建築基準法改正は、設計・施工の現場や不動産市場に大きな影響を与えるものです。
これまでよりも安全性や省エネ性能が求められる一方で、設計の自由度やコスト面での課題も増えるでしょう。
建築士や施工業者、不動産業界にどのような変化が起こるのか、具体的に解説します。
設計・施工への影響|建築士や施工業者の対応は?
2025年の改正では、設計・施工のプロセスが大きく変わる可能性があります。
とくに「4号特例の縮小」や「木造建築の構造計算義務化」により、これまでよりも慎重な設計や施工が求められるようになります。
具体的な影響 |
改正内容 |
|---|---|
小規模建築の |
4号特例の縮小により、小規模な住宅や店舗の建築でも、建築確認申請が必要になる。 |
構造計算の義務化 |
木造3階建て以上の建築物に加え、一定の面積を超える建築物でも構造計算が必須になる。 |
耐火・防火基準の強化 |
木造ビルや商業施設に対する耐火性能の基準が厳格化し、施工方法や使用できる材料が変わる。 |
「これまで簡単に建てられた建物も、手続きが増えてしまうのでは?」
このような心配する方もいるでしょう。
たしかに設計や施工の手間が増える可能性はありますが、その分、安全性の高い建築物が増えるというメリットもあります。
また、建築士や施工業者は改正後の基準を理解することが大切です。
細かな改正まで把握することは、お客様から信頼されるきっかけになるでしょう。
コストや工期の変化|家づくりの価格やスケジュールへの影響
2025年の建築基準法改正によって、建築コストの上昇や工期の延長が懸念されています。
とくに省エネ基準の適合義務化や耐震・防火性能の強化により、必要な設備や材料が増えることが影響しそうです。
考えられる影響は、以下のとおりです。
コスト増加の主な要因 |
影響 |
|---|---|
建築確認申請の手続き増加 |
審査が厳格化することで、確認申請の手続き費用が増える可能性がある。 |
高性能な建材の使用 |
省エネ基準や耐火基準をクリアするため、より高価な建材が必要になる。 |
設計や施工の手間が増える |
構造計算が義務化されることで、設計業務が複雑になり、コストが上がる。 |
「家づくりのコストがどんどん上がるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
たしかに初期費用は増える可能性がありますが、省エネ性能は向上します。
そのため光熱費を削減でき、長期的にはコストメリットがあるとも言えます。
また、工期の面でも影響が予想されます。
確認申請の厳格化や構造計算の義務化により、設計や審査に時間がかかり、着工までの期間が延びる可能性があります。
建築基準法の改正履歴は見れる?|過去の改正をチェック!

建築基準法は、1950年に制定されて以来、時代の変化や災害の教訓をもとに何度も改正されてきました。
とくに大規模な地震や火災が発生するたびに、建築物の安全性を高めるための見直しが行われています。では、過去の主要な改正を振り返ってみましょう。
改正年 |
主な改正内容 |
背景 |
|---|---|---|
1981年 |
新耐震基準の導入 |
1978年の宮城県沖地震で多くの建物が倒壊したため |
1995年 |
耐震診断・補強の推進 |
阪神・淡路大震災で旧耐震基準の建物が多数倒壊したため |
2000年 |
木造住宅の耐震基準強化 |
構造計算偽装問題が発覚し、建築基準の見直しが必要になったため |
2016年 |
耐震基準のさらなる強化 |
熊本地震で「新耐震基準」の建物でも大きな被害が出たため |
過去の改正を見てもわかるように、災害のたびに建築基準法が見直され、より安全な建物づくりが求められるようになっています。
とくに1981年の「新耐震基準」は大きな転換点で、それ以前の建物とそれ以降の建物では耐震性能に大きな違いがあります。
「過去の改正内容を詳しく調べたい」
そんな方は「国土交通省のホームページ」や「日本法令索引」で詳細な改正履歴をチェックしてみてくださいね。
また、建築士や不動産業者に相談すれば、自分が所有している建物がどの基準に適合しているかを確認することも可能です。
2025年の改正も、これまでの改正と同じように、より安全で環境に配慮した建築を目指すためのものです。
今後、さらに基準が厳しくなる可能性もあるため、早めに情報収集をして備えておくことが重要でしょう。
まとめ

今回は、2025年の建築基準法改正の内容と、その影響について解説しました。
改正により、4号特例の縮小や木造建築の構造計算義務化、省エネ基準の適合義務化などが実施され、建築業界や不動産業界にさまざまな変化をもたらします。
とくに確認申請の厳格化や建築コストの上昇など、設計や施工の現場に影響が出る可能性が高く、改正に向けた準備が重要になります。
一方で、耐震性や防火性能の向上、省エネ住宅の普及など、建築物の安全性や快適性が向上するメリットも期待されます。
今後の建築・不動産市場の変化を見据え、新基準に適応できるよう、早めの情報収集と対策を進めていきましょう。