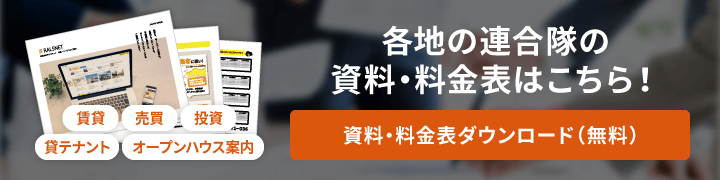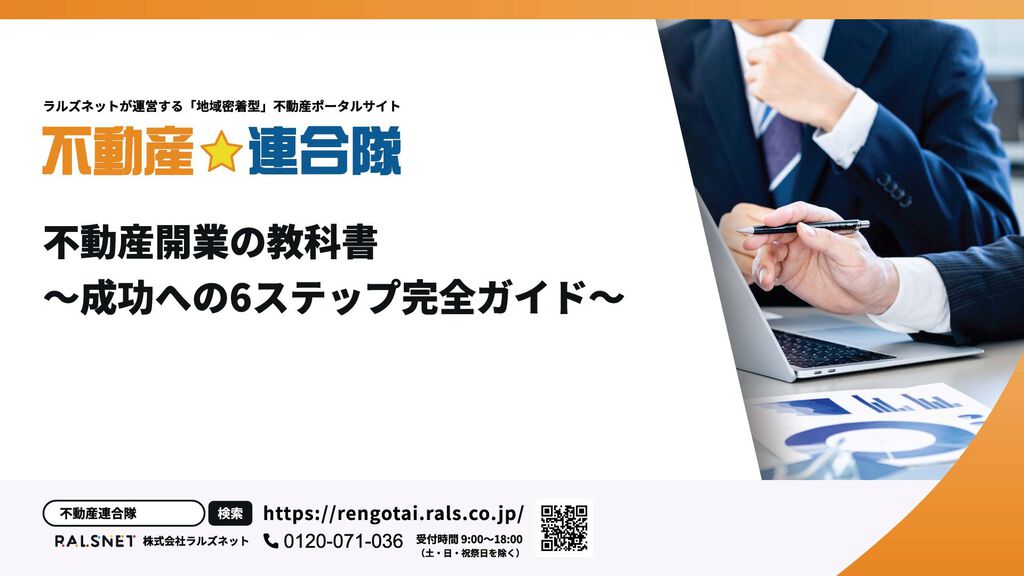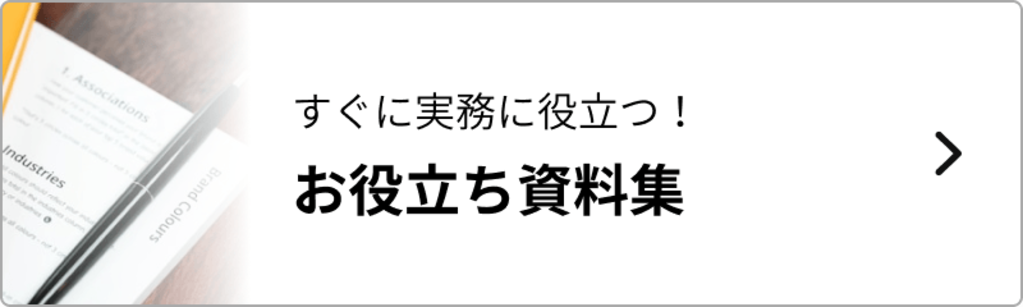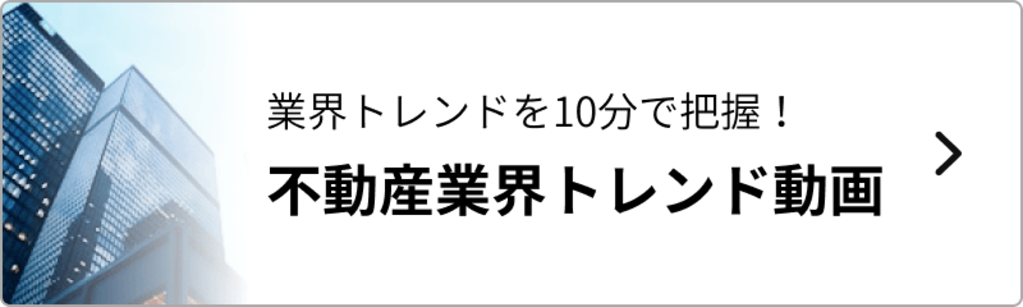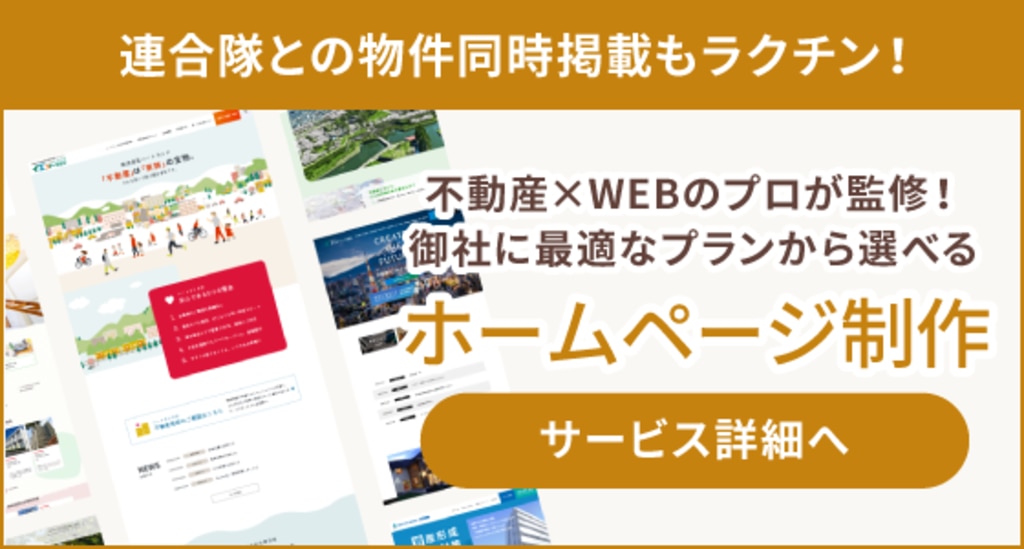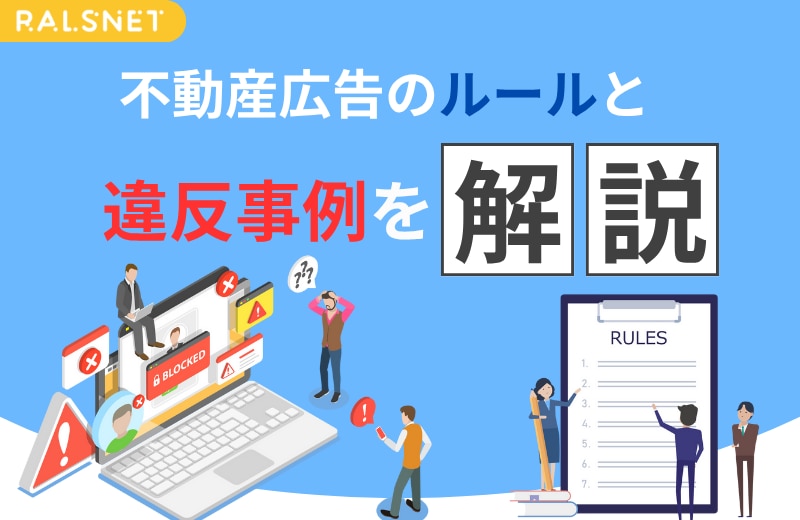
不動産広告のルールから失敗しないために知るべき違反事例まで解説
不動産広告をめぐる法規制は、年々複雑化。近年は、SNSやAIの普及により個人や小規模事会社でも簡単に広告を打てるようになりました。一方で、誤認表示や法令違反が起きやすい環境も広がっています。
広告制作に関わるすべての不動産関係者は、宅建業法や表示規約に基づく「最低限の知識」を持っていないと、無意識のうちに違法な表現を使用してしまう可能性も。現場担当者の「知らなかった」が、会社全体の信頼低下につながるリスクも見過ごせません。不動産広告は「魅せ方」だけでなく、「適法性」こそが最も重要です。
この記事を読むことで、 トラブルを防ぎつつ反響を最大化する広告設計ができるようになります。ぜひ、参考にしてみてください。
目次[非表示]
不動産広告のルールを押さえよう

不動産広告には、宅建業法や表示規約による厳格なルールがあります。 違反すれば行政処分や違約金の対象となるため、正確で誠実な広告づくりが必要です。ここでは、宅建業法や表示規約による 主な規制内容を解説します。
宅建業法による規制
宅建業法では、消費者保護と取引の公正を目的として、以下の広告に対するルールを定めています。
|
それぞれの規制内容を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
誇大広告の禁止
宅建業法第32条では、 物件や取引条件を実際よりも良く見せる「誇大広告」が禁止されています。たとえば、以下のような内容です。
|
また、外観写真の加工やCGによる美化も、実物と大きく違えば誇大表示と判断されることがあります。悪質な場合は、業務停止命令や免許取消処分を受ける可能性もあるでしょう。不動産広告では、実測や根拠資料に基づいた正確な情報掲載が基本です。集客を優先して誇張表現を用いるのではなく、 信頼につながる誠実な広告作成が求められます。
広告の開始時期の制限
宅建業法第33条では、 建築確認を受けていない新築住宅や、造成工事の許可を受けていない宅地の広告を原則禁止しています。未完成物件の場合は、建築確認後や開発許可を受けた後にしか広告を出せません。
一方で、取引開始時期などを明示する「予告広告」は、一定条件を満たす場合に限り、早期の広告が可能になるケースもあります。ただし、建築確認や開発許可を受けていることが前提です。 このように、 広告の開始時期や条件などを把握しておくことで、トラブルを回避しやすくなります。
取引態様の明示
宅建業法第34条では、 不動産広告に売主・代理・媒介(仲介)などの「取引態様」を明記することが義務付けられています。取引態様の記載があることで、消費者は仲介手数料の有無や、誰が契約の当事者になるのかを正しく判断することが可能です。
たとえば「媒介」であれば、買主は別途仲介手数料を支払う必要があります。しかし「売主」とあれば、手数料が不要な可能性もあるでしょう。取引態様は、契約の基本条件に直結する重要な情報であり、誤記・省略・虚偽表示は重大な違反です。広告作成時には、 必ず正しい取引態様を明示するようにしましょう。
表示規約(公正競争規約)による規制

表示規約( 公正競争規約)では、宅建業法を補完しつつ 消費者の誤認を防ぐ目的で、主に以下のようなルールを定めています。
|
広告表現に関する具体的な制限や表示の義務が定められているため、ぜひ覚えておきましょう 。
必要な表示事項
物件の基本情報や取引条件は、 広告に明確かつ具体的に表示しなければいけません。これを「必要な表示事項」と呼び、主に以下の項目が該当します。
|
加えて建築条件付き宅地の場合は、その旨と建築条件の内容も表示が必要です。これらの情報は、 消費者の購買・契約判断に直結するため、 誤記・省略には注意しましょう。
特定事項の明示義務
消費者にとって重要度の高い項目については、 目立つ形で明示する義務があります。たとえば、以下のような情報が重要度の高い項目に該当します。
|
これらは、 購入後にトラブルになりやすい内容であるため、 広告段階で明確に表示しなければいけません。小さな注記で済ませたり、広告に記載したりしないと違反になるため注意が必要です。
物件の内容・取引条件等に係る表示基準
物件の情報や契約条件に関する表示は、 誤認を防ぐために細かな基準が定められています。
|
また、設備の記載(例:オール電化・床暖房付きなど)は、実際に物件に備わっている設備であることを確認のうえ、記載しなければいけません。表示基準を逸脱すると、悪意がなくても違反とされることがあるため、 必ず正しい表示なのかを確認しましょう。
特定用語の使用基準

使用すれば魅力的な用語でも、 特定の条件下でしか使用できない「特定用語」があります。特定用語と使用条件の例は、以下の通りです。
用語 | 使用条件 |
駅近 | 駅からの距離が実測で徒歩10分以内の場合のみ使用可能 |
格安 | 周辺相場と比較して合理的に安価である根拠がある場合に限る |
完全 | 完全に近い状態であることを証明できる具体的な基準が必要 |
曖昧な印象を与える言葉は消費者に誤解を与える恐れがあるため、使用には十分な根拠が必要です。 視覚的に目立つ表現ほど、慎重に扱うべきでしょう。
不当な二重価格表示
二重価格表示においては、 「旧価格」や「定価」との比較を行う場合、適正な根拠が求められます。主なポイントは、以下のとおりです。
|
不当な二重価格表示は、実際よりも有利であると誤認させる「有利誤認表示」にあたる可能性が高く、監視対象にもなります。割引情報やキャンペーン価格を表示する際には、 正確な根拠を残しておくようにしましょう。
おとり広告
「おとり広告」とは、 実際には契約できない物件を広告として掲載する行為です。消費者を誘引する目的で虚偽の情報を掲載することは、悪質な広告違反のひとつです。たとえば、以下のような事例が挙げられます。
|
定期的な物件確認や、広告掲載管理システムの運用がされていない会社では、発生しやすい違反です。会社にとっても信頼喪失につながるため、社内体制の整備が不可欠といえます。
不当表示
上記に該当しない場合でも、 以下のような誤解を与える表示は「不当表示」として違反となります。
|
これらは、表示義務のない項目でも、あえて記載した場合には真実と一致していなければならないという規定によるものです。掲載内容はすべて“契約に影響を与える「情報」であるという前提で、 正確性を確保しましょう。
不動産広告の種類と費用相場
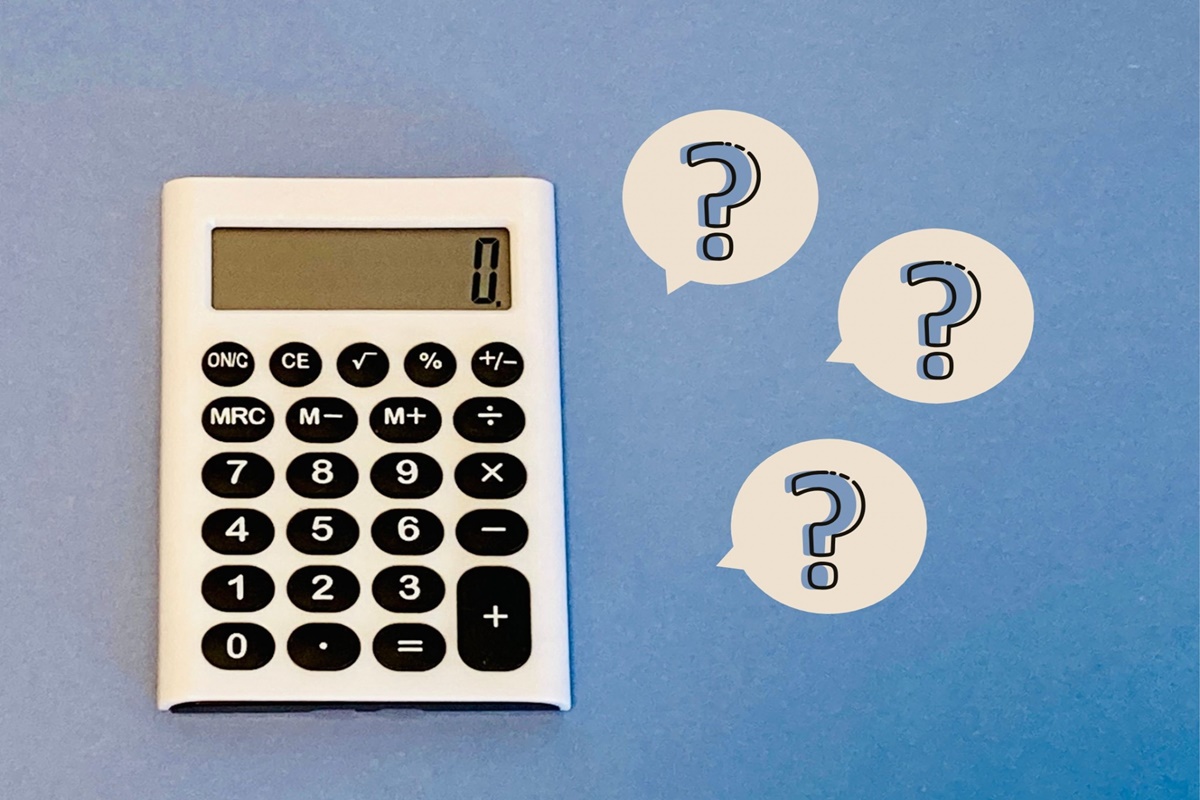
不動産業界では、 物件の認知度を高めて反響を獲得するために、さまざまな広告を活用しています。 それぞれの特徴や費用相場が異なるため、 ターゲットや物件の特性に応じた使い分けが重要です。今回はオフラインとオンラインに分けて、主な不動産広告と費用相場を解説します。
オフライン広告
紙媒体や実店舗などを活用したオフライン広告は、 地域密着型の集客や高齢層への訴求に効果的です。代表的なオンライン広告を見てみましょう。
種類 | 特徴 | 費用相場 |
チラシ | 地域密着で周辺住民に直接アプローチ可能。物件情報や地図を掲載しやすい。 | ・ポスティング:約3〜8円/部 ・新聞折込:約4〜10円/部 |
店頭広告 | 通行人に物件を訴求できる。即効性があり、店舗の視認性向上にも寄与。 | ・のぼり(デザイン込):2,000円〜 /枚 |
看板広告 | 人目につきやすく、反復訴求に効果的。サイズや設置場所によって、費用は大きく変動。 | ・野立て看板:10万〜50万円ほど ・突き出し看板:5~20万円ほど |
フリーペーパー・住宅情報誌掲載 | 地域ごとの購買層へのアプローチが可能。掲載期間や面積で費用が決定。 | ・1/8ページ: 月3万〜10万円ほど ・1/4ページ:月5~20万円ほど ・1/2ページ:10~40万円ほど ・1ページ:20~80万円ほど |
DM・手紙 | ピンポイントに物件情報や査定案内を送れる。信頼性が高く、反響率も高い。 | 印刷+発送:100〜200円/通 |
オンライン広告
インターネットを活用したオンライン広告は、 広範囲の集客や若年層への訴求に効果的です。代表的なオンライン広告を、ご紹介します。
種類 | 特徴 | 費用相場 |
SNS広告(Instagram、Facebookなど) | 詳細なターゲティングが可能。若年層へのアプローチに有効。 | 1クリック:約20~200円 |
動画広告(YouTubeなど) | 視覚的な訴求力が高く、物件の魅力を伝えやすい。 | 1再生:約2~25円 |
リスティング広告(Yahoo、Google広告) | 検索キーワードに連動して表示。即効性が高い。 | 1クリック:約50~1,000円 |
ディスプレイ広告 | 画像やバナーで視覚的に訴求。ブランド認知度向上に効果的。 | 1クリック:約50~100円 |
ポータルサイト掲載(SUUMO、at homeなど) | 多くのユーザーが利用。物件情報の露出度が高い。 | 1枠:1,000円~ 5件:約1万円~ 月額:1.8万円~ |
自社サイト・ブログ運営 | 自社の強みや物件情報を発信。長期的な集客基盤となる。 | サイト制作費:20万円~ ドメイン・サーバー代:約5,000~3万円/年 記事作成費(外注):約5,000~2万円 |
反響を生む不動産広告デザインの作り方

魅力的な不動産広告を作るには、ターゲットに響くデザインや効果測定が不可欠です。写真やキャッチコピーだけでなく、媒体に応じた最適化や反響測定などを解説します。
不動産広告の基本構成と役割
不動産広告で反響を得るには、ただ情報を羅列するだけでは不十分です。情報の「配置」と「順序」がユーザーの視線誘導と行動喚起を左右するため、 設計段階から明確な意図を持って構成しましょう。広告に必要な基本要素は、以下のとおりです。
|
これらをどう配置するかによって、広告の成果は大きく変わります。紙媒体やWebのLP(ランディングページ)で 多用されるのが「Z型・N型レイアウト」です。
レイアウト | 特徴 | 適している媒体 |
Z型 |
|
|
N型 |
|
|
広告を作成する際は、ユーザーの視線と心理を意識して、 「伝えたい情報」より「読みやすく、伝わる情報」を優先して配置するのがポイントです。
視覚で差がつく写真・動画のコツ
不動産広告では、 写真や動画の質が反響数を大きく左右します。視覚で差をつけるために意識すべき項目を以下にピックアップしたので、ぜひ参考にしてみてください。
写真 |
|
動画 |
|
写真は瞬時の魅力伝達に、動画は疑似内覧体験に有効です。物件や広告媒体に応じて最適な手法を組み合わせることで、反響率の向上につながります。
広告コピーの書き方で反響アップ

広告コピーは、 ターゲット層のニーズや悩みに共感する言葉を使うことが重要です。物件の特徴を単純に伝えるだけでなく、「暮らしのイメージ」を意識した言葉選びが効果を発揮します。たとえば、以下のような言葉選びを意識してみましょう。
|
「事実+感情」で印象を深めるのがポイントです。さらに、行動喚起(CTA)として「今週末の見学予約受付中」などの具体的表現を加えると反響が高まります。
媒体ごとの最適化ポイント
広告媒体によって、 伝えるべき情報量やデザインの方向性が異なります。たとえば、以下の広告媒体における主な最適化ポイントを見てみましょう。
広告媒体 | ターゲット | 主な最適化ポイント |
新聞折込 チラシ |
|
|
ポスティングチラシ |
|
|
店頭チラシ |
|
|
ポータルサイト |
|
|
SNS・Web広告 |
|
|
アプローチしたいターゲットに適した媒体を選び、 広告を最適化することで、問合せや来場者数を伸ばしやすくなります。
KPI設計と運用のコツ
適切なKPI設計と運用も、不動産広告を成功させるうえで欠かせません。KPI(重要業績評価指標)とは、「ゴールまでの中間目標を数値で表した指標」のことです。以下のようにゴールを決めて、KPIの設定をしていきます。
ゴール | KPI例 |
資料請求を増やす |
|
問合せを増やす |
|
来場を増やす |
|
認知度を上げる |
|
次に行うのは、「1.表示 → 2.興味 → 3.問合せ →4. 来場 → 5.成約 」という、ファネル(流れ)を意識したKPI設計です。 ファネルの各段階ごとにKPIを設定することで、それぞれの改善点が見えやすくなります。
ファネル(流れ) | KPI例 |
1.表示 | 表示回数(インプレッション) |
2.興味 | クリック数 |
3.問合せ | 問合せ数 |
4.来場 | 来場数 |
5.成約 | コンバージョン率(CTR) |
不動産広告を運用するコツは、以下のとおりです。
|
KPI設計と運用のコツを押さえることで、 広告の無駄を減らし、集客や成約につなげやすくなるでしょう。ぜひ、意識して取り組んでみてください。
不動産広告で失敗しないために知るべき失敗事例
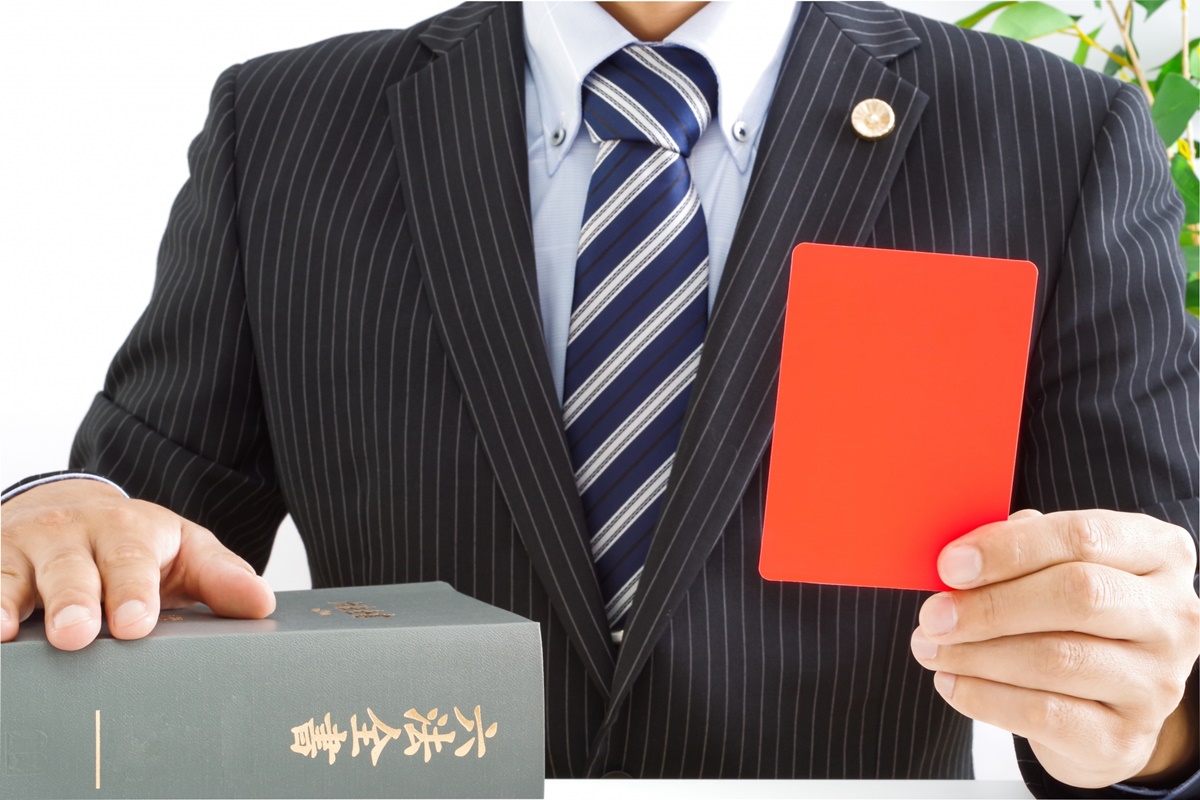
不動産広告で失敗しないためには、 「どのような失敗事例があるのか」を知ることも大切です。失敗事例を知っておけば、事前に対策を行えます。今回は5社の失敗事例を紹介するので、ぜひ自社の不動産広告に役立ててください。
A社の事例~おとり広告など~
A社は、自社ホームページ上で不適切な広告表示を行い、違約金80万円の処分を受けました。主な違反は、以下の通りです。
違反 | 詳細 |
おとり広告 | 入居済み→最大3~4か月間広告を継続 |
費用の不記載 | 10物件:鍵交換費用(例:2.75万円)、クリーニング費用(例:8.23万円)などの不記載 |
敷金の誤表示 | 「敷金1か月・ペット可」と記載するも、実際はペット飼育時に敷金2か月が必要 |
A社は過去にも2回(2014・2020年)の違反歴があり、今回は3回目となります。原因として「システムの不具合に気付かなかった」と釈明しているものの、調査時点で4か月も誤表示に気付かない点から、 日常的なチェック体制の不備が浮き彫りになりました。
B社の事例~保証料の誤認表示など~
B社は、ポータルサイト上で「実際よりも優良・有利」と誤認される不当表示を多数行っていました。主な違反は、以下のとおりです。
違反 | 詳細 |
保証会社に関する不当表示 | 「保証会社利用可 貸主指定」と表示も、実際は保証会社との契約必須かつ高額な家賃保証料が発生(契約時20.1万円、毎月5,040円) |
ペット可の誤認表示 | 「ペット可」のみ記載するも、実際は敷金1か月分の追加費用が必要 |
敷金・償却に関する不当表示 | 「敷金460万円」、「敷引・償却 -」と表示するも、 実際には、敷金460万円のうち230万円の償却が不記載 |
違反の背景には、広告管理を社長が行い、社内で十分なチェック体制を構築していなかったことが挙げられます。こうした表示の不備は、契約時のトラブルに直結するおそれがあり、 広告担当者の法令理解と運用体制の見直しが求められるでしょう。
C社の事例~鍵交換費用の非表示など~
C社は、ポータルサイトにて複数の表示規約違反が確認され、違約金50万円の措置を受けました。主な違反は、以下のとおりです。
違反 | 詳細 |
鍵交換費用の非表示 | 鍵交換費用1.65万円の不記載 |
有料設備の無料誤認表示 | 「バイク置き場あり」とのみ表示するも、実際は月額1,100円かかることの不記載 |
おとり広告 | 契約済みで取引できないにも関わらず、最大1か月以上広告を継続 |
問題なのは、C社が2022年にも同様の「おとり広告」で違反措置(25万円)を受けていたにも関わらず、別の店舗で再発した点です。今回の違反は組織全体としての広告に対する意識の低さ、店舗間の連携不足を示しているといえるでしょう。 広告ルールの順守を徹底し、再発防止のための社内統一と情報共有体制の見直しが急務です。
D社の事例~諸費用の非表示など~

D社は、自社ホームページ上で複数の表示規約違反が認められ、違約金50万円の措置を受けました。主な違反は、以下のとおりです。
違反 | 詳細 |
諸費用の非表示 | ルームクリーニング費用(例:6.05万円)やネット使用料(月額1,650円)の不記載 |
設備の誤認表示 | 「駐車場有」と記載していたが、実際には駐車場なし |
必須情報の未記載 | 入居可能時期の未記載 |
D社は、「管理会社からの情報を一括で取り込むシステムを使用していたが、うまく反映されていなかった」と説明しています。しかし、実際にはシステムへの過信が根本的な原因で、確認作業を行っていかなったことが問題でした。 最終的な「人による確認」の徹底、広告担当者の責任と意識の向上が求められます。
E社の事例~面積表示の不備など~
E社は、2ポータルサイト上で表示規約違反が認められ、15万円の違約金課徴を受けました。主な違反は、以下のとおりです。
違反 | 詳細 |
面積表示の不適切 | 「建物面積105.4㎡(壁芯)」と記載するも、車庫面積12.66㎡を含むことや内訳の不記載 |
おとり広告 | 契約済みで取引できない物件を、1~4か月以上にわたり広告を継続 |
表示項目の記載漏れ | 新築住宅に必要な「私道負担面積(17.81㎡)」の不記載 |
E社は、「これまではパートに入力を任せきりで、社員の確認が行われていなかった」と説明しています。今回の事例からも明らかなように、 入力担当者が誰であれ、複数人によるチェック体制の整備と、表示規約の理解と継続的な研修参加が重要です。個別の気の緩みが違反につながるリスクは依然として残っているため、引き続きの注意が必要だといえます。
不動産広告の今後とトレンド
不動産広告は今、大きな転換期を迎えています。 消費者の情報収集行動は「紙からスマホ・SNS」へと大きくシフトし、物件検索には視覚的でわかりやすいコンテンツが求められる時代に。トレンドとしては動画内見や360°画像、Instagram・TikTokを活用したプロモーションなど、物件の「体験」を届ける広告手法が増えています。さらに、AIによるレコメンドやチャットボットによる接客など、デジタル技術の導入も進行中です。
一方で、おとり広告や費用の不明瞭な表示などへの監視は年々強化されており、法令順守の重要性も再認識されています。広告表現にはクリエイティブさだけでなく、正確性と信頼性の両立が不可欠です。これからの不動産広告は、 「伝える」から「質の高い情報・体験を届ける」へと進化しています。時代に合った広告戦略の見直しが、企業の差別化を左右するでしょう。
効果的な不動産広告を学んで集客・売上アップにつなげよう!

不動産広告は 宅建業法や表示規約で厳しく規制されており、正確な情報を掲載することが重要です。そのうえで、広告の種類や費用、写真や動画の活用などの集客につながる要素を押さえるようにしましょう。 最新の情報や実践的ノウハウを学ぶことで、リスクを抑えながら競合他社と差をつける広告運用が行えます。
不動産広告に関する「よくある質問」
不動産広告で反響を取るにはどうすればいい?
反響を得るには、ターゲットの生活ニーズに寄り添った情報発信が重要です。物件の魅力や差別化ポイントを明確に打ち出し、写真・間取り・費用条件などの情報は正確かつ丁寧に掲載しましょう。信頼感を与える表現と迅速な対応も、反響率向上につながります。
不動産広告で集客しやすいタイトルの付け方は?
タイトルは一目で物件の魅力や特長が伝わるよう、「駅徒歩5分」「ペット可」「南向き3LDK」など検索されやすいキーワードを含めると効果的です。数字や利便性といったワードを取り入れるとクリック率が上がり、集客力も高まります。
不動産広告で掲載写真は何枚がベスト?
掲載写真は20〜30枚程度が理想的です。外観・リビング・キッチン・水回り・収納・眺望など、物件全体のイメージが伝わる構成を意識しましょう。明るく鮮明な写真を選び、生活動線がわかる順番で並べることで、内見予約につながりやすくなります。
不動産広告で避けるべき表現は?
「完璧・絶対・最高・激安・完売」などの表現や、事実と異なる記載は不当表示に該当する恐れがあります。費用や条件が曖昧な表現も注意が必要です。宅建業法や不動産公正競争規約などに基づき、正確かつ適切な広告表現を徹底しましょう。
チラシとネット広告では作り方に違いはある?
チラシは短時間で視覚的に魅力を伝えられる構成が求められ、物件写真・価格・立地を大きく掲載するのが効果的です。一方でネット広告は検索対策や詳細情報、UI設計が重要で、クリック後の導線や情報の網羅性が集客に直結します。
不動産広告の掲載タイミングはいつがベスト?
物件情報の更新や新規掲載は、ユーザーの閲覧が集中する金曜夜〜土日に合わせるのが効果的です。また、1〜3月・9月は引越し需要が高く、広告反響も増加傾向にあります。定期的に条右方を更新し、掲載順位や閲覧率などを維持しましょう。
不動産広告の文章を自動生成AIで作っても大丈夫?
AIで文章を生成することは初稿作成に有効ではあるものの、掲載前に人の目で内容や表現の確認が必須です。誇大表現や事実誤認を避けるためにも、ルールを理解した担当者が最終チェックを行うようにしましょう。
不動産広告における法令違反を防ぐ体制づくりは?
法令違反を防ぐには、情報入力時のチェック体制づくりが不可欠です。大前提として、「1人で完結させない」ことが挙げられます。入力者・確認者の二重チェック体制を整えるとともに、社内研修や広告マニュアルの整備を定期的に行えば、法令違反リスクを軽減できるでしょう。