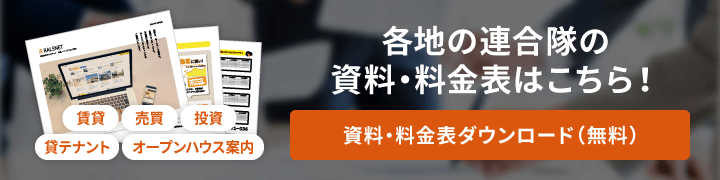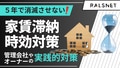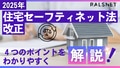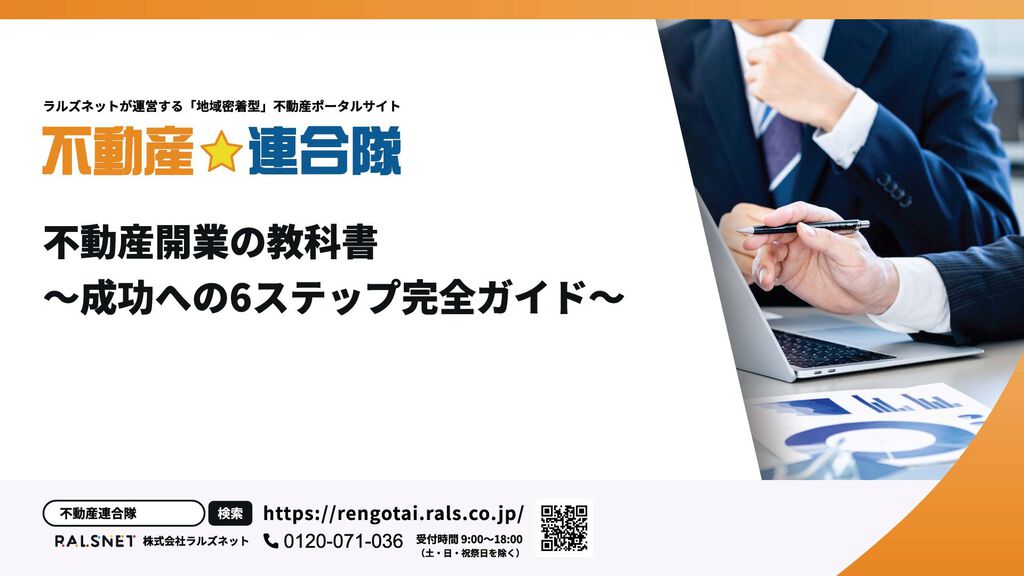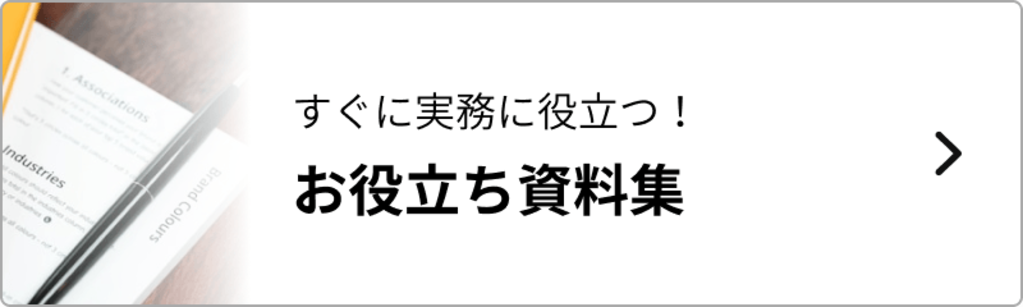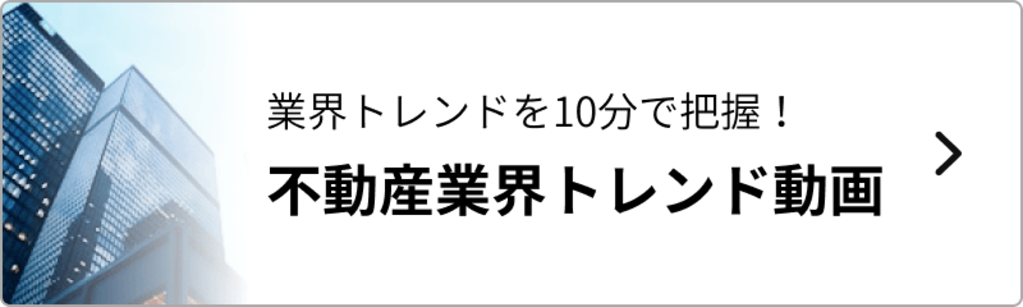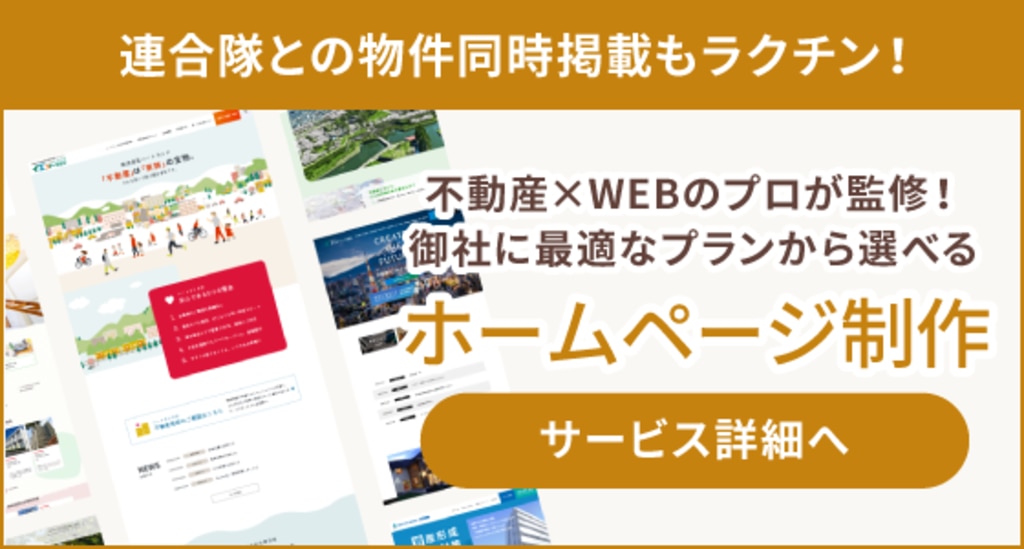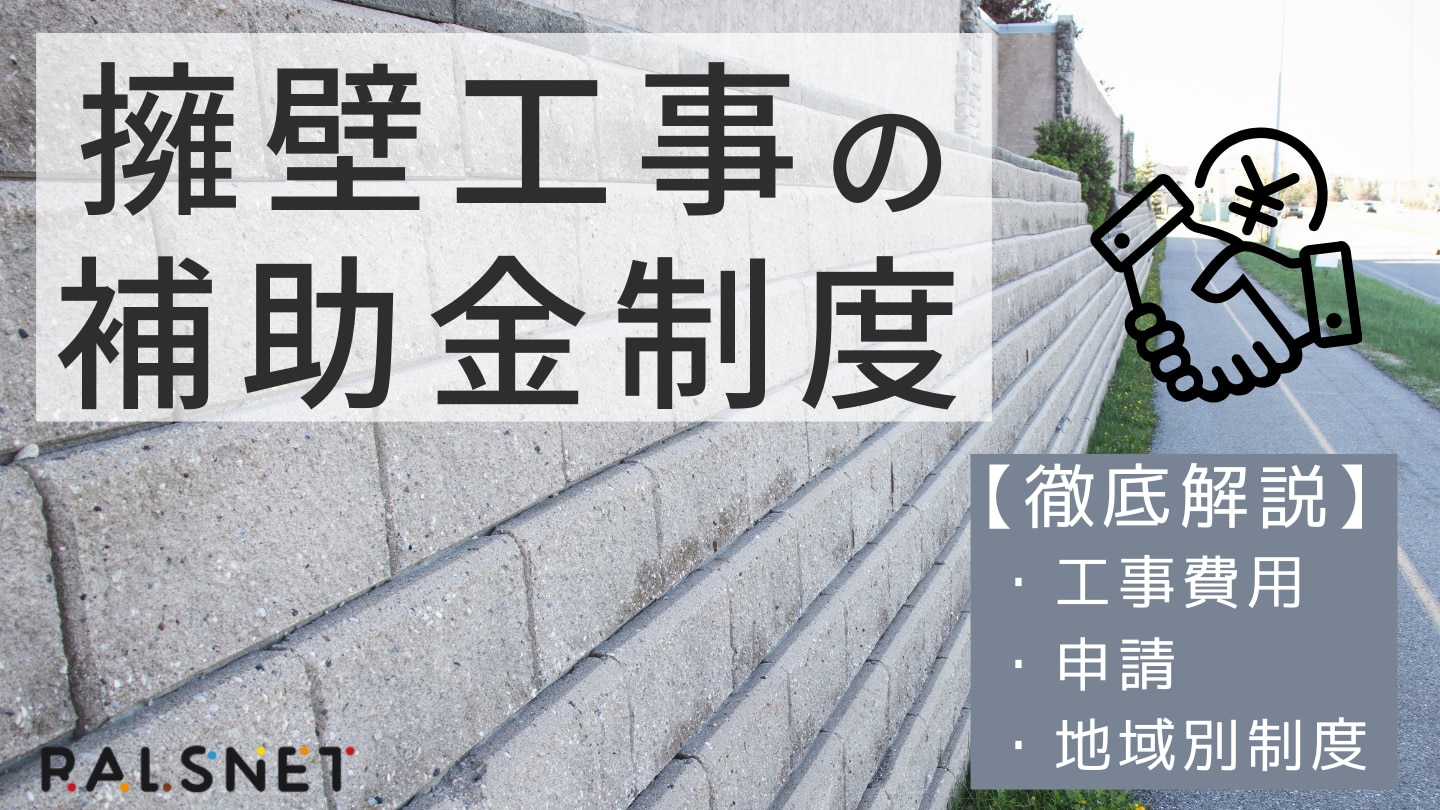
擁壁工事の補助金制度|工事費用・申請・地域別制度まで徹底解説!
「擁壁の補修って、補助金でカバーできないの?」
このように思ったことはありませんか?
老朽化した擁壁の修繕や建て替えは数百万円規模になることも多く、できれば自治体の制度を使って負担を減らしたいと考える方は少なくありません。
実は、一定の条件を満たせば擁壁工事に補助金を使える自治体が多数ありますが、工事前の申請や対象工事の範囲など、見落としやすいポイントもあります。
本記事を読めば、補助金を有効活用でき、擁壁の安全対策を安心して進められるでしょう。
目次[非表示]
- 1.擁壁工事に補助金は使える?まず知っておきたい基本と注意点
- 2.擁壁工事の補助金はいくらもらえる?費用と助成額の相場感
- 3.擁壁工事の補助金がある地域は?全国制度と地域制度まとめ
- 3.1.国の制度「がけ地近接等危険住宅移転事業」とは
- 3.2.東京都・神奈川県など都市部の支援制度
- 3.3.北海道・九州など地方都市での補助金事例
- 3.4.地域の擁壁補助金制度はどう調べる?検索のコツと注意点
- 4.擁壁工事の補助金申請はいつ・どうやる?手続きの流れと必要書類
- 5.擁壁工事の補助金をうまく活用するコツ
- 6.擁壁工事の補助金を使った事例を紹介
- 7.擁壁工事の補助金の見落としがちなポイント
- 8.擁壁工事の補助金を賢く使って、安全な暮らしを守ろう
- 9.よくある質問
擁壁工事に補助金は使える?まず知っておきたい基本と注意点

条件を満たせば、擁壁工事に使える補助制度がある自治体も多く存在します。ただし、どのような擁壁でも対象になるわけではなく、事前申請が必要な点にも注意が必要です。
まずは、補助制度を活用するための基本をしっかり確認しておきましょう。
擁壁とは?崩落リスクと法的な位置づけ
擁壁とは、土砂の崩壊を防ぐために、斜面や高低差のある敷地の境に設けられる構造物です。とくに高さがある場合は、地震や集中豪雨で崩落するリスクが高く、重大な事故につながるおそれもあります。
建築基準法では、高さが2メートルを超える擁壁について構造や材質に関する技術基準が定められており、安全性を確保することが義務づけられています。もし古い擁壁が基準を満たしていない場合は、再建や補強が必要になるケースも少なくありません。
補助金が出る擁壁と出ない擁壁の違い
補助対象かどうかは、高さ・位置・危険度・公共性など複数の要素で決まります。代表的な基準は次のとおりです。
高さ2m超 かつ 道路や通学路に面し、通行者に危険が及ぶおそれがある
土砂災害警戒区域・急傾斜地 に指定されている
老朽化・傾き・ひび割れなど安全性に問題がある
反対に、私道や人目につかない位置で第三者被害が想定しにくい擁壁は対象外となるケースが多いので注意しましょう。
「補修だけ」では対象外のケースに注意
注意したいのが、「補修工事」は補助の対象外となる自治体が多いことです。たとえば東京都世田谷区では、ひび割れを埋める、表面をきれいにするだけの軽微な工事について「補助金は出ない」と明記されています。
一方で、福岡市「宅地防災対策助成金」では、補修工事でも上限100万円・助成率⅓が設定されています。
補助の対象になるのは、擁壁全体を建て替える、鉄筋コンクリートで補強するといった抜本的な安全対策に限られることが一般的です。「せっかく工事をしても対象外だった…」という事態を避けるためには、着工前に自治体へ相談し、制度の条件に合うか確認しておくことが大切です。
擁壁工事の補助金はいくらもらえる?費用と助成額の相場感

擁壁工事は高額になりやすいため、補助額によっては家計への影響も大きく変わります。
ここでは、自治体ごとの助成率や上限金額、工事費用の目安、補助を受けた場合の実質負担についてわかりやすく整理します。
自治体ごとの助成率と上限額の違い
擁壁工事に対する補助制度は、自治体ごとに助成率や上限額が異なります。たとえば、東京都世田谷区では工事費の3分の1(上限300万円)です。
しかし、福岡市では同じく3分の1の助成で、上限額は新設・補強が300万円、補修が100万円と細かく分かれています。
静岡市では工事費の2分の1まで(上限500万円)と、より手厚い補助制度が用意されています。このように、自治体の予算規模や地形的な事情、安全対策への重点度合いによって支援内容に差があるのが現状です。
とくに、崖地や高低差のある宅地が多いエリアでは、より高い補助率や上限が設定されている傾向があります。
擁壁工事の費用相場はどのくらい?
擁壁の新設工事は、1㎡あたり約3万〜5万円が相場です。たとえば高さ2m・延長幅10mの擁壁はおおよそ20㎡の施工面積となるため、60万〜100万円程度が施工費の目安です。ただし、現地の状況や重機の使用可否、地盤の状態などによって費用が上下します。そのため、必ず見積もりを取り、現場に合った金額を把握しましょう。
とくに高さが5メートルを超えるような大型の擁壁では、1,000万円以上になるケースも珍しくありません。
補助金を加味した費用感をシミュレーション
仮に工事費用が300万円かかる場合、世田谷区や福岡市の制度を活用すると100万円の補助を受けられ、自己負担は約200万円です。静岡市のように1/2の補助がある場合は、150万円の自己負担で済む計算になります。
このように、補助制度を利用することで負担を大きく減らせますが、補助対象の上限額を超えた分は全額自己負担になる点にも注意が必要です。
また、多くの自治体では補助金は「交付決定後に着工 → 工事完了後に実績報告 → 補助金振込」という後払い形式を採用しています。そのため、一時的に全額自己資金を用意する必要があります。
擁壁工事の補助金がある地域は?全国制度と地域制度まとめ

擁壁工事に関する補助制度は、国の枠組みに加え、都道府県や市区町村ごとに独自の支援制度が整備されている場合があります。
ここでは、全国的に使える制度と、実際に地域で活用されている具体例をご紹介します。
国の制度「がけ地近接等危険住宅移転事業」とは
国が全国の市区町村向けに交付している制度として、「がけ地近接等危険住宅移転事業」があります。がけ地近接等危険住宅移転事業は、崖崩れや土砂災害のリスクが高いエリアに建つ住宅を安全な場所へ移転するために、自治体に交付金を出す仕組みです。
ただし、この制度は直接「擁壁の改修そのもの」を補助するものではなく、原則として危険地からの移転が目的です。擁壁単体の改修に使えるケースは少ないものの、関連事業として整備される場合もあるため、自治体によっては部分的に補助へ転用されていることもあります。
東京都・神奈川県など都市部の支援制度
都市部では住宅が密集し、擁壁の安全性が周辺の住民に与える影響も大きいため、独自の補助制度が設けられている自治体が多くあります。ここでは、東京都・神奈川県の代表的な補助制度を一覧でまとめました。
北海道・九州など地方都市での補助金事例
都市部だけでなく、崖地や高低差のある宅地を多く抱える地方都市でも、老朽化した擁壁に対する補助制度が整備されています。以下は、実際に補助金制度が確認できた北海道・九州の事例です。
地域の擁壁補助金制度はどう調べる?検索のコツと注意点
「自分の地域に制度があるか調べたい」と思ったら、まずは市役所や区役所の都市整備課や建築指導課のウェブサイトを確認してみましょう。「擁壁」「補助金」「助成」「安全対策」などのキーワードで検索するのが効果的です。
検索時は、「擁壁」ではなく「老朽擁壁」「崖地」「崖条例」など、行政が使う専門用語を含めると制度にたどり着きやすくなります。また、年度ごとに制度の見直しや予算終了があるため、最新年度の情報かどうかにも注意しましょう。
擁壁工事の補助金申請はいつ・どうやる?手続きの流れと必要書類

擁壁工事の補助金制度は手続きや書類に不慣れだと戸惑いやすく、申請のタイミングを間違えると対象外になることもあります。
ここでは、申請から補助金の振込までの基本的な流れと注意点を解説します。
申請に必要な書類と提出方法
必要な書類は自治体ごとに異なりますが、おおむね以下のようなものが求められます。
工事前の擁壁の現況がわかる写真や図面
工事の設計図・仕様書・見積書
土地・建物の登記事項証明書
申請者の住民票や印鑑証明など本人確認書類
施工業者との契約書(予定を含む)
提出は窓口持参のほか、郵送や電子申請に対応している自治体も増えています。書類に不備があると審査に時間がかかるため、不明点は事前相談で確認しながら進めましょう。
「着工前申請」が必須な理由と失敗例
補助金制度の多くは「事前申請が原則」です。つまり、工事を始める前に申請して許可を得ておかないと、いかに条件を満たしていても補助が出ないというケースがほとんどです。
たとえば、横浜市や福岡市、川崎市などでは「着工後に申請した場合は対象外」と明記されています。過去には「急いで工事を始めたら後から補助があると知ったが申請できなかった」という例もあるため、工事業者と相談する前に、まず自治体に確認することが大切です。
交付決定から完了報告・補助金振込までの流れ
申請が受理されると、自治体での審査を経て「交付決定通知書」が送られてきます。これを受け取ってから工事を着工することになります。ここで重要なのは、交付決定が下りる前に着工してしまうと補助金対象外になる点です。
工事完了後は「完了報告書」と「支出証拠(領収書など)」を提出します。その後、現地調査や確認を経て補助金が指定口座に振り込まれるという流れになります。振込までの所要期間は明記がない自治体が多いため、数週間〜数か月の幅で見込み、具体的な時期は窓口で確認しましょう。
擁壁工事の補助金をうまく活用するコツ

擁壁工事の補助金は金額が大きい分、申請のタイミングや内容で結果が大きく変わる制度です。「せっかく制度があるのに活用できなかった」と後悔しないためには、申請前からしっかりと準備しておくことがポイントになります。
ここでは、補助金を賢く活用するための実践的なコツをご紹介します。
予算枠に注意!早めの申請が重要
多くの自治体では、年度ごとの予算枠に限りがあります。つまり、条件を満たしていても予算が埋まってしまえば受付終了になる場合があるのです。
とくに3月末で締める自治体が多いため、4〜6月の申請開始直後が申請の狙い目です。「まだ今年は余裕があるはず」と油断していると間に合わないこともあるため、早めの情報収集と申請準備を心がけましょう。
事前相談と行政書士・業者との連携がカギ
申請書類は専門的な図面や見積書なども含まれるため、工事業者との連携が欠かせません。また、自治体によっては行政書士や建築士による書類作成が必要になることもあるため、最初からプロと協力体制を組んでおくのが安心です。
自治体の窓口では「事前相談」を受け付けている場合がほとんどなので、まずは制度の対象になるかどうか確認しながら、準備すべき書類や進め方のアドバイスをもらっておくとスムーズです。
費用を抑える施工・申請上の工夫とは
擁壁工事の補助対象になる工事内容の範囲を確認したうえで、余計なコストをかけずに必要最小限の工事にとどめることも、費用を抑える工夫のひとつです。
また、自治体によっては「再利用できる資材の活用」や「指定業者による施工」で加点や審査優遇がある場合もあります。申請時に有利になるよう、制度の細かい要件も事前にチェックしておくことをおすすめします。
擁壁工事の補助金を使った事例を紹介

制度の概要や申請の流れを知っても、実際にどのような人がどのように補助金を活用しているのかがわからないと、なかなかイメージが湧きにくいかもしれません。
ここでは、実際に擁壁工事に補助金を活用した3つの地域の事例をご紹介します。自治体ごとに条件や支援内容が異なるため、ご自身の地域と照らし合わせながら参考にしてみてください。
老朽擁壁の建て替えで上限300万円:東京都世田谷区
世田谷区は、公道に面し高さが2メートルを超える危険な擁壁を造り替える工事に対して、工事費の1/3・上限300万円を助成します。
補強・補修だけは対象外なので、倒壊リスクが高い古い擁壁は新しい基準に合わせてつくり直すのが基本です。たとえば、工事費が900万円なら補助300万円、600万円なら補助200万円が目安です。
手続きは事前協議→交付申請→交付決定→契約・着工→完了報告→額確定→請求→振込の順で進みます。世田谷区のチラシと手順図に、対象要件とフローがわかりやすく示されています。
参照|世田谷区:擁壁改修等補助金
豪雨後の安全確保を後押し:福岡市の新制度
福岡市は2025年6月1日開始の「宅地防災対策助成金」で、擁壁の築造・補強・補修を支援します。助成は工事費の1/3で、築造・補強は上限300万円、補修は上限100万円です。
たとえば、豪雨で変状が出た擁壁を補強し工事費450万円の場合、補助金150万円(1/3)を受け取れるイメージです。交付決定前の契約・着手は不可、市内事業所の施工といった条件や、完了報告の期限(2月末または完了後15日以内の早い方)も明記されています。
申請の流れと様式は市の案内ページから確認できます。
参照|福岡市:宅地防災対策助成金について
最大400万円まで上乗せ可能:横浜市の崖地【防災】対策
横浜市の「崖地【防災】対策工事助成」は、建築基準法等の手続きが必要な擁壁工事などを対象に、工事費の1/3・上限400万円まで助成します。
算定は1/3と工法別単価×面積、そして上限400万円のうち最も小さい額で決ます。たとえば工事費1,200万円なら上限400万円、900万円なら補助300万円が目安です。
交付決定前の契約・着工は不可、市内に本社のある事業者との契約が要件で、郵送申請にも対応しています。年度の完了報告期限(2月末)や受付期間も毎年度告知されるので、早めの準備が安心です。
擁壁工事の補助金の見落としがちなポイント

補助金の制度を調べて申請までたどり着いても、「そんな条件があったの?」と後から気づくことは少なくありません。とくに擁壁工事の場合は、制度の対象や申請者の資格、工事後の扱いにおいて見落としやすいポイントがいくつかあります。
トラブルを避けるためにも、事前に知っておきたい注意点をご紹介します。
補助対象は所有者に限られる場合がある
多くの補助制度では、申請者が擁壁を所有している本人またはその相続人であることが求められます。たとえば、借家人や隣地の住人など、所有権がない人は原則申請できません。もし共有名義になっている場合は、すべての共有者の同意書が必要になることもあります。
とくに古い擁壁では、所有者が不明確なケースもあるため、登記簿や境界図を確認し、誰が申請権を持っているのかを早めに整理しておくことが大切です。
施工業者や地域要件でNGになるケース
補助制度の中には、「自治体が指定した登録業者を使うこと」や「地域内に本社を持つ業者に限る」といった要件が設けられていることがあります。知り合いの業者に依頼したくても対象外になる場合があるため注意が必要です。
また、施工業者が作成する図面や見積書の内容が制度の基準に合っていないと、書類が差し戻されることもあるため、経験豊富な業者を選ぶこともポイントです。
補助後の「転売制限」など制度独自の条件
補助金を受けた物件には、一定期間の転売制限や用途制限が課されることがあります。たとえば「5年間は売却不可」「住宅以外の用途に変更不可」といった条件がつくケースです。
これを知らずに将来的に売却しようとした際に、行政から返還を求められる可能性があるため、制度要項の細かい部分までしっかり確認することが大切です。
不動産会社に相談する場合も、補助制度が絡む物件だと伝えることでスムーズに話が進むでしょう。
擁壁工事の補助金を賢く使って、安全な暮らしを守ろう

今回は、擁壁工事に関する補助金制度の概要や、地域ごとの違い、申請手続きのポイントについて解説しました。
補助金を使えば高額になりがちな擁壁工事の費用負担を大きく抑えられますが、制度を活用するには「着工前の申請」が必須であることを忘れてはなりません。
とくに擁壁の高さや位置、危険性の有無などによって補助対象が細かく分かれるため、まずはご自身の地域に制度があるかどうかを調べ、自治体へ事前相談することが重要です。
よくある質問
擁壁の一部補修だけでも補助金は出る?
一部の自治体では「補修」も補助対象になる場合がありますが、原則として老朽化による撤去・再築や安全確保を目的とした工事が対象です。ひび割れ補修など軽微な工事だけでは対象外となるケースもあるため、事前相談で確認するのが安心です。
補助金って申請すれば必ずもらえるの?
条件を満たしていても、予算の上限に達していたり、申請書類に不備があると却下される可能性もあります。また、申請前に工事を始めてしまった場合は対象外になることが多いため、「交付決定後に着工」が基本と考えてください。
所有者じゃなくても擁壁工事の補助金申請できる?
多くの補助制度では、申請者が擁壁の所有者であることが求められます。借地人や隣接者の場合は対象にならないため、登記情報などを確認して、申請資格を明確にしておきましょう。共有名義の場合は、全員の同意が必要になることもあります。
工事後にさかのぼって擁壁工事の補助金申請できる?
基本的には事前申請が必須で、工事後にさかのぼって補助を申請することはできません。万が一、事前相談や申請をせずに工事を進めてしまった場合は、補助の対象から外れてしまうことになります。必ず工事前に自治体へ確認しましょう。