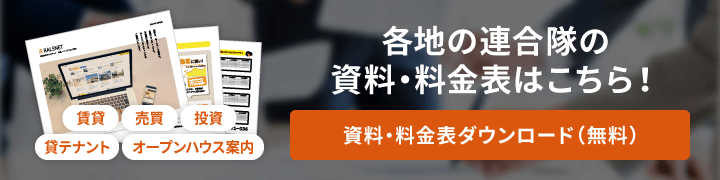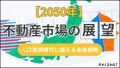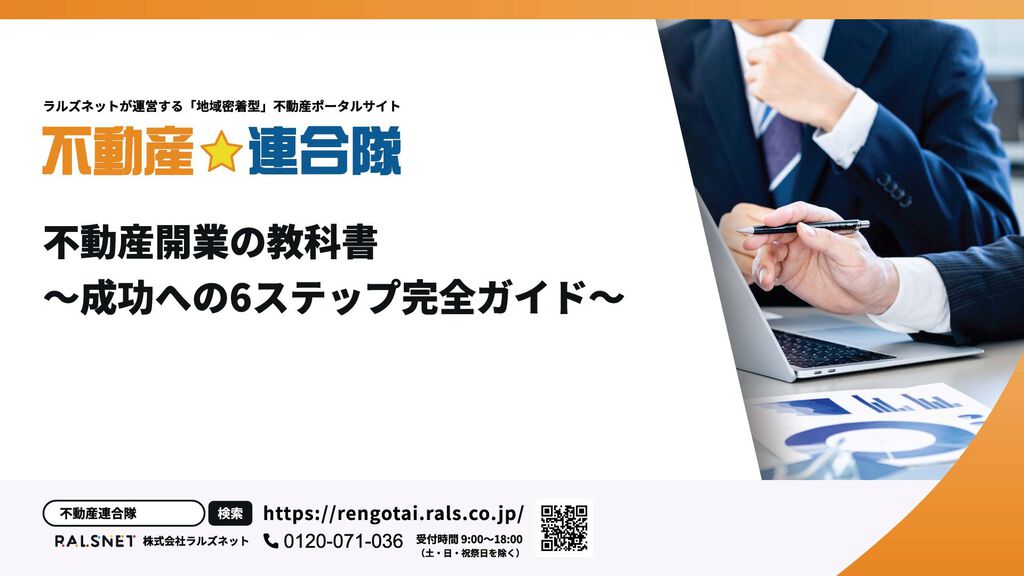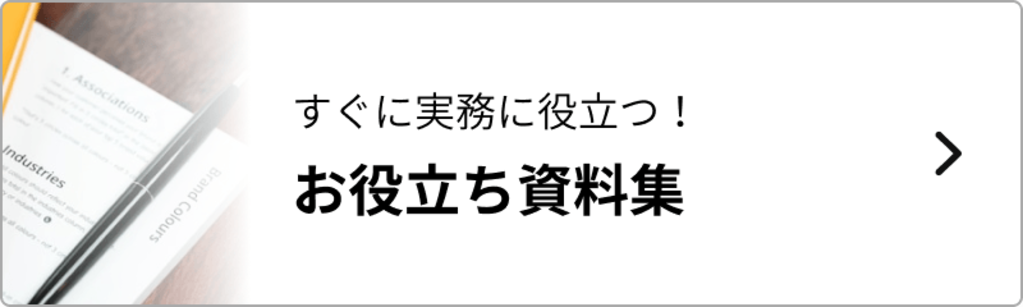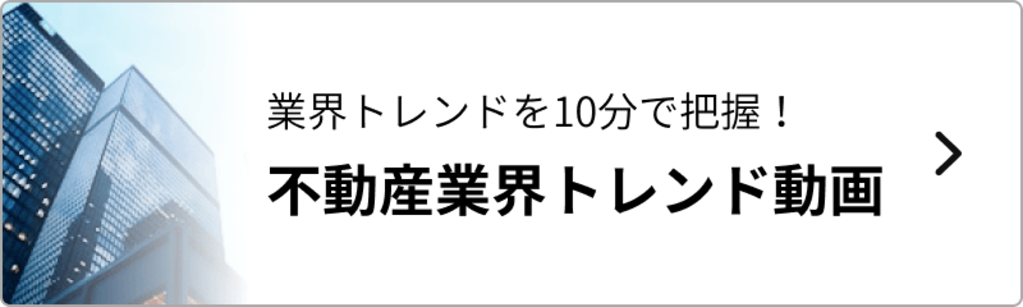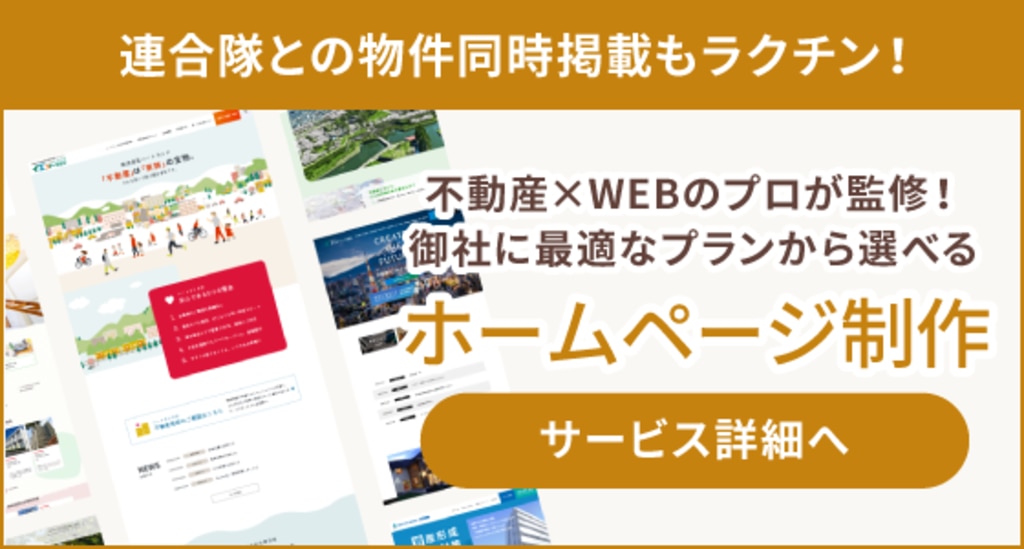2025年住宅セーフティネット法の改正|4つのポイントをわかりやすく解説!
「高齢者が入居希望なんだけど、滞納や孤独死が心配で…」
そのような声をオーナーや現場スタッフから耳にすることは少なくありません。
実は、2025年10月に改正される住宅セーフティネット法は、こうした不安を制度でカバーする仕組みです。終身賃貸の導入支援や残置物の明確な処理ルール、保証制度の新設など、不動産実務に直結する変更点が数多く盛り込まれています。
本記事では、2025年の住宅セーフティネット法改正のポイントをわかりやすく解説するとともに、不動産実務にどう活かすべきかを解説します。
本記事を読めば、住宅セーフティネット法の改正の要点を把握し、不安を安心に変える対応力を高められるでしょう。
目次[非表示]
住宅セーフティネット法とは?

住宅セーフティネット法は、民間賃貸住宅を活用して、住まいの選択肢を広げるための制度です。住宅情報の「見える化」と支援体制の整備を組み合わせることで、入居のハードルを下げる仕組みとなっています。
ここでは、制度の目的や対象、仕組み、公営住宅との違いなど基本的なポイントをわかりやすく整理します。
法律の目的は「要配慮者への住まいの確保」
住宅セーフティネット法の目的は、住宅確保要配慮者が円滑に住まいを見つけ、安心して入居できる環境を整えることです。
背景には、以下のような社会的変化があります。
単身高齢者の増加
持ち家率の低下
一方で、大家(賃貸人)側には、次のような懸念が根強くあります。
孤独死や死亡時の残置物の処理
家賃滞納のリスク
高齢者への見守り対応の負担
住宅セーフティネット法は、こうしたギャップを埋めるために、登録制度や支援の枠組みを整え、入居に対する不安を小さくすることを目指しています。
対象となる住宅確保要配慮者とは?
住宅セーフティネット法の支援対象は、以下のような方々です。
低額所得者
被災者
高齢者
障害者
子育て世帯
また、省令により外国人も対象に含まれます。さらに、自治体の判断で対象を追加することもでき、たとえば「新婚世帯」を加えている地域もあります。
現場対応では、申込み前に該当する区分を確認し、必要書類の案内を早めに行うことで、スムーズな入居支援につながるでしょう。
セーフティネット住宅と公営住宅の違い
セーフティネット住宅と公営住宅は、混同されやすいですが、役割と仕組みが異なります。以下の表で比較・整理しましょう。
セーフティネット住宅は、「入居を拒まない」民間賃貸を登録して利用する仕組みです。一方、公営住宅は自治体が建設・管理を行う住宅で、選定や入居条件も異なります。両者を組み合わせることで、地域全体の住まいの選択肢が広がります。
制度の仕組みは「登録住宅+支援体制」
実務の流れはシンプルで、登録→公開→申込み→支援連携の順で進みます。
賃貸人が物件を登録し、自治体が受理
情報は「セーフティネット住宅情報提供システム」で一般公開
入居希望者が物件を探して申込み
必要に応じて、居住支援法人が相談・見守りを担当
自治体は供給促進計画や協議会を通じて地域連携を強化
とくに実務上は、支援窓口と早めに連絡体制を整えておくと、入居後のトラブルを予防できます。
住宅セーフティネット法の改正(2025年)の4つのポイント

2025年の住宅セーフティネット法改正では、「住まいの不安を感じやすい場面」を先回りで防ぎ、入居と管理の両面で安心できる環境を整えることが目的です。施行は2025年10月1日ですが、関連する認定や規程整備は同年7月1日から始まります。
ここでは、現場対応に直結する4つの改正ポイントをわかりやすくご紹介します。
終身建物賃貸借の認可が簡素化される
終身建物賃貸借は、入居者が生きている限り契約が続き、亡くなった時点で契約が終了する仕組みです。
従来は「住宅単位」で認可を受ける必要があり、手間がかかるため活用が進みにくい面がありました。改正により「事業者単位」での認可へと簡素化され、導入のハードルがぐっと下がります。
複数物件での一括運用が可能
標準契約書やガイドラインが整備され、実務もスムーズに
たとえば、高齢者向けの一棟賃貸や、特定フロアへの集中導入など、提案しやすい選択肢が増えるでしょう。
残置物処理のモデル契約が実装レベルまで進む
これまで「誰がどう対応するか」が曖昧だった残置物の処理が、制度として正式に位置づけられます。
住宅セーフティネット法改正後は、居住支援法人の業務に「残置物処理等」が明記され、モデル契約条項も整備されます。これにより、対応方法や費用の扱いを事前に整理しやすくなるでしょう。
死後事務委任の範囲や手順を業務規程で明文化
支援法人と連携することで、鍵の開錠・立ち会い・費用精算の負担を軽減
たとえば、申込み時に同意書と支援法人の連絡体制をセットで提示しておくと、退去時の混乱を防ぐ効果が期待できます。
家賃滞納に備える「家賃債務保証制度」も新設
家賃保証の選択肢として、国土交通大臣が認定する公的な家賃債務保証制度がスタートします。とくに住宅確保要配慮者の入居において、民間保証では対応しにくい場面を支える制度です。
2025年7月1日から申請受付、10月以降に認定がスタート
原則として連帯保証人を求めない設計
保証料の妥当性や内部規程、体制が審査される
現場では、募集図面や案内資料に「家賃債務保証制度の優先利用可」を記載しておくことで、与信面の不安を和らげ、入居相談がスムーズに進みます。
「居住サポート住宅」の仕組みが新たに加わる
「居住サポート住宅」とは、居住支援法人がオーナーと連携し、安否確認や見守り、福祉との橋渡しまで行う住宅です。自治体が所定の基準に基づき認定を行います。基準の一例は、以下のとおりです。
規模:原則25㎡(既存物件は18㎡、共用部を活用すれば13㎡も可)
安否確認:1日1回以上
見守り:月1回以上
必要に応じて、地域の福祉と連携
家賃:近隣の相場と均衡する範囲
この制度は、とくに単身高齢者の受け入れを検討している物件に有効です。たとえば、ワンルームを改修して見守りを導入するだけでも、制度の認定対象となる場合があります。
セーフティネット住宅の補助金はある?

セーフティネット住宅として登録することを前提に、改修費の補助や家賃を低くおさえるための補助金が用意されています。とくに空き家の活用や既存住宅の改修を検討している場合、補助金制度を組み合わせることで入居しやすい物件づくりが可能になります。
なお、補助制度の内容や上乗せ条件は自治体によって異なるため、早めのスケジュール確認が重要です。
改修費補助|バリアフリー・耐震改修などの対象
セーフティネット住宅に登録予定の物件について、必要な改修に対する補助金が交付されます。たとえば、以下のような工事が対象になります。
段差の解消や手すり設置などのバリアフリー対応
耐震補強や省エネ設備の導入
間取り変更や見守りセンサーの整備
2025年度は4月2日〜12月12日の公募期間が予定されており、事前審査を早めに進める必要があります。たとえば「段差解消+見守りセンサー」のように複数の改修を一括で計画し、登録申請と同時に補助申請を出す流れが一般的です。
補助率や上限額は国の要領と自治体要綱で確認することが大切です。
家賃低廉化補助|減額分を国や自治体が補填
家賃の一部を減額する「家賃低廉化支援」も制度化されています。これは登録された住宅の家賃や保証料の一部を、国や自治体が公的に補填する仕組みです。
市場家賃と実際の家賃の差額を公費で補填
家賃債務保証料の補助も含む
運用の流れとしては、自治体の募集に応じて申請を行い、交付決定後に入居者を迎え、最終的に実績報告を提出します。現場では、募集図面に「低廉化前後の家賃」を明記しておくと説明がスムーズです。
自治体の上乗せ制度もチェック
国の補助に加え、自治体によっては独自の支援を上乗せしているケースがあります。とくに大都市圏では名称や内容が地域特有になっているため、事前に確認しておくと無駄がありません。
申請前には、各都道府県や政令市のホームページで「上乗せの有無・名称・締切」を確認してから、国の募集要領に進むのが効率的です。
申請の流れとスケジュールの確認
補助金申請の流れは「登録」と「補助」の2本立てで考えると、全体が把握しやすくなります。
物件の登録または登録準備
用途・面積・設備を整理し、登録条件に沿った整備を行います。改修費補助の申請
事前審査→交付申請→工事→実績報告という順番です。家賃低廉化の申請
区分や金額を整理し、自治体の様式に沿って申請を進めます。- 自治体上乗せの確認
名称・条件・申請期間などを調べ、社内説明資料やオーナー向け提案に活用します。
契約書や同意書の整備、支援法人との連携体制の構築など実践的な視点で、制度改正への備えを一緒に進めていきましょう。
不動産会社がやるべき実務7つ|オーナー対応の備え方も解説

2025年10月1日に施行される制度改正に向けて、早期に段取りを整えておくことで、現場での対応がスムーズになります。
ここでは、以下の不動産会社が現場で取り組むべき7つの実務を解説します。
それでは、詳しく見ていきましょう。
終身賃貸契約書の見直し
「終身建物賃貸借」を扱う場合は、社内で使用している契約書の見直しが必要です。残置物条項の有無や死亡時の契約終了、相続、原状回復の扱いまで、一連の流れを「ひとつの物語」として通しておくことで、現場対応に迷いがなくなります。
単身高齢者の入居が多い物件では、終身契約と定期借家契約の説明を統一した雛形を準備すると、スタッフが混乱せずに案内できます。社内研修では、見落とされやすい文言を抜き出し、短時間の読み合わせで共有するのがおすすめです。
残置物条項の同意書の準備
入居時点で、残置物の扱いについての合意形成が欠かせません。入居者、受任者、賃貸人それぞれの役割分担をわかりやすい言葉で整理し、「誰が」「どう対応するのか」「費用負担はどうするのか」などの点を明文化します。
居住支援法人が関与する地域では、支援業務規程と整合の取れた内容にしておくと、現場対応がスムーズです。来店者には「安心して借りられる仕組みが用意されています」と伝えることで、不安を和らげる効果もあります。
認定家賃債務保証業者の導入検討
高齢者や生活保護受給者など、審査に課題が生じやすい入居希望者に対しては、認定家賃債務保証業者の導入を検討します。連帯保証人を不要とする方向性を軸に、保証内容や相談窓口の充実度、トラブル時の初動対応などを比較検討しましょう。
店舗対応では「連帯保証人は求めず、仕組みで支えます」とシンプルに伝えたうえで、図や資料を用いた説明が効果的です。オーナーへの説明では、保証の範囲と除外を先に示すことで、リスクへの懸念を取り除けます。
居住支援法人との連携ルート整備

単独対応には限界があります。見守りや相談体制の外部連携をあらかじめ構築しておくことで、申込みから入居後のトラブル対応まで一本の流れが生まれます。窓口の担当者名、対応時間、夜間連絡の取り方、緊急時のサインなど具体的に詰めておくことが重要です。
店舗には、紹介カードや法人の名刺をまとめて置いておくと、来店時の案内がスムーズになります。
居住サポート住宅への登録準備
「安否確認」「見守り」「福祉連携」の3点を備えた住宅は、居住サポート住宅として登録が可能です。
登録することで、空室解消の導線としてセーフティネット住宅情報提供システムに掲載され、地域の支援ニーズにも応えられます。
設備や広さは制度に準じて整え、支援の頻度や内容を明確に案内することが求められます。登録に向けた改修費補助と合わせて計画を進めると効果的です。
オーナーへの周知と勉強会
オーナーが不安を抱きやすいのは、滞納・残置物・孤独死といったリスクです。こうした懸念を先回りして共有し、制度の施行時期や書類の整備状況、保証制度の活用までを一連のストーリーで伝えると納得が得られやすくなります。
勉強会では、制度の要点は短く、実際の事例を中心に紹介し、質疑で理解を深める構成が効果的です。配布資料は、すぐに実務に使える様式にしておくと、説明後の動き出しが早くなります。
社内研修・問い合わせ対応の強化
初期対応の質が、入居希望者の安心感を左右します。生活保護・高齢者・外国籍・無職など属性別に必要な書類や案内順を定め、社内で共有しましょう。
検索サイトの使い方、提出書類の見本、連絡先リストなどは、すぐ取り出せる場所に整理します。現場からの疑問やトラブルは週次で集約し、文言のズレや様式の改善に反映し続ける体制が望まれます。
住宅セーフティネット法改正を実務にどう活かす?

住宅セーフティネット法の改正は、大きな投資をせずとも、小さな工夫で現場の動きを変えるチャンスになります。ここでは、不動産会社が今日から取り組める現実的なアクションを4つの観点でご紹介します。
制度対応に向けた情報収集を始める
まず大切なのは、住宅セーフティネット法改正の一次情報を一元化することです。国や自治体の告知、募集要項、申請様式、Q&Aなどを1つの共有フォルダに集めましょう。
おすすめは、「制度概要」「申請手順」「連絡先」の3カテゴリに分けて格納し、古いファイルは「旧版」フォルダへ退避させるシンプルな方法です。
本部と店舗で同じ資料を参照する環境を整えるだけで、案内の表現が統一され、問い合わせ時の行き違いが減少します。
メルマガや社内資料の活用も効果的
忙しい現場には、要点だけを短く届ける情報発信が効果的です。たとえば、毎週同じ曜日に「今週の改正ポイント」「使える様式」「提出期限」などを3行程度にまとめて配信し、詳細は共有フォルダへのリンクで誘導する方法がおすすめです。
また、制度全体の流れや申請の注意点は、外部の業界向けメルマガなどを活用することで、読みやすくタイムリーな情報を得られます。現場の店頭トークにもすぐ転用できる内容が多く、スタッフの即時対応力アップにもつながります。
社内研修や問い合わせ対応体制の整備
制度対応における信頼感は、店頭や電話の最初の数分で決まります。一次回答を3分で返す体制を目指し、想定問答と必要書類の順番を「短冊形式」の資料にして整理しておきましょう。
「高齢者」「生活保護」「外国籍」「無職」などの属性ごとに確認ポイントを一枚にまとめておくと、誰が対応しても説明のズレがなくなります。
さらに、内見時には現地で見守り体制や連絡手順を説明する場面を設け、文書・案内・実物の言葉を一致させることで誤解を防げます。
営業現場の声をフィードバックとして集約する
制度対応は一度整えて終わりではありません。改善のポイントは「情報の流れを止めないこと」です。
おすすめは、週1回15分の短い定例ミーティングを設け、現場でつまずいた表現や、質問が多かったトークを記録・共有していく方法です。たとえば、「保証人は必要か?」といったよくある質問への回答を毎週1行ずつ磨き、資料や図解にも反映させます。
成約や問い合わせにつながった具体例は、数字や写真を添えて全社で共有すると、オーナー説明にもそのまま流用でき、再現性のある提案力となって蓄積されていきます。
住宅セーフティネット法改正に対応して提案力を強化しよう

今回は、住宅セーフティネット法の改正ポイント、補助の仕組み、そして現場での実務の進め方について解説しました。
施行日と準備の時期をおさえ、終身賃貸・残置物・認定保証・居住サポート住宅を全体像で整理し、オーナー提案と社内運用の要点をまとめました。とくに、早めの情報整理と書式の統一が成果への近道です。
住宅セーフティネット法の改正でよくある質問
住宅セーフティネット法の条文はどこで読めますか?
法改正の根拠となる条文は、e-Gov法令検索(e-Laws)で確認できます。正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」です。
国土交通省の公式ページでも改正概要や制度のポイントが整理されています。
生活保護利用者の家賃支払いはどうなりますか?
生活保護制度では、家賃は住宅扶助の対象です。入居者本人ではなく、福祉事務所から家主へ直接家賃が支払われる「代理納付制度」を利用することで、家賃滞納のリスクを軽減できます。
共益費の一部も含められる場合があり、対応可否は自治体により異なります。
募集時点で代理納付の運用ルールを確認し、事前に合意が得られるような説明が大切です。
居住サポート住宅の認定基準は厳しいですか?
認定のハードルは、「住宅の基準(面積・設備)」と「支援内容(見守り・安否確認・福祉連携)」の両面で判断されます。省令や実務要領には、面積や構造・支援頻度・連携体制などの要件が一覧表で示されており、様式に沿って準備すれば申請は難しくありません。
保証会社の認定には何が必要ですか?
今回の改正で新設された「認定家賃債務保証業者制度」では、保証会社が一定の基準を満たすことで、国土交通大臣からの認定を受けられるようになります。申請受付は2025年7月1日から、認定の開始は10月以降の予定です。主な要件は、以下の通りです。
連帯保証人の設定を求めない運用
苦情対応や内部規程、約款の整備
保証料の妥当性や情報公開の仕組み
窓口は各地方整備局で、すでにQ&Aが公表されています。制度利用を予定する場合は、早めの問い合わせと準備が望まれます。
残置物処理は誰がどのようにすればよいでしょうか?
入居者が死亡した際の契約解除や残置物の処理は、国土交通省・法務省のモデル契約条項を活用することで、手続きの明確化が図れます。
契約時には、死後事務委任契約や同意書で、あらかじめ支援法人に権限を委任し、残置物の保管・換価・廃棄の流れを明示することが推奨されています。
改正後は、「残置物処理等業務」が支援法人の正式業務に位置づけられるため、業務規程と処理スキームの整備が必要不可欠です。