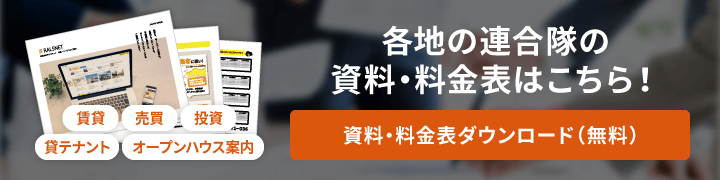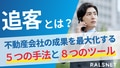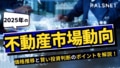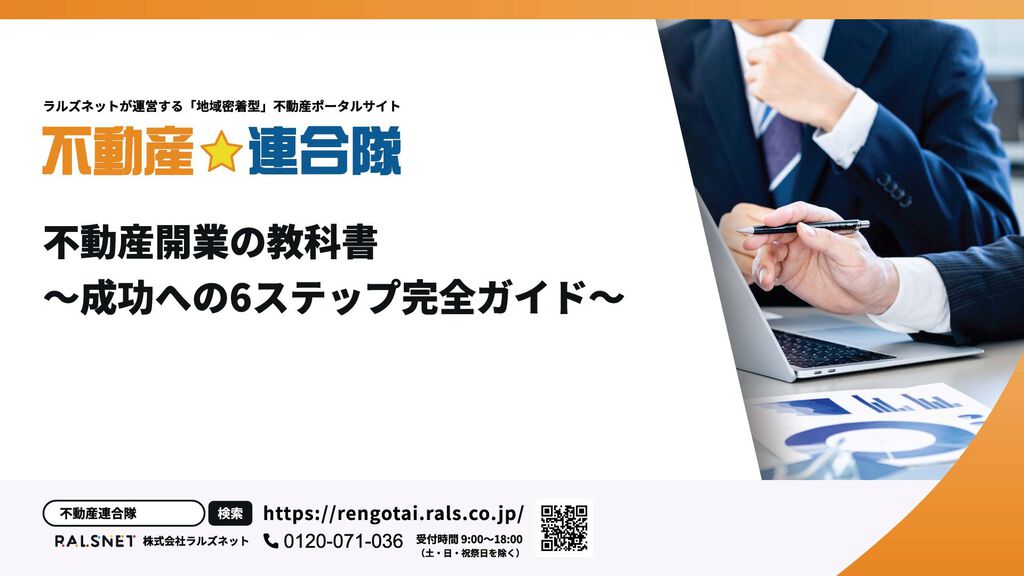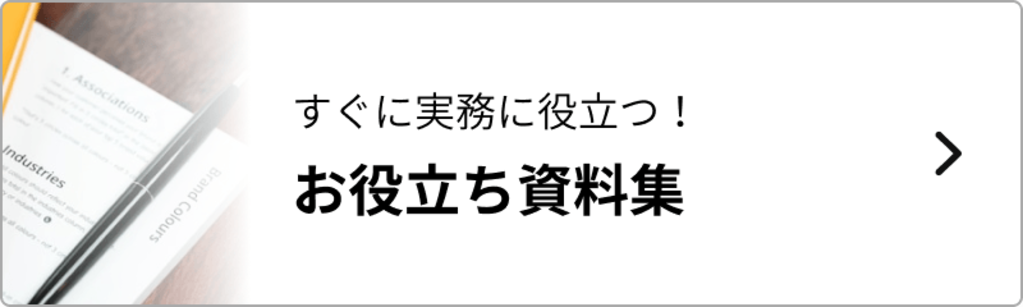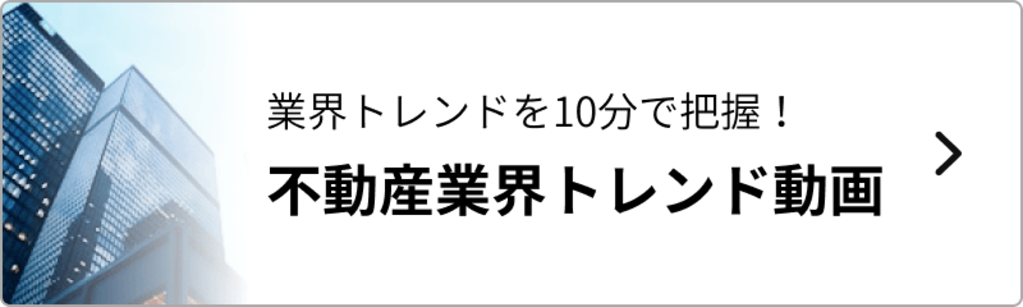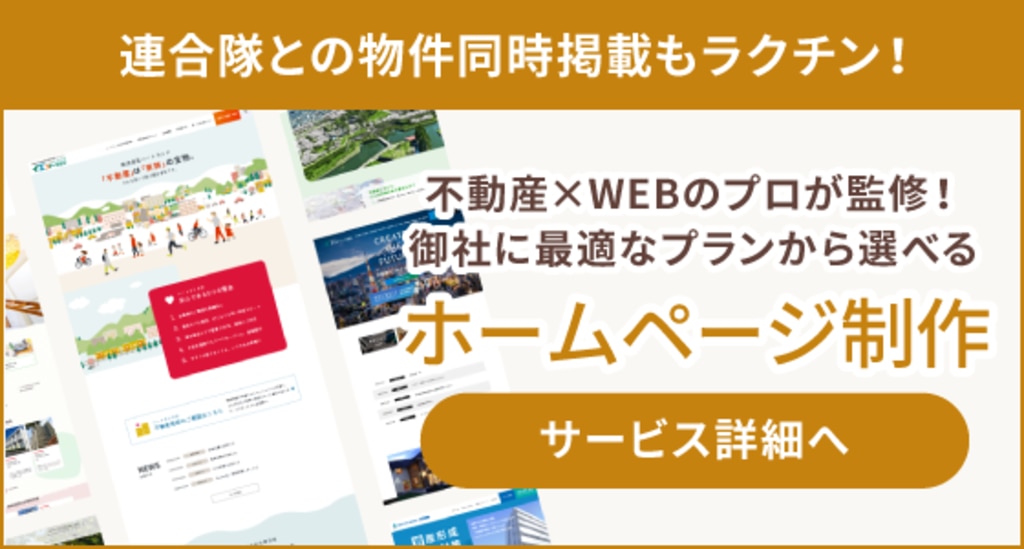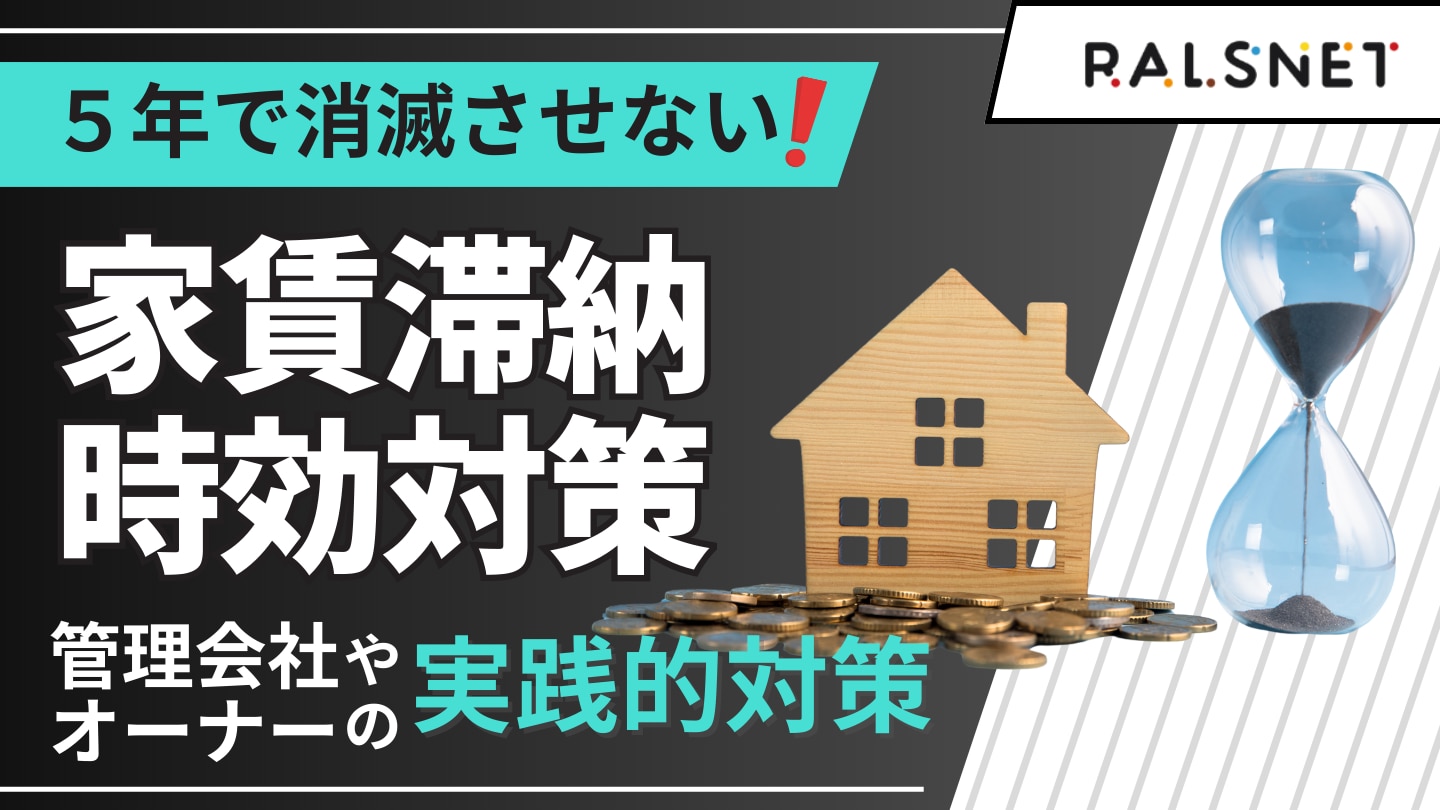
家賃滞納 時効対策|5年で消滅させない!管理会社や貸主の実践的対策
家賃滞納者への対応は、後手に回ると取り返しがつかない事態を招くことがあります。管理会社や貸主であれば、このリスクを肌で感じている方も多いのではないでしょうか。
中でも注意すべきなのが、「家賃滞納 時効」の問題です。 家賃滞納が発生してから何の対応も行わずに5年が経過してしまうと、法律上の「消滅時効」が完成し、請求する権利がなくなってしまう可能性があります。
こうした損失を防ぐためには、家賃滞納分の時効が完成する前に、適切な対応を取ることが不可欠。本コラムでは、滞納家賃の時効が完成する仕組みと、それを防ぐための管理会社や貸主の対応方法について、わかりやすく解説します。
目次[非表示]
家賃滞納の時効は5年で完成する……カウントされるのはいつから?

家賃滞納分は、請求が発生してから5年で時効が完成すると請求できなくなります。はじめに、その根拠となる法律や、時効がカウントされはじめる起算点などの基本情報を確認しましょう。
家賃滞納の消滅時効は5年が原則
民法第166条第1項により、家賃を含む債権は、債権者(今回の場合は貸主)が権利を5年行使しないとき、請求できなくなります。このように、 一定期間が経過すると、法律上その権利を行使できなくなる制度を「消滅時効」といいます。
(債権等の消滅時効) |
「本来、払うのが当たり前の家賃が5年経ったら請求できなくなるなんて…」と、憤りを感じる貸主もいらっしゃるかもしれません。しかし、どうかご安心ください。家賃滞納分は自動的に時効になるわけではありません。
貸主側が時効を完成猶予(旧:停止)・更新(旧:中断)する手続きを取れば、対抗することが可能です。
※2020年4月の民法改正により、かつての「時効の停止・中断」という用語は廃止され、現在は「完成猶予・更新」と表現されています。
家賃滞納分の時効は、支払い日からカウントされる
留意したいのは、家賃滞納分の時効は、滞納月ごとに個別にカウントされる点です。たとえば、家賃の支払い日が2025年8月31日であれば、5年後の2030年8月31日の0時0分になると、消滅時効が完成して請求できなくなります。
長期的な家賃滞納があった場合でも、すべての未払い分が一括で時効になるわけではありません。以下のような取り扱いになることを管理会社や貸主は覚えておきましょう。
・5年経過した家賃滞納分 → 時効完成
・5年経過していない家賃滞納分 → 時効未完成
家賃滞納者が時効を援用する際の流れ

家賃滞納が5年以上になった場合でも、未払い分が自動的に消滅するわけではありません。借主が「これは時効なので支払い義務はありません」と貸主に意思表示してはじめて時効が適用されます。
このように、 権利がある相手に対して、時効を理由に責任を否定する行為を「時効の援用(えんよう)」といいます。次に、借主が時効を援用する流れを見ていきましょう。
管理会社や貸主は、家賃滞納者の時効完成を阻むためにも、援用のポイントを知っておくことが重要です。
援用の手順1:時効の完成を確認する
借主が時効の援用をしたいとき、まず確認すべきことは「本当に時効が完成しているかどうか」です。具体的には、最後の家賃の支払い日から5年以上が経過しているかをチェックします。
ただし、 支払い日から5年以上経っていても、以下のようなことがあった場合、時効は完成猶予や更新されている可能性があります。
・貸主から催告書が届いた
・借主が一部でも家賃を支払った
・借主が家賃を支払う意思を示した など
貸主側から見ると、「時効を更新する手続きをいかに行うか」がポイントになります。
援用の手順2:貸主に通知する(内容証明郵便など)
時効の完成を確認したら、次に借主が行うのは、貸主に対して「時効援用の意思を表示すること」です。この際、利用されることが多い手段が、内容証明郵便です。これは、「いつ・どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出したか」を郵便局が証明してくれる制度。
なお、 借主が貸主に対して「時効の援用を通知する手段」には、郵便以外に、電話や口頭もあります。どの手段を選択しても法的には有効ですが、裁判時などの立証が難しいため、内容証明郵便の利用が一般的です。
援用の手順3:貸主が通知を受け取る
貸主側に「時効援用の通知」が届いた時点で、時効の効力が確定します。時効が確定してしまうと、これを覆すことは難しく、家賃滞納分が支払われることは原則ありません。
管理会社や貸主の中には、「内容証明を受け取らなければ時効が完成しないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、法律上は、 受け取りを拒否しても「意思表示が相手に到達した」とみなされる可能性が高いのです。
家賃滞納者からの「時効の援用」を防ぐ方法

前述のように、家賃滞納の債権があっても、借主が「時効の援用」をするとその債権は消滅します。
そのため、 貸主としては借主に援用を主張される前に、「いかに時効を更新するか」がカギに。以下では、貸主が知っておきたい「時効の援用を防ぐための基本知識や具体的な手段」をわかりやすく解説します。
時効の「完成猶予」と「時効の更新」の違い
基本情報として知っておきたいのが、時効の「完成猶予(旧:停止)」と「更新(旧:中断)」という言葉の違いです。両者は似たような印象の言葉ですが、以下のように法的にはまったく違う意味ですので注意しましょう。
完成猶予(旧:停止) | ・一時的にカウントが止まる |
更新(旧:中断) | ・カウントがリセットされる |
時効の援用を防ぐ方法1:催告
催告は、家賃滞納分の時効を「完成猶予」する方法です。 家賃滞納分の支払いを求める文書には、以下の3つがありますが、時効の完成猶予が目的の場合は、「催告書」を選択してください。
1.催促状 | 家賃滞納分の軽い「注意喚起」を目的とした文書 |
2.督促状 | 催促状よりも強めの「警告」の意味合いで送られる文書 |
3.催告書 | 借主に対して家賃の支払いを法的に要求する文書 |
催告は、口頭や通常の文書でも法的に有効ですが、今後の訴訟などのために証拠を残すという意味では、内容証明郵便の選択がおすすめです。
家賃滞納者に催告をしても、最大6か月の猶予期間を得られただけであり、時効を完全に更新することはできません。管理会社や貸主は、以下に挙げる方法で、時効を更新することが重要です。
時効の援用を防ぐ方法2:債務承認(一部支払い)
借主が家賃滞納分の一部を支払った場合、「債務を認めた」とみなされ、その時点で時効は更新されます。たとえ支払額が 500円や1,000円など少額でも、支払いがあれば時効は更新され、再び5年間のカウントが始まります。
時効の援用を防ぐ方法3:裁判
家賃滞納分について、内容証明を送った後に裁判を起こせば、その時点で時効は更新されます。訴訟手続きが進んでいる間は、時効の進行が完成猶予され、 判決確定すれば債権はそこから10年有効になります。
裁判は手間と費用がかかるため、負担を軽減したい場合は、簡易裁判所で申し立てが可能な「支払督促」も選択肢のひとつです。
家賃滞納の時効と連帯保証人の関係は?

家賃滞納分について、時効が成立してしまっても「連帯保証人に請求すれば大丈夫」と考える貸主の方もいるかもしれません。しかし、 保証人に対する請求も原則として5年で時効となるため、注意が必要です。
保証人の債務は、主債務者(借主)の債務と密接に結びついており、時効の起算点や完成猶予・更新の扱いも基本的には同じです。以下のポイントを押さえておきましょう。
時効の起算点 | ・ポイント:借主が家賃滞納をしはじめた日からカウント ・補足:保証人の責任は、主債務者の債務と同時に発生します。 そのため、時効のカウントも、借主が家賃滞納をした日から始まります。 |
時効の完成猶予や更新 | ・ポイント:保証人にも個別対応が必要 保証人にも内容証明を送るなど、請求や通知を行うことが必要です。 |
家賃滞納者に対しては、粘り強く時効を更新することが重要!

悪質な家賃滞納者に対し、「時効になってしまったのだから仕方ない……」と諦めてしまう貸主の方もいるかもしれません。
しかし、 粘り強く時効の更新を続けることで、債務者の経済状況の回復や意識の変化により、滞納家賃の支払いが実現するケースも一定数あります。
一度でも家賃滞納に対して「時効だから仕方ない」と許容してしまうと、今後同様のケースでも時効の主張を受け入れてしまいやすくなります。だからこそ、管理会社や貸主としては、常に毅然とした態度で対応を続けることが重要なのではないでしょうか。
家賃滞納の時効でよくある質問
保証会社が代わりに支払った家賃滞納分の時効はどうなる?
借主が家賃を滞納した場合、保証会社が代わりに家賃を支払うケースがあります(代位弁済)。このとき、貸主側の家賃債権は保証会社への支払いによって消滅し、貸主が借主に対して直接請求する権利はなくなります。
一方で、保証会社は、借主に対して求償権を取得。貸主に代わり、借主に対して、家賃滞納分を請求できる権利を得ます。この保証会社から借主への求償権にも、5年間の消滅時効が適用されます。この消滅時効の起算点は、「代位弁済があった日」から5年です。
※ただし、営利を目的としない協会や団体が代位弁済をした場合、時効完成までの期間が10年となります(一部例外あり)。
公営住宅(県営住宅・市営住宅)の「家賃滞納の時効」の扱いは?
民法上、家賃など債権の消滅時効は5年とされています(民法第166条)。このルールは、公営住宅(県営住宅・市営住宅など)でも原則として同様に適用されます。
一方、公営住宅は民間に比べて、「対応が甘いのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし実際には、家賃の債権者である都道府県や市区町村は、徴収や時効への対応が厳格です。そのため、公営住宅においては「家賃滞納の時効」が完成する可能性が低いといえるでしょう。
家賃滞納の時効対策に弁護士は必要?
家賃滞納者への対応は、貸主(オーナー)ご自身でもある程度は可能です。たとえば、内容証明郵便による催告でも、一定期間の時効の完成猶予を図れます。ただし、以下のような深刻なケースでは、なるべく早めに弁護士への相談・依頼を検討すべきかもしれません。
・時効の完成が迫っている
・借主が夜逃げし、連絡が取れない
・保証人の所在が不明である
・裁判を視野に入れている
こうしたケースでは、法的に正しい手続きを踏まないと、時効が完成してしまうおそれがあるため、専門家の関与が有効です。弁護士に依頼することで、時効を更新するための手続きをスムーズに取りやすくなります。