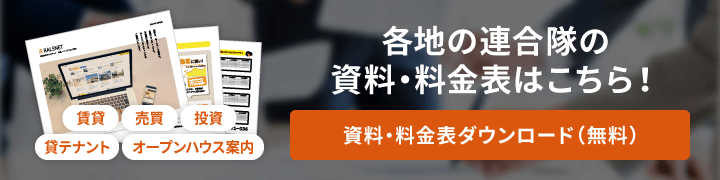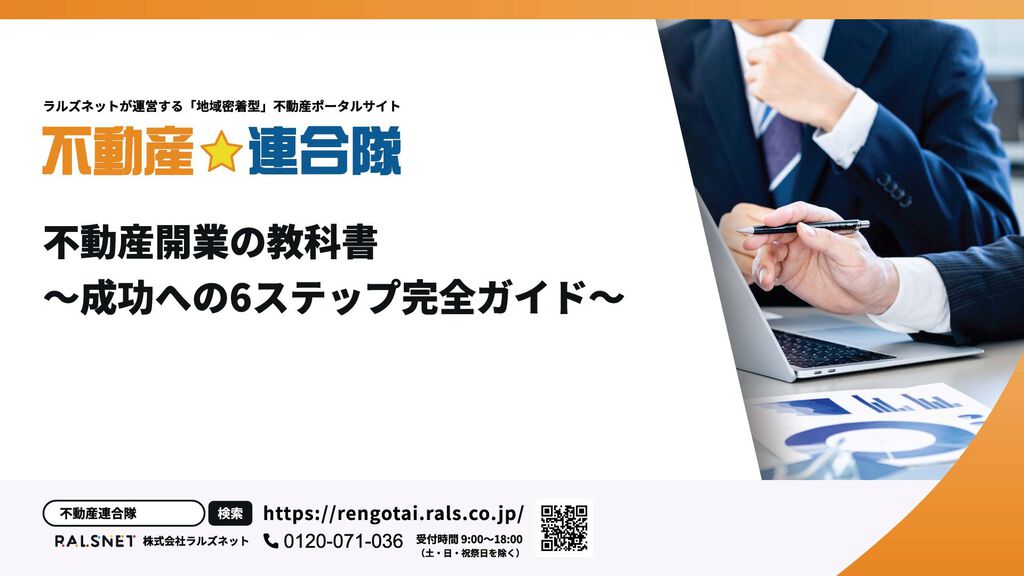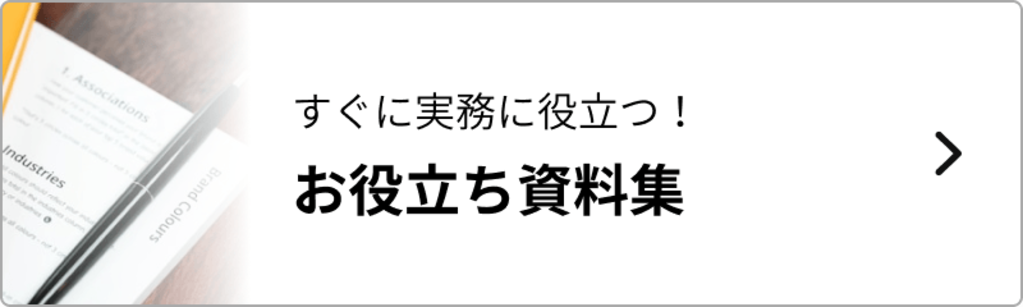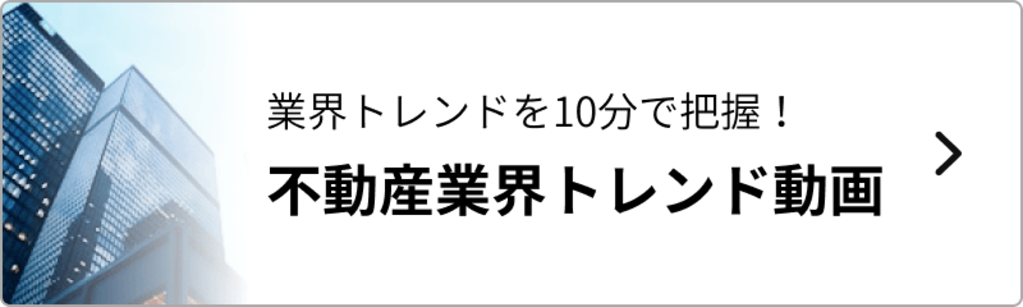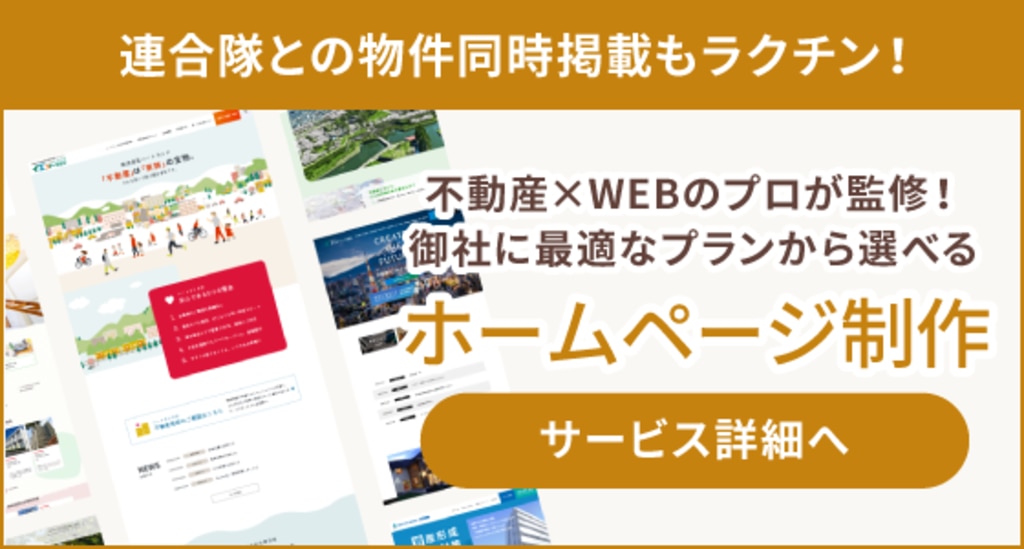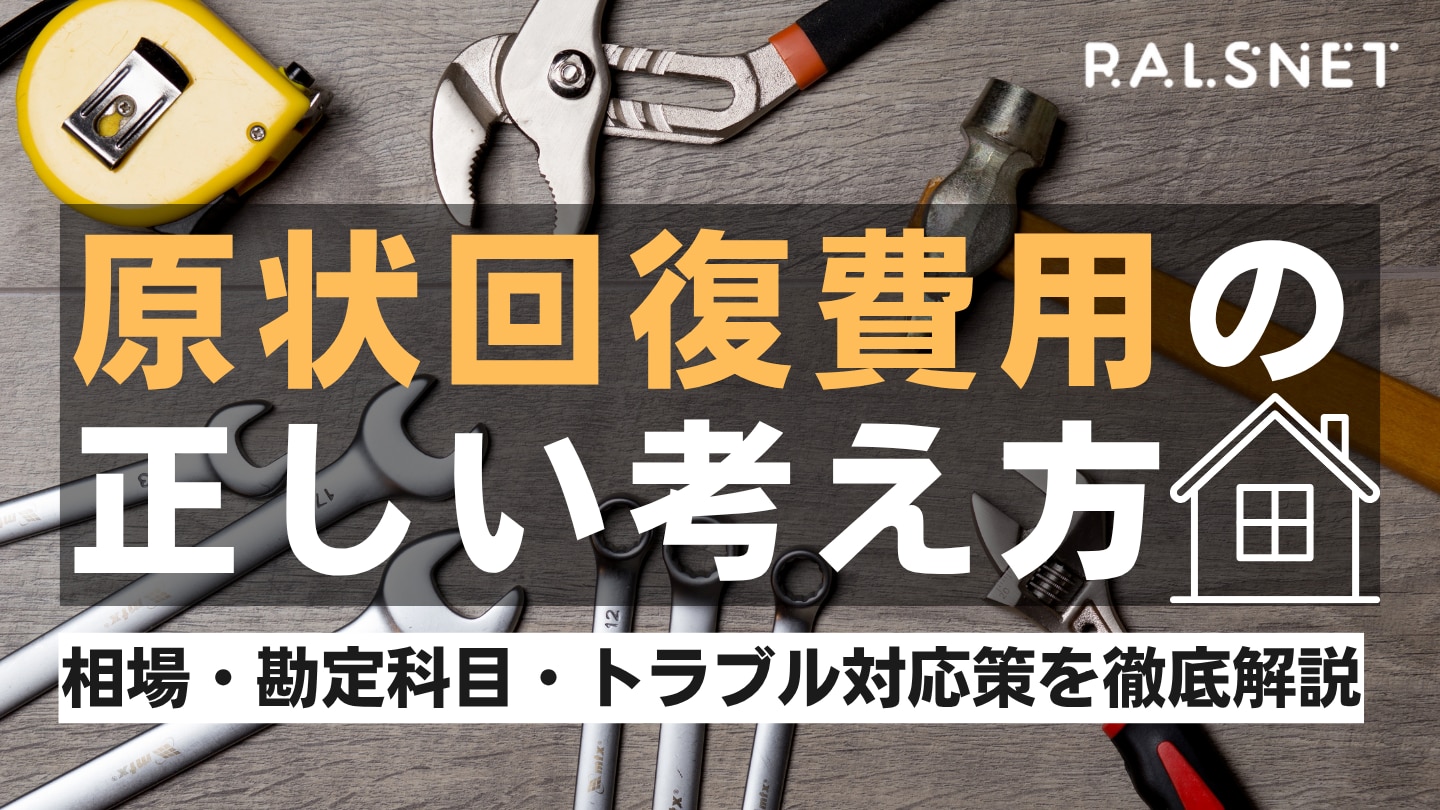
原状回復費用の正しい考え方|相場・勘定科目・トラブル対応策を徹底解説
賃貸管理でよくあるトラブルのひとつが、原状回復費用をめぐる問題です。退去立会い時、入居者から「費用が高すぎる!」「この傷は入居時からあった!」などのクレームを受けた経験がある不動産会社の方も多いのではないでしょうか。
本記事ではこうしたトラブルを防ぐために、原状回復費用の基本的な考え方から、相場の目安・会計処理のポイント・そしてトラブル防止策までをわかりやすく解説します。管理業務の実務で使える原状回復費用の知識をお届けします。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方とは?

原状回復費用を正しく判断するには、国土交通省が取りまとめて公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下、原状回復ガイドライン)」の考え方を把握する必要があります。
原状回復ガイドラインは、賃貸住宅の契約終了時における「原状回復の賃借人・賃貸人の費用負担」について、トラブル防止の観点から一般的な基準を示したものです。
原状回復ガイドラインの内容はあくまで「目安」であり、法的拘束力はありません。しかし、国土交通省と専門家が協議して作成された信頼性の高い内容のため、裁判所でも判断の根拠として広く採用されています。
原状回復ガイドラインは、オーナーや管理会社にとっては「請求の正当性」を示す重要な裏付けになります。ポイントを確認していきましょう。
原状回復ガイドラインの3つのポイント
原状回復ガイドラインの内容は、国土交通省の公式サイトで確認できます。すべてに目を通すとかなりのボリュームですが、基本的な考え方は以下の3つのポイントに集約されます。
・通常の住まい方、使い方による損耗や経年劣化は賃借人の負担としない
・故意・過失、善管注意義務違反等による損耗(汚れや傷、破損)は賃借人の負担とする
・もはや通常の住まい方、使い方とはいえない損耗や毀損は賃借人の負担とする
引用:大塚浩著「Q&Aわかりやすい賃貸住宅の原状回復ガイドライン<再改訂版>の解説と判断例(令和5年3月補訂)」
これに基づくと、通常の使用による汚れ・傷・破損や経年劣化はオーナー負担、それ以外は入居者負担ということになります。ただし、この考え方を知っていても、原状回復費用の判断で迷うこともあるでしょう。このような場合は、原状回復ガイドラインの別表1が役立ちます。その一例は以下の通りです。
損耗・毀損の内容 | 費用の負担者 |
畳の裏返し、表替え | 賃貸人(オーナー)の負担が妥当 |
家具の設置による床、カーペット のへこみ、設置跡 | 賃貸人の負担が妥当 |
テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ | 賃借人(入居者)の負担が妥当 |
冷蔵庫下のサビ跡 | 賃借人の負担が妥当 |
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ | 賃借人の負担が妥当 |
このほかにも、原状回復ガイドラインには数多くの事例が示されています。お時間のない方は、原本をダウンロードしたうえで別表の部分だけでも一読されることをおすすめします。
原状回復費用の特約は、「無効」と判断されることもある
原状回復ガイドラインは、不動産会社の仲介業務とどのように関わっているのでしょうか。
この点については、国土交通省で定めている重要事項説明には「解約時の敷金等の精算に関する事項」があり、ここに原状回復が含まれているという解釈が一般的です。
これを考慮すると、原状回復に関する特約がある場合には、その内容について丁寧に説明する必要があるでしょう。注意したいのは、賃貸借契約書に「〇〇の費用は借主負担」と明記されていても、内容によっては裁判で無効と判断されることです。
たとえば、賃貸借契約時に「通常損耗も借主負担とする」という特約を定めても、賃借人の理解・同意が不十分だと無効になった判例もあります。これを考慮すると、特約を設ける際には、賃借人に対して内容を丁寧に説明し、「内容を理解したか」の確認をすることが大切です。
原状回復費用には、オーナー負担分は含まれる?
管理会社やオーナーが注意したいのは「原状回復費用」という言葉の意味が、使われる場面によって変わることです。
一般的に、管理会社や工事会社の現場で「原状回復費用」という場合は、オーナーの負担分を含めた費用の総額を指すケースが多く見られます。たとえば、クロス張り替えやハウスクリーニングなど、入居者負担とオーナー負担の両方を合算した見積もり金額を「原状回復費用」と呼ぶことも少なくありません。
一方で、ガイドラインでは、原状回復を「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。つまり、ガイドラインに基づくと、原状回復費用とは「入居者負担分のみ」を意味することになるでしょう。
このように、同じ「原状回復費用」という言葉でも、法的な意味と実務上の使い方ではニュアンスが異なります。そのため、オーナーや入居者とのやり取りでは、原状回復という言葉をどのような意味で使っているのかを明確に伝えることが重要です。
原状回復費用という言葉への誤解を防ぐためにも、実務では以下のように区別して使用すると良いでしょう。
・原状回復費用(オーナー・入居者双方の負担分を含む)
→ 工事全体の総額を示す場合。見積書・請求書などで使用
・原状回復費用(入居者負担分)
→ ガイドラインや契約上の「入居者が支払う部分」を示す場合
原状回復費用の「一般的な項目」と「特殊な項目」

次に、「原状回復費用にどのような項目が含まれるか」を確認しておきましょう。重要なことは、原状回復の項目は、大きく分けて「一般的な項目」と「特殊な項目」の2種類があることです。
退去立会いをされる際には、「今回は特殊な項目が含まれないか」を確認しましょう。
原状回復費用の一般的な項目(ハウスクリーニング、クロス張り替え、床材・畳など)
原状回復費用の主な内訳と、具体的な事例は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
ハウスクリーニング | ・最も基本的な原状回復作業 ・水回り、床、窓(網戸含む)、エアコン、換気扇 など |
クロス(壁紙)張り替え | ・タバコのヤニや家具の擦れ、画びょう跡、日焼けなどの状況で張り替えを判断 ・全面張り替えと部分張り替えがある |
床材の張り替え・補修 | ・フローリングやクッションフロアの交換 ・傷、焦げ跡、日焼けなどの状況で張り替えを判断 |
その他 | ・畳の表替え・交換、巾木の交換、建具の交換、コーキング打ち替えなど |
原状回復費用の特殊な項目(庭の除草、ベランダ補修、ゴミ屋敷対応など)
物件の状況によっては、通常の原状回復費用ではカバーできない「特殊な項目」が発生することがあります。主に次のようなケースが該当します。
・ゴミ屋敷の清掃
物件内に大量のゴミがあり、入居者が退去日までに所有物を整理できない場合、専門会社による分別・撤去・清掃が必要になることがあります。
・残置物の処分
敷地内や共用部に大型家具や生活用品が放置されるケースでは、撤去・廃棄費用が追加で発生します。
・ペット飼育による損耗
壁や床の傷、臭いの除去などが必要な場合、クロスや床の全面張り替え・脱臭・消毒といった追加作業が発生します。
・庭・ベランダの除草・補修
庭やバルコニーが放置され雑草や汚れが目立つ場合、清掃や塗装補修などの費用が必要になることがあります。
このような特殊な項目の対応は、費用が高額になりやすく、入居者との費用負担の線引きも難しいケースが多いです。
原状回復費用のマンションやオフィスの相場

原状回復のトラブルを防ぐには、不動産会社の担当者が相場感を把握しておくことが大切です。
原状回復費用が高すぎると、入居者とオーナー双方が納得できずに、トラブルに発展してしまいます。原状回復費用の相場を意識した「適正価格」を目指しましょう。
※以下の金額は、オーナー・入居者双方の負担を合計した「工事全体の総額」です。
※内容は「ハウスクリーニング+クロス全面張り替え」を想定しています。
マンションの原状回復費用の相場
マンションの原状回復費用は、専有面積と施工内容によって決まります。まず、どの物件でも必要となるハウスクリーニングの相場を確認してみましょう。
間取り | 相場(ハウスクリーニング総額) |
ワンルーム・1K(20~25㎡程度) | 3~5万円程度 |
1DK・1LDK(30~45㎡程度) | 5~10万円程度 |
2DK・2LDK(50~65㎡程度) | 10~20万円程度 |
2LDK以上 | 20万円以上 |
上記は一般的なハウスクリーニングの相場であり、汚れの程度や清掃範囲によって実際の金額は変わってくるでしょう。これに加え、クロスや床材、設備交換などの費用が必要となります。
たとえば、ワンルーム(25㎡)で以下の原状回復工事をした場合、相場は15万円程度〜になります。
・ハウスクリーニング
・クロス張り替え
・クッションフロア張り替え
・ソフト巾木交換 など
オフィスの原状回復費用の相場
オフィスの原状回復費用は、ケースバイケースというのが実状です。理由は、以下の項目によって原状回復費用が大きく変わってくるからです。
・規模
・ビルのグレード
・スケルトン(躯体むき出し状態)が必要か
・空調、照明、配線の復旧までを含むか など
これを踏まえたうえで、一般的なオフィスの原状回復費用の目安は以下のとおりです。
規模 | 相場(坪単価) |
小規模オフィス(~50坪) | 3~5万円/坪 |
中規模オフィス(51~100坪) | 4~8万円/坪 |
大規模オフィス(101坪~300坪) | 8~12万円/坪 |
たとえば、坪単価5万円で50坪のオフィスであれば、約250万円が目安となります。
原状回復費用の勘定科目

原状回復費用は、内容によって「修繕費」または「資本的支出」に区別されます。
・修繕費:クロスの張り替えや床の補修など、もとの状態に戻すための支出
・資本的支出:建物・設備などの価値を高めたり、耐用年数を延ばすための支出
修繕費は経費として計上でき、利益を圧縮する効果があります。一方、資本的支出は耐用年数に応じて減価償却をしていきます。なお、資本的支出では、その内容によって「建物」「建物附属設備」「構造物」などの勘定科目が使われるため注意しましょう。
小規模な資本的支出は経費として扱える
資本的支出は、以下の要件に該当すると経費として計上することが可能です。
・20万円未満か
・周期がおおむね3年以内か
・通常の維持管理のものか
・前年末取得価額の10%以下か など
原状回復費用を「修繕費」「資本的支出」に仕訳する際は、下記の国税庁の公式サイトに掲載されているフローチャートを利用すると便利です。
原状回復費用のトラブルを防止するポイント

原状回復費用をめぐるトラブルの多くは、「説明不足」と「認識のズレ」によって起こります。これを解消するには、以下の3つの対策を意識し、貴社のスキームやマニュアルを構築することが重要です。
契約時に原状回復について説明する
トラブルを防ぐ第一歩は、入居前の段階で原状回復費用の内容や考え方を伝えておくことです。原状回復費用については、重要事項説明の「敷金等の精算に関する事項」で説明することが義務づけられています。
しかし、入居者が原状回復の知識を持っていない場合は、ガイドラインを参考にしながら基本的な考え方を伝えるのが賢明でしょう。とくに、原状回復に関する特約を設ける場合は、より丁寧な説明が必要です。
写真撮影やチェックシートで証拠を残す
原状回復費用のトラブルを減らす2つ目のポイントは、入居時点の現況記録を残すことです。写真と確認リストなどで「入居時の状態」を記録しておくことで、お互いの主張の食い違いを減らせます。
■ 入居時の物件状況撮影
・リビング、キッチン、水回りなどスペースごとに撮影する
・破損や傷がある箇所は、アップ目に撮影する
・ファイル名や図面上で位置がわかるように整理する
■ 原状回復確認リスト
・国土交通省が提供する「原状回復確認リスト」を流用またはカスタマイズする
・借主と貸主双方で記名、捺印する
・借主が原本、貸主がコピーを保管する
退去立会い時にエビデンスに基づいて説明する
退去立会いでは、エビデンスに基づいて原状回復費用を説明するのが鉄則です。
・現況
・入居時に撮影した写真
・入居時に取り交わした原状回復確認リスト
これらのエビデンスと共に、原状回復ガイドラインが判断の目安になることを解説すると、入居者の納得感が高まりやすいです。
原状回復費用を理解して退去時トラブルを回避しよう

今回は、賃貸管理における原状回復費用の考え方と、実務でのトラブル防止策について解説しました。
とくに重要なのは、「原状回復ガイドライン」の基本を理解し、通常損耗と入居者負担の線引きを明確にしておくことです。あわせて、写真やチェックシートによる証拠の記録、丁寧な説明の徹底もトラブル回避には不可欠です。
また、原状回復費用の実務では「費用総額」と「入居者負担分」の定義にズレが生じやすく、オーナーや入居者との誤解を防ぐためにも、言葉の使い分けと説明が求められます。
こうした管理業務を丁寧に行う一方で、安定した入居者獲得のためには「集客力の強化」も重要です。地域特化型ポータル「不動産連合隊」なら、地元ユーザーに強く訴求できるだけでなく、物件ごとの反響分析や掲載効率にも優れており、入居から退去まで一貫して管理を支えてくれます。
トラブルの少ない管理と安定集客の両立を目指すなら、ぜひ「不動産連合隊」へのご相談をご検討ください。
原状回復費用に関するよくある質問
退去費用で入居者が払わなくていいものは?
入居者が負担しなくてよいのは「通常の使用による損耗・経年劣化」にあたる部分です。たとえば、以下のようなケースはオーナー(貸主)の負担となります。
・日焼けや照明の熱によるクロスの変色
・家具の設置跡(軽いへこみなど)
・エアコンや給湯器など設備の老朽化による故障
・フローリングの経年変化によるツヤ落ち
これらは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも明記されており、「入居者が通常の注意を払って生活していても避けられない損耗」として扱われます。一方で、タバコのヤニ汚れやペットによる傷・臭い、子どもの落書きなどは「過失・故意」に該当し、入居者負担になります。
原状回復費用が100万円以上になるのはどのようなケース?
一般的な原状回復費用は5〜20万円程度に収まります。しかし、以下のようなケースでは100万円を超えることもあります。
・壁、床、天井の全面張り替え(タバコ・ペット・カビ汚れなど)
・水漏れや火災などによる構造部分の補修
・店舗や事務所など、内装造作の撤去費が必要なケース
・数十年など長期間居住による大規模修繕
とくに「ペット可物件」や「DIY可能物件」では、自由度が高い分、退去時に大きな修繕費用が発生することがあります。事前に契約書や特約条項で「どこまで入居者負担とするか」を明確にしておくことが、トラブル回避のポイントです。
原状回復費用と敷金の関連性は?
賃貸契約時に借主が貸主に預ける敷金は、家賃滞納による債務返済や、入居者の過失や故意で部屋を損傷させた場合の原状回復費に充てられます。退去時に発生した実費を差し引いたうえで、残額があれば入居者へ返還されます。
ただし、「敷金がある=すべて賄える」というわけではありません。敷金を用いても、費用が賄えない場合は、入居者に対して追加の費用を求める必要があります。