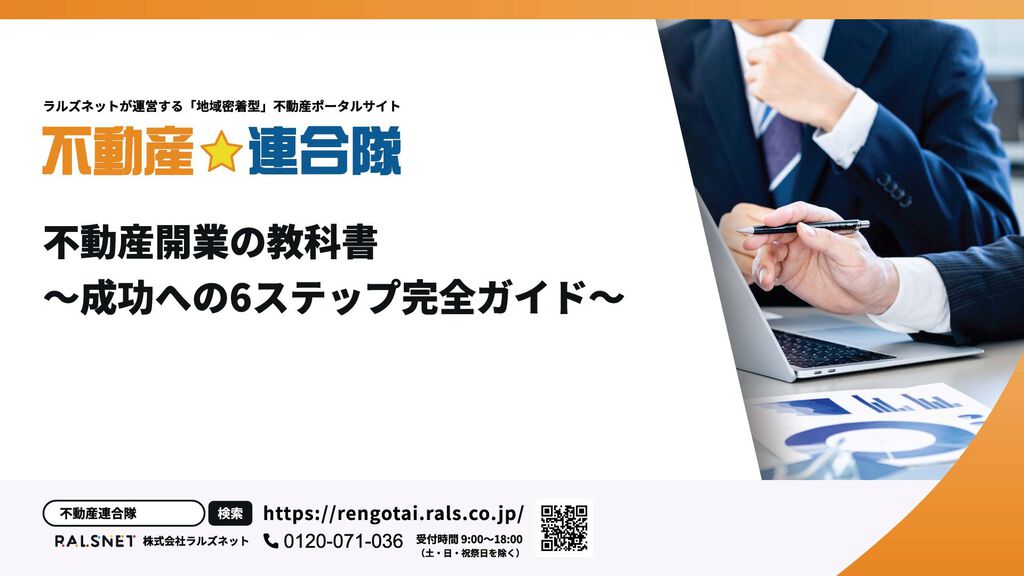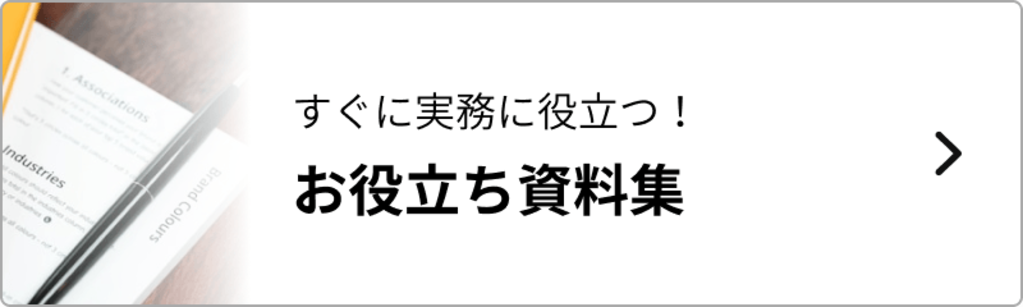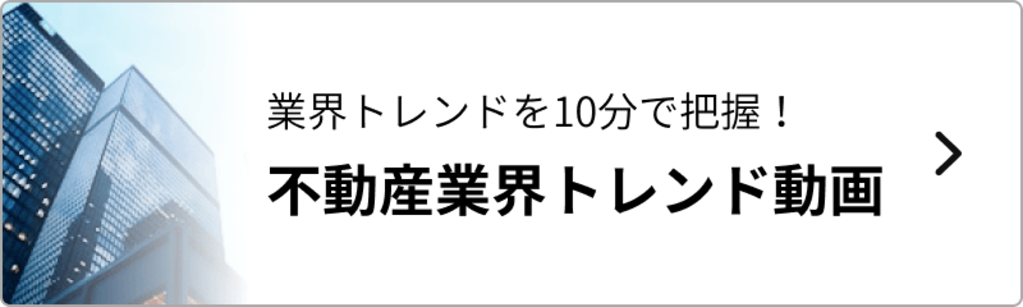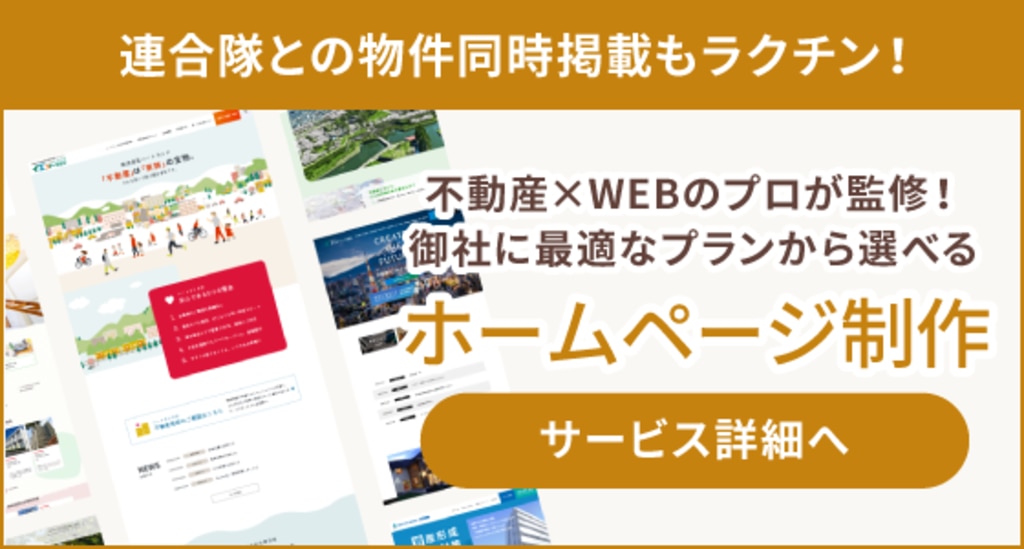【2025年】首都圏の家賃相場推移|繁忙期の変化と戦略をプロが解説
2025年1~3月の繁忙期における首都圏の家賃動向は、物件種別やエリアによって異なる特性があります。家賃動向を理解することは、今後の投資戦略を練るうえで重要です。
本記事では、首都圏における物件種別・エリア別の家賃動向から収益を圧迫する2つのコスト、「売る人・買う人・持つ人」それぞれに適した投資戦略について解説します。不動産オーナーとのつながりがあるなら、ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
【物件種別】首都圏の家賃動向データ(2025年1-3月期)

2025年1~3月の繁忙期における首都圏の家賃動向を、物件種別ごとに解説します。本データはレインズの賃貸成約事例に基づき、直近3年間および家賃の推移が変則的だったコロナショック前(2019年)と比較しています。今後の投資戦略を練るうえで、参考にしてみてください。
マンションは全エリアで前年・コロナ前超え
マンションの家賃水準は、首都圏の全エリア(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)において、前年比およびコロナショック前よりも上昇しています。エリアによっては、コロナショック前と比較して2割近く水準が上がっている事例もあります。マンションは成約事例の登録件数が多いため、家賃動向のトレンドを把握するのに役立つでしょう。
アパートはマンションより緩やかな上昇傾向
アパートの家賃水準は、マンションと比較して安価な傾向にあるものの、繁忙期においては前年比およびコロナショック前よりも上昇しています。エリアによってはコロナショック前と比べて2割近く上がっている一方で、全体的には横ばい傾向(前年比)にあり、マンションほど急激な上昇ではありません。なお、アパートは各エリアの成約事例がマンションに比べて少ない点には、注意が必要です。
【エリア別】マンション家賃の詳細な動向

首都圏の家賃動向はエリアによって異なる特性を持っています。ここでは、成約事例が豊富でトレンドを把握しやすいマンションに限定し、主要な首都圏エリアの動向について掘り下げて解説します。
東京都|東京23区では都心部を中心に高騰が続く
東京23区におけるマンションの家賃上昇は極めて顕著です。とくに、千代田区や港区といった都心3区では、賃料の㎡単価が5,000円を超えるなど高い水準で推移しています。その他のエリア(豊島区など)を含めても、東京23区はすべてのエリアで前年比およびコロナショック前の水準を上回る結果となりました。
都心部では、コロナショック前と比較して2割近くの上昇を見せるエリアもあります。このような高い賃料水準と需要の高さこそが、国内外から不動産投資の注目を集める要因です。
神奈川県|横浜市の一部で上昇ペースに鈍化の兆し
横浜市におけるマンションの家賃動向は、東京23区とは異なります。長期的なトレンドとして見れば、コロナショック前と比べて全エリアで家賃水準が上昇していることは確かです。しかし、前年比で比較すると、家賃水準が下がっていたり、横ばいになっているエリアが増えてきています。今後の動向に注視する必要があるでしょう。
神奈川県|川崎市も横ばいのエリアあり
川崎市においても、全体的に見ればマンションの家賃水準は堅調です。家賃水準は、すべてのエリアでコロナショック前よりも上昇しています。しかし、横浜市と同様に横ばい(前年比で上昇率100%台)のエリアも見られます。長期的な水準としては向上しているものの、直近の短期的な変動においては、家賃の上昇が一定の水準で落ち着きつつあるでしょう。
埼玉県・千葉県|全体的に上昇傾向
埼玉県や千葉県の家賃水準は、直近3年間において約7%上がっています。家賃水準が上がっている主なエリアは、埼玉県では和光市やさいたま市浦和区、千葉県では浦安市や市川市などです。長期的に見ても上昇傾向にあり、コロナショック前の家賃水準よりも高いことがわかります。
参考:LIFULL HOME'S|埼玉県の賃貸マンション
|千葉県の賃貸マンション
今後の不動産投資で注意すべき2つのコスト

不動産投資の収益を圧迫する要因として、注意すべき2つのコストがあります。家賃上昇が見込めない物件では、これら2つのコスト増がキャッシュフローを悪化させる原因となるため、事前の理解とリスク対策が重要です。
建築費・修繕費の上昇で利益が圧迫される
不動産投資における大きな懸念材料の一つが、建築費と修繕費の上昇です。とくに、家賃が横ばい傾向にある物件や大規模修繕を控えている物件は、建築費・修繕費のコスト増は利益を直接的に圧迫します。建築費・修繕費が上昇しているため、より多くの自己資金を投入する必要性が高くなります。
金利上昇でキャッシュフローは確実に悪化する
現在、多くの金融機関で不動産投資ローン(主に変動金利)の利上げが進んでおり、キャッシュフローの悪化に直結しています。たとえば、2024年10月から今年の4月にかけて、0.4%程度の利上げを行なったケースが多く見られます。仮に、融資額1億円・期間30年・金利2.3%→2.7%に上昇した場合、月間のキャッシュフローは約2万円(年間で約25万円)も悪化するでしょう。家賃が上がらない物件では、この金利上昇分がそのまま収益を圧迫するため、借入リスクは確実に高まります。
家賃動向から考える今後の投資戦略

家賃上昇と増加するコストという2つの市況変化を踏まえ、不動産を「売る人」「買う人」「持つ人」のそれぞれにとって、適した戦略を考える必要があります。家賃上昇と増加するコストから導かれる、今後の不動産投資の方向性について解説します。
【売る人】修繕・空室・借入リスクが高い物件保有者
現在、不動産価格は高騰しているため、売却を検討するには良い時期だと言えます。とくに、以下の方は売却を検討してみましょう。
- 借入金が多く家賃の低い物件を保有している
- 大規模修繕が必要な物件や修繕が多い物件を保有している
- 賃貸需要が乏しく空室の多い物件を保有している
収益物件の場合は、築年数が古くなるほど融資期間が短くなり、価格が下がってしまうこともあります。適切な売却時期を見極めて早めの決断を行うことで、リスクを軽減できるでしょう。
【買う人】現金や法人活用で低金利を活かせる人
金利が上昇している状況でも、優位に投資を進められる方がいます。以下の方は、積極的に投資を検討しても良いでしょう。
- 低金利で融資を受けられる
- 法人や相続対策などで現金や高い属性を活かせる
- 課税所得が高く減価償却によって節税効果が得られる
金利コストが収益を圧迫する中でも、自己資金を多めに投入したり低金利が確保できる属性を持ったりすることが、賃貸経営を成功させる鍵になります。
【持つ人】相続対策や自己資金に余裕のある地主層
現在保有している物件を持ち続けるべきなのは、投資目的以外にメリットがある地主層です。たとえば、「相続対策になる」などのメリットがあれば、物件を持ち続けても良いでしょう。また、すでにローンを完済済みでキャッシュフローに余裕がある方も、「保有する」という選択肢があります。金銭的な余裕があることで、コスト上昇というリスクを気にし過ぎず健全な賃貸経営が行えます。
賃貸経営では、経費計上できる項目が多くありません。そのため、修繕やリフォームを通じて物件の価値を維持したり、家賃を上げられるように努力をしたりすることが重要です。
まとめ|家賃動向を理解して不動産投資を最適化しよう!

2025年繁忙期の首都圏家賃動向を調査すると、マンションを中心に全体的な上昇が見られました。しかし、エリアによっては上昇が緩やかになったり、横ばいになったりする兆しも見られます。一方で、建築費・修繕費・金利上昇というコストが投資のキャッシュフローを圧迫しています。まずは、これらの現状を理解することから始めましょう。そのうえで、物件状況や自身の属性(借入状況・自己資金・相続対策など)を考慮した戦略(売却・購入・保有)を選択し、実行していくことが成功への近道です。