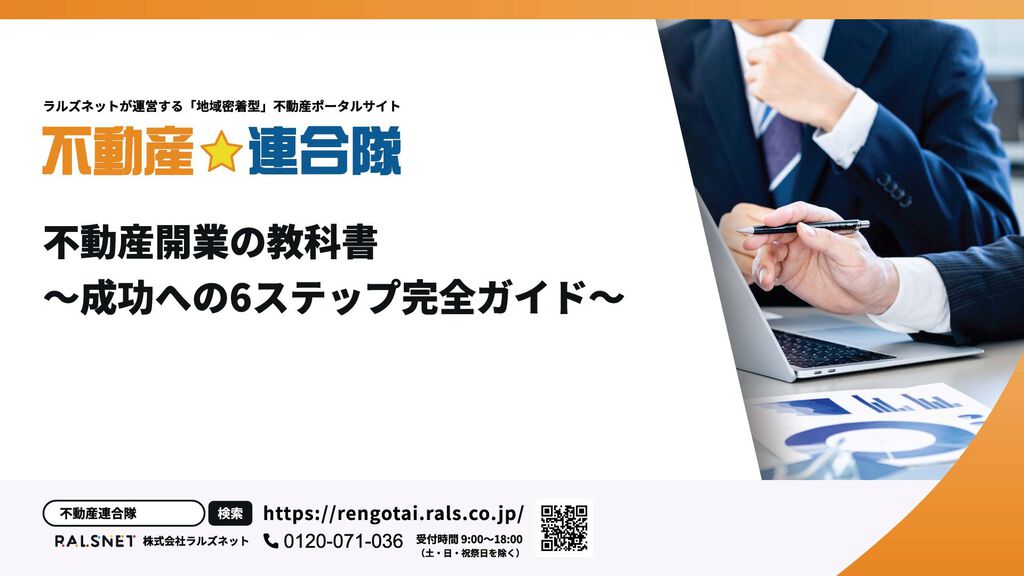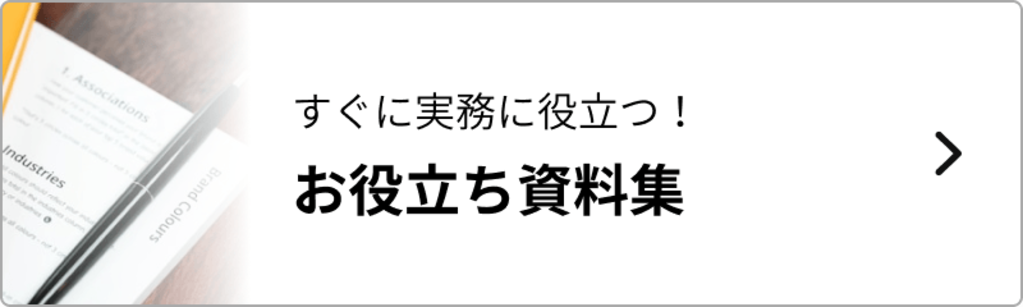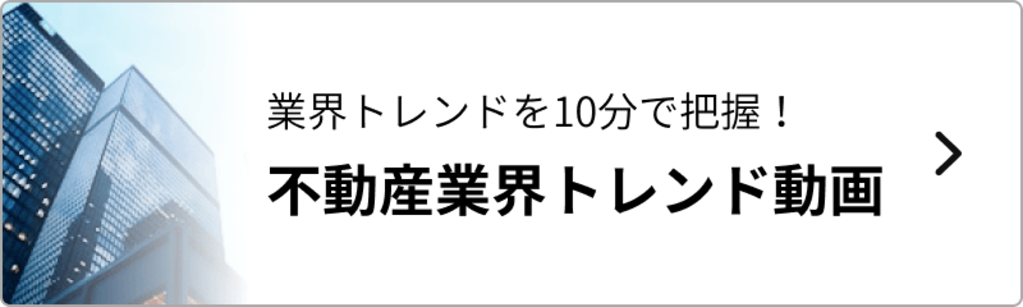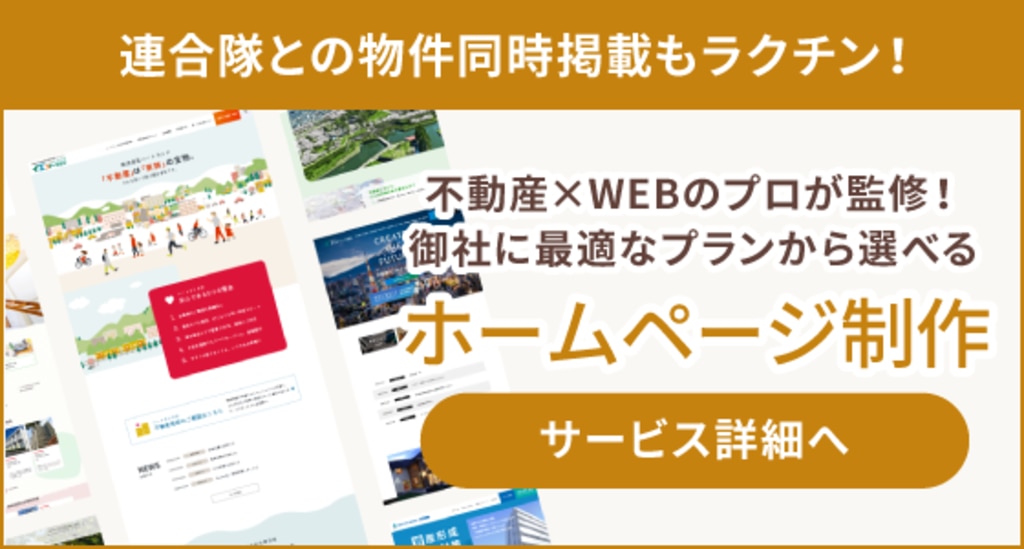不動産投資に役立つCPM理論|CF・IRV・3つの利回りで投資効率を可視化
不動産投資では、CPM理論の活用が役立ちます 。誰もが気軽に不動産オーナーになれる現代だからこそ、倫理観と収益最大化の哲学を根底に置くCPM理論の知識は不可欠です。
本記事では、 不動産経営の収益を可視化するキャッシュフローツリーから、投資の健全性を図る3つの利回り、レバレッジの判断基準まで解説します。お客様に客観的かつ安全な投資戦略を提案するためにも、参考にしてみてください。
目次[非表示]
CPMとは?「倫理と利益最大化」の哲学
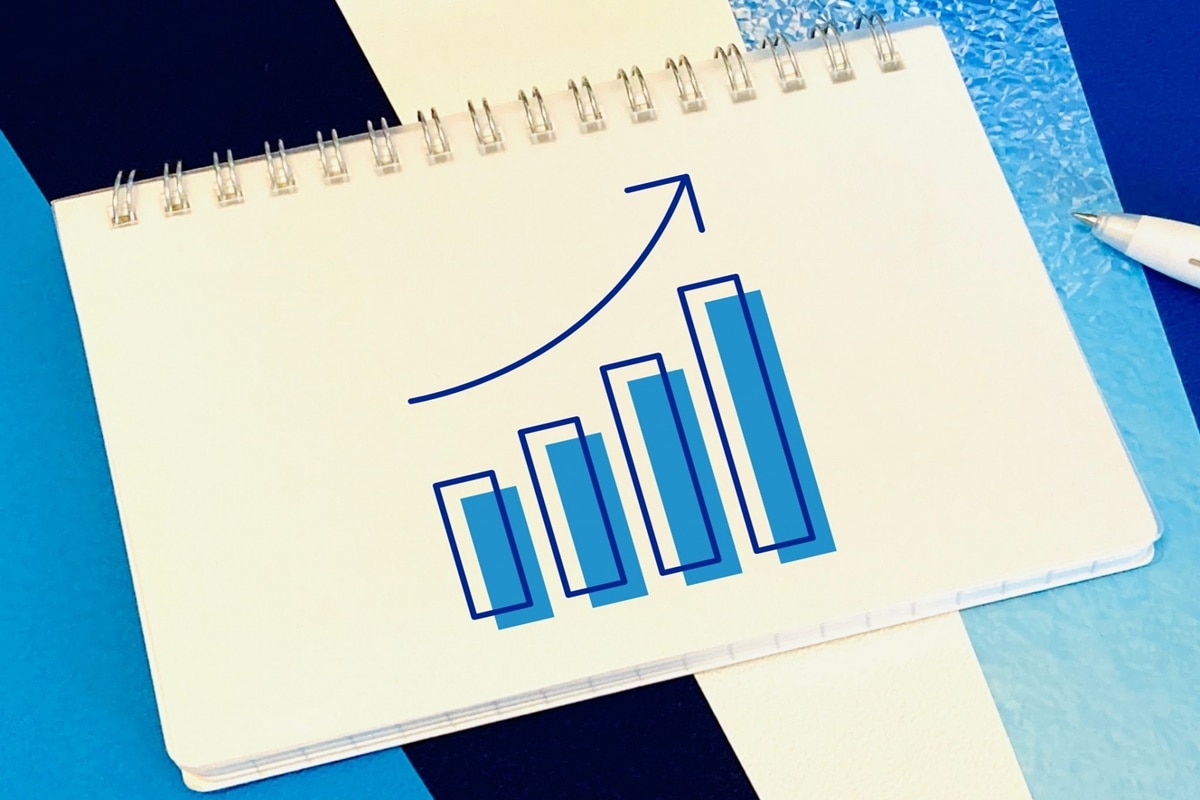
CPM(公認不動産経営管理士)とは、 アメリカの歴史ある不動産資格です。CPMは、倫理・利益相反の排除を根底に置き、不動産投資家の収益を最大化させる目的があります。
CPMを運営している全米不動産管理協会(IREM)は、日本の不動産業界団体が戦後に誕生した一方で、戦前の1933年から存在しています。倫理やコンプライアンスが当たり前の現代に、 戦前の不動産業界から「倫理」を掲げてきたCPMの姿勢は先進的といえるでしょう。
参考:IREM| CPM倫理規定
CPM理論と他の投資理論との違い
CPMが他の投資倫理と異なるのは、 先進的な倫理観を重視する点です。倫理から不動産投資・賃貸管理のすべてをワンストップで、21日間かけて学びます。具体的な学習内容は、以下のとおりです。
- 倫理
- キャッシュフロー分析
- 融資分析
- メンテナンス方法
- マネジメント方法
- マーケティング戦略
- 不動産評価方法 など
近年、給与所得者向けの不動産投資ローンが増加する中で、不動産投資の知識が一般化してきています。CPMの考え方に基づく投資指標(キャッシュフローツリーやIRVの法則など)においても、資格の有無にかかわらず広く普及し始めています。
不動産会社や営業担当者は、 CPMの考え方を知識として知っているだけでなく、実際の営業現場で実践していくことが重要です。
参考:IREM| CPM必修科目・受講日程
不動産投資で重要な「キャッシュフローツリー」
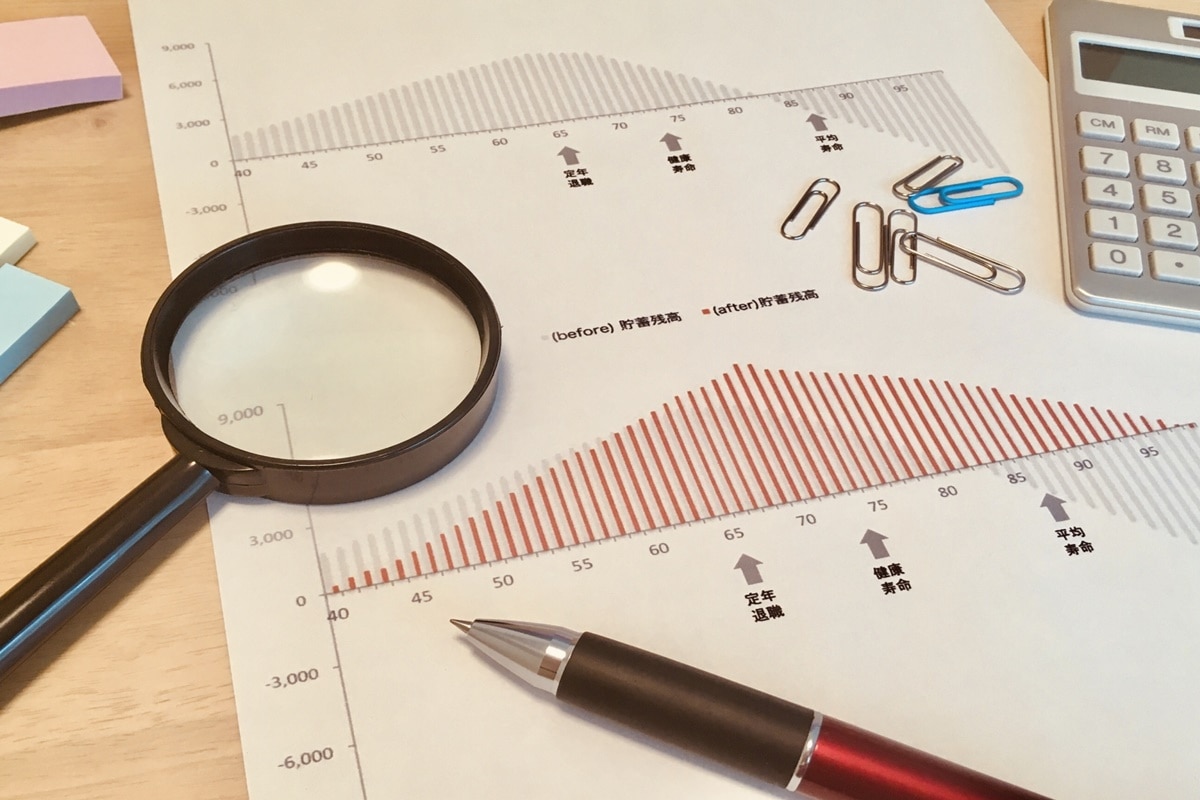
不動産投資の成功は、「キャッシュフローツリー」で決まると言っても過言ではありません。キャッシュフローツリーを活用すれば、手残りの目安から賃貸経営の健全性・安全性などを客観的に判断できます。
キャッシュフローツリーの基本構造
キャッシュフローツリーは、 不動産の収益性を図るために必要な構成要素を示す表です。総潜在収入(満室時のMAX家賃収入)から各種費用を差し引き、最終的にオーナー様の手元にいくら残るかがわかります。
キャッシュフローツリーのステップ・構成要素・詳細は、以下のとおりです。
ステ ップ | 構成要素 | 詳細 |
1 | 総潜在収入(GPI) | 満室時の年間家賃合計 |
-空室・未回収損 | 空室リスクや入居者の未回収損(滞納)を差し引く | |
2 | 実行総収入(EGI) | 家賃収入から空室などのリスクを差し引いた金額 |
-運営費(Opex) | 物件を維持運営するのに必要な運営費を差し引く | |
3 | 営業純利益(NOI) | ステップ2までの経費を差し引いた純利益 |
-年間返済額(ADS) | 借入がある場合は、営業純利益から年間返済額(元本と利息の合計)を差し引く | |
4 | 税引き前キャッシュフロー(BTCF) | ステップ3後に算出できる税引き前の手残り金額 |
5 | 税引き後キャッシュフロー(ATCF) | 税引き前キャッシュフローから、所得税や住民税を差し引いた後の最終的な手取り金額を算出 |
キャッシュフローツリーの構成要素を理解しておくことで、不動産投資が成功しやすくなるでしょう。
賃貸経営の健全性を図る目安の数値指標
収益物件には、健全性を判断するための数値指標が存在します。数値指標はあくまで目安ですが、 物件の収益性を評価する上で非常に有効です。総潜在収入(家賃収入)を100%とした場合の、数値指標は以下のとおりです。
- 空室ロス:10 %以下
- 運営費:20 %以下
- 年間返済額:55 %以下
- 税引き前キャッシュフロー:15 %以上
金融機関が最重要視する「資金繰りの指標」

金融機関が融資の際に最重要視する指標として、資金繰りの指標があります。物件の生み出す純利益が、借入返済に対して十分な安全性を図る指標です。主に「返済倍率(DCR)」と「損益分岐点(BER)」が用いられます。
返済倍率 (DCR) の目安と重要性
返済倍率(DCR)とは、 返済額に対する安全性 を図る指標です。返済倍率は、「 営業純利益(NOI)÷年間返済額(ADS)」 で算出できます。
返済倍率の数値が低いほど安全性も低くなります。たとえば、返済倍率が1の場合は、 物件の営業純利益と年間返済額が同額であることを意味しています。つまり、不動産投資として利益を出せていない状態です。
金融機関では返済倍率を重視しており、 1.2~1.3倍以上 を求められる傾向にあります。返済倍率を確認して、借入の安全性を把握しておきましょう。
損益分岐点 (BER) から見る経営の余裕
損益分岐点(BER)は、 経営状況の安全性を図る指標です。損益分岐点は、「固定費(運営費と年間返済額の合計)÷総潜在収入(GPI)」で算出できます。
損益分岐点は、 数値が低いほど経営に余裕があると判断でき 、70~75 % 以下 が目安です。損益分岐点を見ることで、物件がどの程度の空室に耐えられるかを把握するのに役立ちます。
不動産査定の基本公式「IRVの法則」

不動産査定の基本公式が、IRVの法則です。IRVの法則では、「価格(V:バリュー)・利回り(R:レート)・収入(I:インカム)」という三要素の関係性を表しています。不動産投資家にとって基本的かつ重要な考え方であり、CPM理論においても学習する内容です。
IRVの法則(収入・ 利回り・価格)活用法
IRVの法則を構成している三要素は、以下のように 入れ替えることで、各収入・利回り・価格を出せる関係性にあります。
- 価格=収入÷利回り
- 利回り=収入÷価格
- 収入=利回り✕価格
たとえば、収益物件の価格が1,000万円、年間200万円の家賃収入を生んでいる場合の利回りは、「200万円÷1,000万円=20 %」です。このように、 IRVの法則を活用することで、不動産投資に役立つ要素の数値を導き出せます。
投資効率を決定づける「3つの利回り」

CPM理論では、不動産投資における投資効率を図るため、「物件・投資家・銀行」という3つの利回りを比較することが重要です。各利回りの詳細を解説します。
物件の利回り(実質利回り/ネット利回り)
物件の利回り(実質利回り/ネット利回り)とは、 物件が持っている本来の収益力を示す数値です。物件の利回りが高いほど、購入した物件から得られる収益が高くなります。
物件の利回りを算出する計算式は、「(年間家賃収入 - 年間維持管理費・経費)÷(物件購入価格 + 購入時の諸経費)✕100」です。
なお、物件の利回りには「表面利回り」もあります。ただし、 表面利回りは諸経費を考慮していないため、より現実的な数値ではない点に注意が必要です。
投資家の利回り(CCR)
投資家の利回り(CCR)とは、 自己資金に対する投資効率 を示す数値です。投資家の利回りが高いほど、投資効率が良いと判断できます。
投資家の利回りを算出する計算式は、「税引き前キャッシュフロー÷自己資金額×100」です。
3つの利回りの中では、最も重要だとされています。また、後述するレバレッジ効果を判断するための利回りとしても活用されます。
銀行の利回り(K %)
銀行の利回り(K%)とは、 金融機関側から見た収益率 を示す数値です。銀行の利回りが低ければ、銀行側が融資に対するリスクも低いと判断している可能性があるでしょう。
銀行の利回りを算出する計算式は、「年間返済額÷融資額×100」です。
銀行の利回りは、銀行側から見た安全性を図る指標として利用できるほか、 レバレッジ効果の判断基準にもなります。
正のレバレッジと負のレバレッジの判断基準
投資家の利回りと銀行の利回りを比較することで、レバレッジ(融資による投資効率を上げる仕組み)が効いているかどうかの判断が可能です。
種類 | 状態 | 詳細 |
正のレバレッジ | 投資家の利回り>銀行の利回り | 現金購入時よりも投資効率が向上し、収益が増加する理想的な状態のこと。 |
負のレバレッジ | 投資家の利回り<銀行の利回り | 現金購入時よりも投資効率が低く、収益が減少する望ましくない状態のこと。 |
負のレバレッジで不動産投資を続けると、収益が悪化してしまう原因になります。 融資を利用して不動産を購入する場合は、 正のレバレッジかどうかを見極めることが重要です。
まとめ|CPM理論を活用して投資戦略を提案しよう!
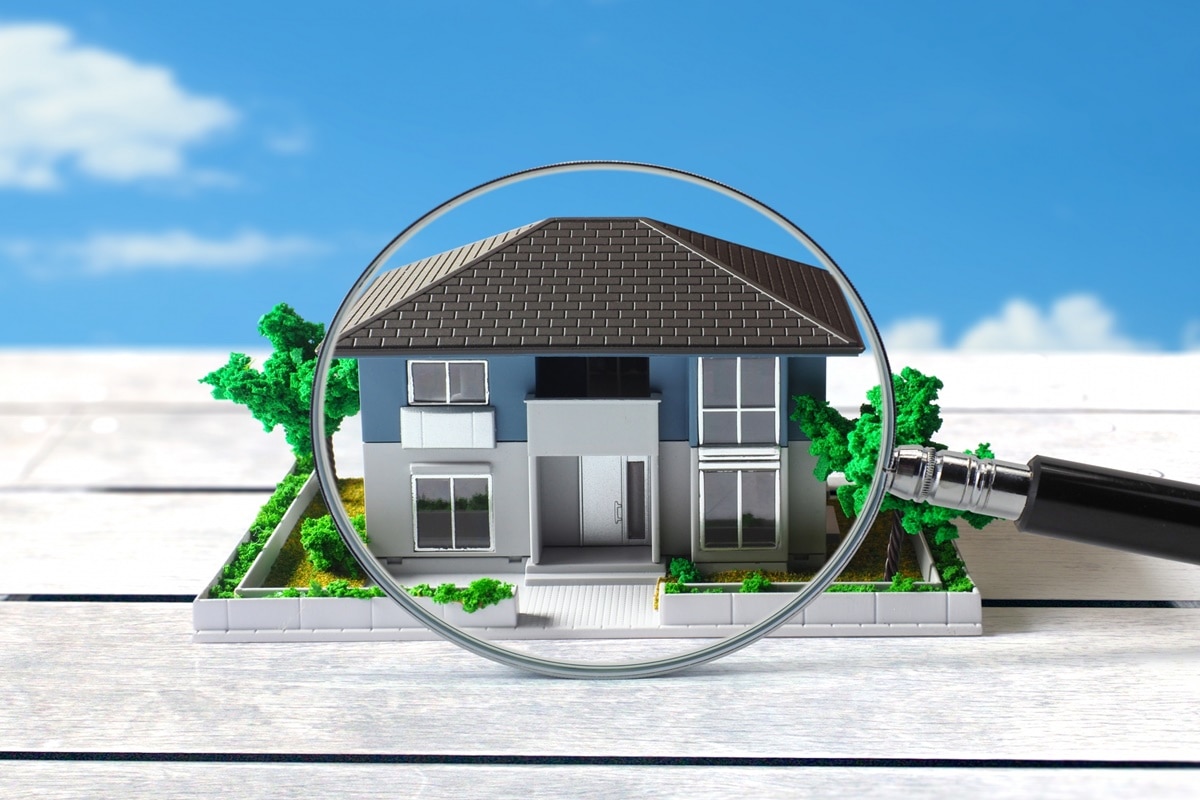
CPM(米国不動産経営管理士)は、倫理観を重視しながら不動産投資や賃貸管理に関する内容をワンストップで学び、収益の最大化を目指せる資格です。CPM理論で学ぶ キャッシュフローツリーやIRVの公式、3つの利回りといった内容は、 不動産投資・賃貸管理を成功させる ために重要です。知るだけではなく実践することで結果につながるため、日々の投資戦略にCPM理論を活用していきましょう。