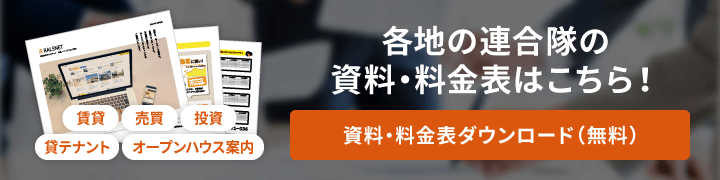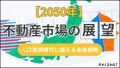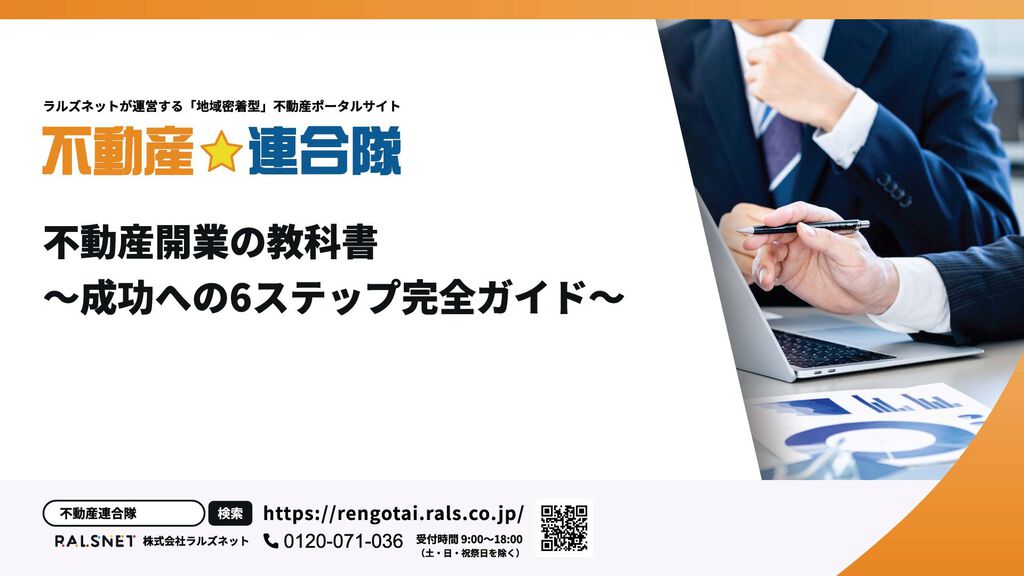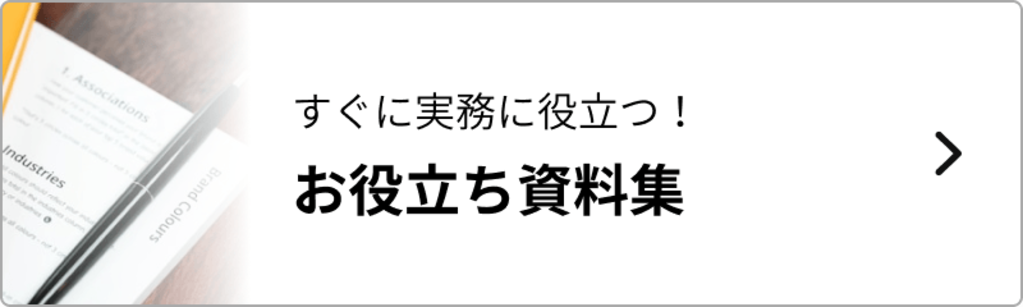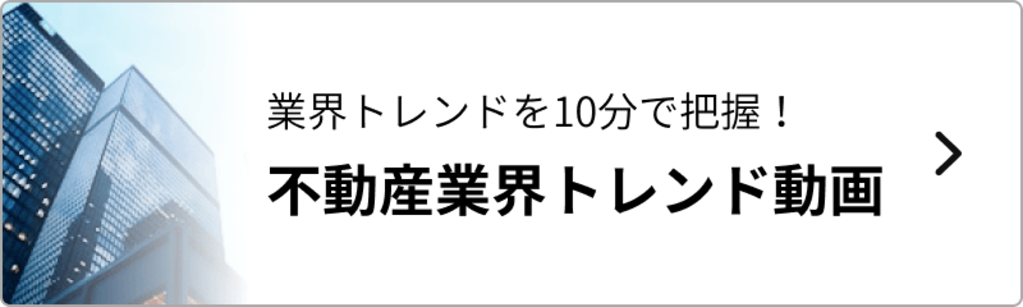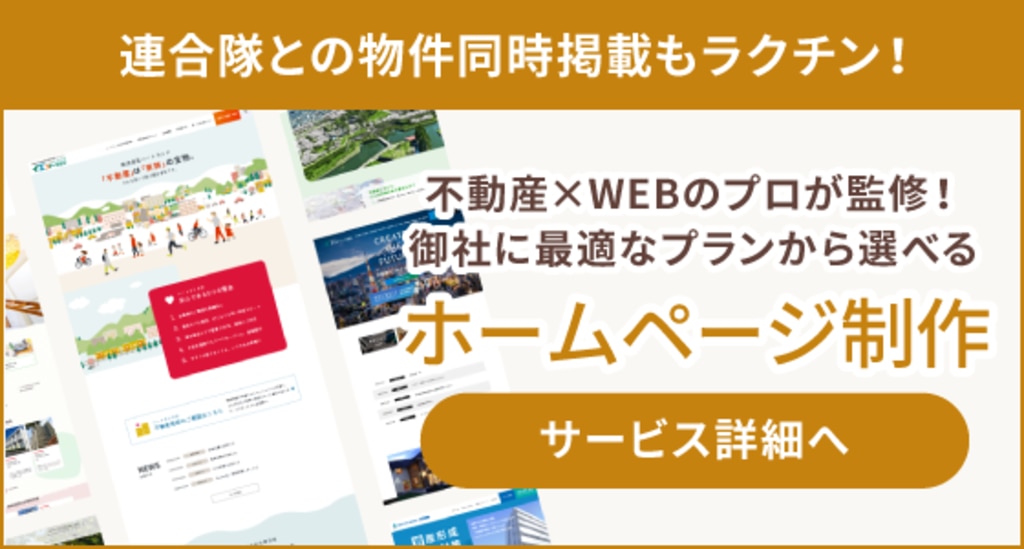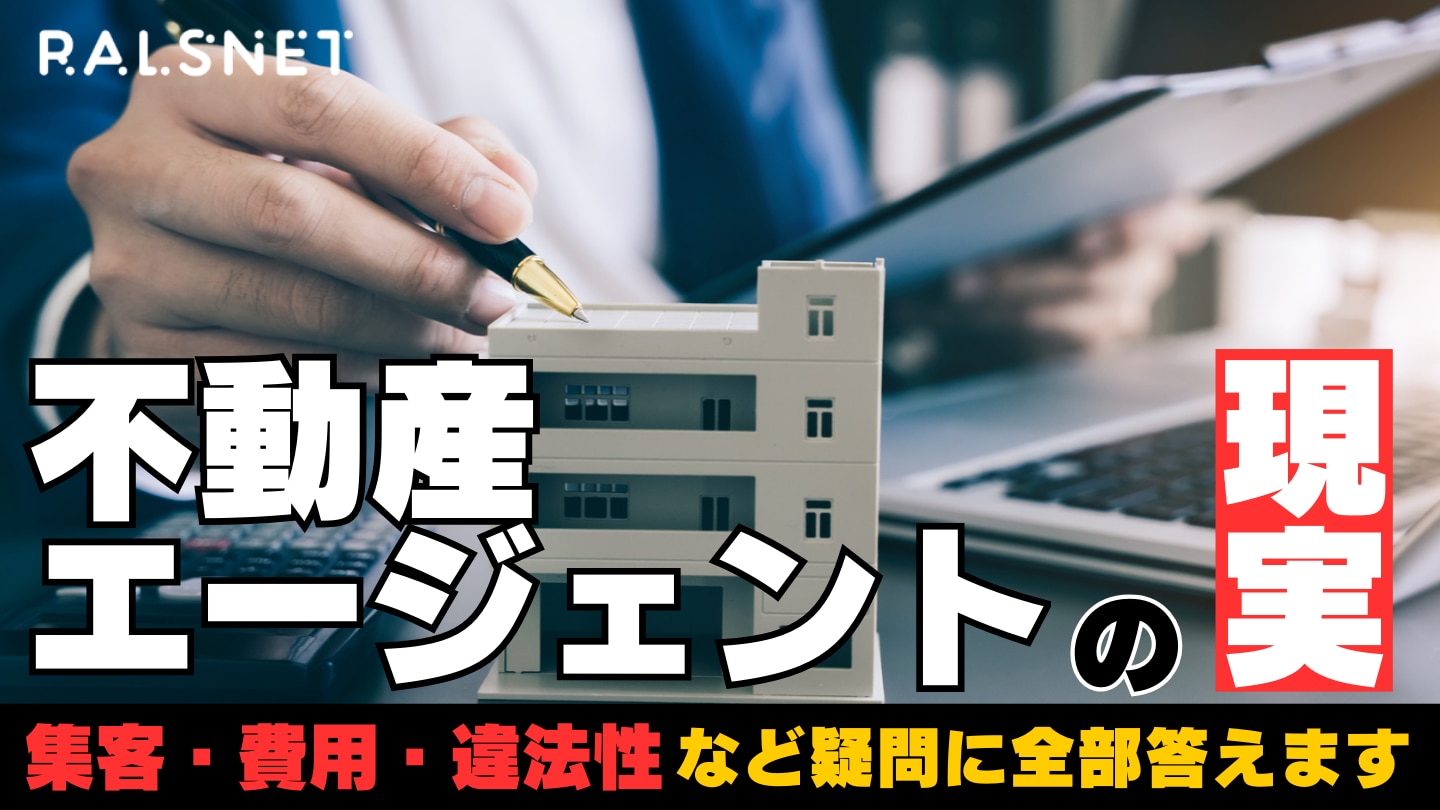
不動産エージェントの現実|集客・費用・違法性など疑問に全部答えます
「不動産エージェントって、ほんとに稼げるの?なんだか怪しい…」
このような不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
SNSや広告では「年収1,000万円」などの華やかな情報が目立つ一方で、法律・契約・集客に関する正しい知識がなければ、うまくいかないケースも少なくありません。だからこそ、不動産エージェントにご興味のある方は、制度や費用、ルールをしっかり理解しておく必要があります。
本記事では、不動産エージェントの仕組みや収入の実態、法律上の注意点までを整理して解説します。自分に合ったスタイルを見極める手助けとなる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
目次[非表示]
- 1.不動産エージェントとは?仕組みと基本をわかりやすく解説
- 2.不動産エージェントの年収の現実|どれくらい稼げるの?
- 3.不動産エージェントは違法なの?法律面の注意点を確認しよう
- 3.1.宅建業法と免許の必要性とは?
- 3.2.無免許営業のリスクと罰則
- 3.3.「専任宅建士」の役割と設置義務について
- 4.不動産エージェントは副業でもできる!未経験でも大丈夫?
- 5.不動産エージェントにかかる費用をチェック
- 6.不動産エージェントの集客方法|現実的なやり方とは?
- 7.不動産エージェントは稼げない?失敗パターンと対策
- 7.1.ありがちな失敗例を3つ紹介
- 7.2.稼げない原因は“仕組み化”不足?
- 7.3.成功する人に共通するマインドと行動
- 8.不動産エージェントは賃貸と売買どちらがいい?
- 9.不動産エージェントの比較|自分に合う会社はどこ?
- 10.不動産会社はエージェント制度を導入すべき?
- 10.1.人材確保・働き方の多様化につながる
- 10.2.地域密着・紹介営業の強化につながる
- 10.3.コスト効率とスピード感を高められる
- 11.まとめ|不動産エージェントの現実を知り、納得して始めよう
- 12.不動産エージェントに関するよくある質問
不動産エージェントとは?仕組みと基本をわかりやすく解説

不動産エージェントとは、売買や賃貸を希望するお客様に対し、物件の紹介や契約のサポートを行う仲介のプロフェッショナルです。一般的な不動産会社の正社員と異なり、エージェントはフリーランスや業務委託として活動することが多く、会社に雇用されているわけではありません。
そのため「出勤義務がない」「完全歩合制(フルコミッション)」など、自由度の高い働き方が特徴です。
エージェントは、宅建業免許を持つ不動産会社と業務委託契約を結び、提携先不動産会社の名義のもとで活動します。顧客の要望に応じて物件を提案し、内見や条件交渉、契約の流れまでをサポートする点は従来の営業職と似ていますが、働き方や報酬モデルが異なります。
不動産エージェントは「不動産会社の社員」ではなく、「成果報酬で動くパートナー」という位置づけに近い存在です。
不動産エージェントの年収の現実|どれくらい稼げるの?

不動産エージェントの売上は青天井ですが、安定収入とは限らないというのが現実です。
ここでは、報酬の仕組みや手数料のルール、売買・賃貸の違い、実際の年収事例まで具体的にわかりやすく解説します。
仲介手数料の計算ルールと上限
不動産エージェントの報酬は、契約が成立した際に発生する仲介手数料の一部(もしくは全額)から得られます。そのため、「手数料の計算ルール」を理解することは大切です。賃貸と売買の手数料の計算ルールは、以下のとおりです。
【売買の仲介手数料(上限)】
上記3段階の手数料を合算した金額に、消費税を加えた金額が法定上限額です。
2024年7月1日施行の法改正により、取引価格が800万円以下の宅地または建物は、次のような特例が設けられました。
【賃貸の仲介手数料(上限)】
売買・賃貸で違う?片手/両手の報酬モデル
エージェントの報酬は、「片手」と「両手」という取引構造によっても変わります。
両手取引は、理論上は報酬も2倍に近づきますが、「囲い込み(他社の紹介客を拒否)」といった問題も起こりやすいため、業界でも注意されています。2025年1月には、こうした行為に対する規制が強化されました。
また、売買では1件あたりの金額が大きいため、1件あたりの仲介手数料も大きくなります。
一方、賃貸は成約スピードが速い分、回転率で勝負する形になります。
実際の年収事例と稼げる人の特徴
不動産エージェント制度を提供するTERASS(テラス)では、「年間報酬3,000万円を超えるトップエージェントも存在する」とHPで紹介されています。また、報酬率は最大90%(通常75%)とされており、会社員の歩合給に比べて高い水準です。
成果を上げているエージェントに共通する特徴としては、以下のような点が挙げられます。
自分の名前で信頼を積み上げられる人
SNSやブログなどでの発信を継続している
紹介や口コミの連鎖を意識して行動している
法律や不動産実務の知識を日々アップデートしている
逆に、営業経験がない、もしくは自己管理が苦手な人にとっては「完全歩合制」はリスクにもなり得ます。
不動産エージェントは違法なの?法律面の注意点を確認しよう

不動産エージェントを副業で始めたい人や、フリーで動きたいと考えている人にとって、宅建業法の仕組みはややこしく感じるかもしれません。
ここでは、免許や契約に関する法律面のポイントを解説します。
宅建業法と免許の必要性とは?
不動産の売買や賃貸を「業として」行う場合は、宅建業の免許が必要です。「業として」という言葉には、以下の3つの要素が含まれます。
継続して(反復して)
営利を目的として
不特定多数を相手に
たとえば、知り合い1人にだけ物件を紹介した場合は免許の対象外となることもありますが、何人ものお客様に継続的に物件を紹介して手数料を得る場合は、免許が必要になります。
【宅建業免許の基本情報】
無免許営業のリスクと罰則
もし免許を持たずに宅建業を行った場合は、「無免許営業」として法律違反となります。
違反には、以下のような罰則が科されます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(第79条)
悪質な場合は懲役と罰金の併科もあり得ます
また、免許を持つ業者の名前だけ借りて営業する行為(いわゆる「名義貸し」)も禁止されています。名義貸しは「宅建業法第13条」で明確に禁じられており、名義を貸した側も処分の対象です。
エージェントとして合法的に活動するためには、「免許業者のもとで業務委託契約を結ぶ」という形が一般的です。
「専任宅建士」の役割と設置義務について
宅建業免許を取得した会社には、「専任の宅地建物取引士(宅建士)」を配置する義務もあります。
【専任宅建士のルール】
従業者の5人に1人以上の割合で、専任の宅建士を配置
各事務所に1名以上の「専任」が必要
専任とは、常勤かつ専属でその会社に勤務していること
たとえば、10名の営業スタッフがいる場合、最低でも2名の宅建士が必要になります。
専任宅建士は、重要事項の説明や契約書への記名を担当するなど、取引の中核的な役割を担います。
不動産エージェントは副業でもできる!未経験でも大丈夫?

不動産業界には法律や専門知識があるため、気軽に不動産エージェントの副業を始めてよいものなのか不安を感じる方も多いはずです。
ここでは、副業として取り組む際の注意点や、未経験でも安心してスタートできるサポート体制について詳しくご紹介します。
副業で始めたい人が知っておくべきこと
不動産エージェントは、業務委託契約を前提とした働き方であることが多いため、副業としても取り組みやすいスタイルです。ただし、副業として行う場合には、以下の点に気をつける必要があります。
就業規則の確認
勤務先の会社が副業を許可しているか、まずは規則を確認しましょう。
業種によっては競業禁止のルールがあることもあります。労働時間の通算
副業であっても、労働基準法では労働時間の合計が
上限(1日8時間・週40時間)を超えると問題になる可能性があります。健康管理と本業への影響
睡眠不足や本業への支障が出ないよう、自分自身の体調管理も重要です。
また、会社に内緒で始める行為はリスクが高いため、控えましょう。もし始める場合は、事前に相談・申告をしておくのが安心です。
会社員の副業ルールと就業規則の注意点
副業をする上では、厚生労働省が発行している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が参考になります。ガイドラインでは、以下のような基本的な考え方が示されています。
本業の勤務時間中に副業をしてはいけない
副業先での労働時間も本業と通算して管理される
秘密保持義務・信用失墜行為は禁止
健康管理・過労防止の責任は本人にもある
とくに不動産業の場合は、お客様とのやりとりや契約締結など、責任が伴う業務が多いため、「短時間だから大丈夫」という考えではなく、自己責任での時間管理とルール遵守が重要になります。
未経験から始めるなら、どのようなサポートがある?
不動産の知識がなくても、制度や仕組みが整っているエージェント制度を選べば、安心してスタートできます。以下のようなサポートが用意されている会社も増えています。
たとえば、TERASSやSHERPA、RE/MAXなどでは、エージェント未経験者向けの研修プログラムを用意しています。そのため、必要な知識を段階的に学べるようになっています。
「宅建士の資格がなくても大丈夫?」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、免許業者の下で活動する場合は、宅建士でなくても業務は可能です。ただし、重要事項の説明や契約締結には宅建士の補助が必要となるため、将来的には資格取得を視野に入れておくのもよいでしょう。
不動産エージェントにかかる費用をチェック

不動産エージェントとして活動を始める際、多くの方が気になるのが「費用」の問題です。
ここでは、必要な費用と内訳、代表的なエージェント制度の比較、そして損をしないための考え方まで整理して解説します。
月額費用や初期費用の相場はどれくらい?
不動産エージェントは「フルコミッション型(完全歩合制)」で活動するのが一般的ですが、その分、活動に必要な月額費用や初期費用が発生するケースもあります。
【一般的な費用相場(2025年時点の例)】
上記はRE/MAXやSHERPAの一部オフィス事例です。拠点や時期により異なるため、詳細は必ず確認しましょう。
収支シミュレーションで「赤字にならない」かを確認しよう
どれだけ報酬率が高くても、活動のコストが報酬を上回ってしまっては意味がありません。
そのため、活動前に簡単な「損益シミュレーション」をしておくことをおすすめします。
【賃貸エージェント活動の簡易シミュレーション】
月額費用:2万円(システム利用料+通信+交通費など)
1件あたりの成約報酬:賃料8万円×50%(報酬配分)=4万円
月の目標件数:2件
→月間報酬:4万円×2件=8万円
→収支:8万円−2万円(固定費)=実質利益6万円
つまり、1件の成約で黒字化できる計算です。売買なら単価が高くなる分、1件で月収20万円を超えるケースもありますが、その分、成約までの期間は長くなる傾向があります。
不動産エージェントの集客方法|現実的なやり方とは?

エージェントとして活動する上で、「どうやってお客様と出会うのか」は最大の課題です。
ここでは、現在の不動産業界で実際に使われている集客の手段を、エージェント目線でわかりやすくご紹介します。
地域特化ポータルサイトの活用方法
不動産エージェントにとって、「地域密着の検索流入」は非常に重要です。全国規模のポータルサイトでは競合が多く、費用も高額になりがちですが、地域特化型ポータルサイトや自社メディア(ブログ型サイト)を活用することで、効率的な集客が見込めます。
たとえば、北海道限定・長崎県限定といった特化型ポータルに掲載することで、以下のような効果が期待できます。
地元で物件を探している顧客にピンポイントで届く
大手よりも顔の見える営業ができるため、信頼を得やすい
独立型エージェントでも地域の専門家として認知されやすい
また、Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)とあわせて登録しましょう。住所や連絡先、口コミなどを充実させておくと、検索結果の上位表示にもつながります。実際、「地域名+不動産」や「地域名+賃貸」の検索で地図情報が表示されることも多く、店舗を持たないエージェントでも信頼感を演出できます。
SNS(InstagramやX)での信頼獲得術
最近では、SNSを活用して自分自身の営業スタイルや人柄を発信するエージェントも増えています。とくにInstagramやX(旧Twitter)は、写真や実例を使った投稿との相性がよく、短期間での認知拡大にも向いています。
【SNS活用のポイント】
ストーリーズやリールで物件紹介やお客様の声を発信
日常の出来事や家探しのコツを投稿して親近感を演出
プロフィール欄に連絡先や相談用LINEを設置する
SNSでの発信を積み重ねることで、「この人に相談してみようかな」と思ってもらえる機会が増えていきます。
ただし、SNS上で物件の募集情報を掲載する際には、広告表示に関するルール(表示規約・おとり広告ガイドライン)にも注意が必要です。
【表示に関する注意点】
すでに成約済みの物件を掲載しない(=おとり広告に該当)
必要な条件(賃料・敷金・面積など)は明示する
写真やコメントは実物を正確に反映した内容にする
広告表示に関するルールは、「不動産公正取引協議会」のガイドラインに明記されており、違反すると行政指導の対象となる可能性もあります。
紹介・口コミを生むにはどうすればいい?
一度でも契約につながると、そこから紹介の連鎖が始まることがあります。とくにエージェント型の営業スタイルでは、信頼関係をベースとした紹介営業が効果的です。
紹介や口コミを生みやすくするには、次のような工夫が有効です。
契約後のアフターフォローを丁寧に行う
「お友達を紹介してもらえると嬉しいです」と一言添える
お礼状や感謝のメッセージを手書きで送る
紹介特典(ギフトカードや割引など)を用意する(※要法令確認)
また、Googleビジネスプロフィール上で口コミをもらえるよう依頼することも大切です。リアルな体験談が載ることで、信頼性と安心感が大きく高まります。
不動産エージェントは稼げない?失敗パターンと対策

SNSや広告で「年収1000万円」などの華やかな情報を見る一方で、「実際にやってみたけど稼げなかった」という声もあるのが不動産エージェントの現実です。
ここでは、なぜ稼げないケースがあるのか、どのような失敗パターンがあるのかを整理した上で、成功するために大切な考え方をわかりやすく解説します。
ありがちな失敗例を3つ紹介
不動産エージェントとして活動を始めた方がよく陥りがちな失敗を3つに分けて紹介します。
1.集客を甘く見ていた
「ポータルサイトに登録すれば勝手に反響がくる」と思っていたが、まったく問合せが来ず、収入ゼロで終了するケースがあります。
2.情報やスキルの学習を怠った
不動産業は法律・税金・建築・ローンなど複合的な知識が求められます。学ばずに自己流で動いた結果、お客様に信頼されず、契約につながらないことがあります。
3.継続できなかった
完全歩合制の場合、最初の数か月は無収入になることもあります。成果が出るまでの時間や地道な活動に耐えられず、途中であきらめてしまうケースも多いです。
稼げない原因は“仕組み化”不足?
営業や人脈に自信がある人でも、不動産エージェントとして結果が出ないのは、「再現性のある仕組み」がないからかもしれません。
【よくある“仕組み化不足”の例】
上記の状況では、たとえ営業センスがあっても「毎回ゼロから努力し直す」ことになり、結果として効率が悪くなってしまいます。
成功する人に共通するマインドと行動
安定して成果を出している不動産エージェントには共通点があります。特別なスキルがあるというよりも、地道で継続的な行動と素直な学びの姿勢を持っている方が多いです。
【成功する人の特徴】
毎日のスケジュールを自分で組み立て、実行できている
顧客対応をすべて「次につなげる」意識で行っている
業界の変化(法改正・ITツール)を積極的に学び取り入れている
自分をブランドとして育てていく意識がある(SNS、口コミ対応など)
短期成果に一喜一憂せず、半年〜1年先を見て動いている
「稼げるかどうか」は一発勝負ではなく、“仕組み化×継続”という地味な積み重ねによってつくられていきます。
不動産エージェントは賃貸と売買どちらがいい?

不動産エージェントの「賃貸・売買」には、それぞれメリットとデメリットがあり、営業スタイルやライフスタイルによって向き・不向きも変わります。
ここでは、賃貸と売買それぞれの特徴を整理しながら、自分に合った選び方を見つけるヒントをご紹介します。
賃貸エージェントのメリット・デメリット
賃貸をメインに扱うエージェントは、短期的な成約件数の多さが最大の特徴です。比較的ライトな決断で契約に至るため、初心者や副業スタートにも向いています。
【賃貸エージェントの特徴】
【メリット】
比較的すぐに成果が出やすい
案件の回転率が高く、経験値を積みやすい
顧客と密に接することで紹介につながりやすい
【デメリット】
単価が小さいため、成約数を追わないと収入が増えにくい
同業他社との競争が激しいエリアも多い
繁忙期(春)と閑散期の差が大きい
「とりあえず1件契約してみたい」「不動産業に慣れたい」という方には、賃貸から始めるのもよい選択肢です。
売買エージェントのメリット・デメリット
売買を扱うエージェントは、高額な報酬が魅力です。1件の成約で数十万円〜百万円以上の手数料が発生することも珍しくありません。
【売買エージェントの特徴】
【メリット】
1件の成約報酬が高く、効率よく収入を得られる
顧客との信頼関係が深まり、紹介につながりやすい
仕組み化・リピート営業で「安定収入型」も目指せる
【デメリット】
成約までのリードタイムが長く、短期的な成果が出にくい
専門知識や交渉力、法的理解が必要
顧客の意思決定が慎重で、途中で流れるリスクもある
「ある程度まとまった時間が取れる」「専門的な提案が得意」「営業経験がある」という方には、売買エージェントが向いています。
選ぶときの判断ポイントと注意点
賃貸と売買、どちらを選ぶべきかを判断するためのチェックポイントを見てみましょう。
【判断ポイントの一例】
また、「最初は賃貸で経験を積み、のちに売買へ移行する」というキャリア設計をする方も多くいます。自分の生活スタイルや得意分野にあわせて、柔軟に選択できるのも不動産エージェントの魅力です。
不動産エージェントの比較|自分に合う会社はどこ?

近年では、フルコミッション型のエージェント制度を導入している会社も増えており、それぞれに報酬モデルやサポート体制、契約内容に違いがあります。
ここでは、主要な5社を比較しながら、自分に合う会社を選ぶための視点を整理していきましょう。
不動産エージェントの報酬モデルを比較
以下は、2025年時点で公表されている主要な不動産エージェント制度の比較です。報酬率や費用、特徴を一覧にまとめました。
※報酬率や費用は、拠点や契約条件・時期により変更される場合があります。
※正式な条件や最新の情報は、各社の公式サイトや説明会などで必ずご確認ください。
直営型とフランチャイズ型の違いとは?
不動産エージェント制度には、会社がすべてを管理する「直営型」と、一定のルールのもとに独立運営する「フランチャイズ型」の2種類があります。それぞれに特徴があるため、選ぶ際のポイントを知っておきましょう。
【直営型の特徴】
統一されたサポートやルールがある
組織としての一体感が強い
報酬や費用も画一的な場合が多い
【フランチャイズ型の特徴】
加盟店ごとに報酬率や費用が異なる
運営スタイルの自由度が高い
サポート体制に差があるため、加盟店選びが重要
たとえば、RE/MAXはフランチャイズモデルを採用しており、「どのオフィスに所属するか」でサポートの質や費用面が大きく変わることがあります。
「おすすめランキング」に惑わされない選び方
インターネットで検索すると、「不動産エージェントおすすめランキング」や「年収〇〇万円稼げる」などの情報が多く見つかりますが、鵜呑みにするのは危険です。
大切なのは、自分の働き方や目的に合っているかどうかです。
【選ぶときのチェックポイント】
「稼げるかどうか」は制度そのものだけでなく、自分自身が制度にフィットしているかどうかによって大きく変わります。
不動産会社はエージェント制度を導入すべき?

人材の確保や業務効率の見直しといった背景から、エージェント制度を導入する企業も少なくありません。
ここでは、不動産会社がエージェント制度を導入することで得られる効果や、組織活用のポイントについて詳しく解説します。
人材確保・働き方の多様化につながる
多くの業界と同じく、不動産業界でも人材不足は深刻です。とくに中小規模の不動産会社では「求人を出してもなかなか応募が来ない」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった悩みを抱えているケースが少なくありません。
そこで注目されているのが、業務委託型のエージェント制度です。
【導入による効果の一例】
子育て中・介護中などフルタイム勤務が難しい人材も活用できる
副業や複業を希望する優秀な人材が参加しやすくなる
ノルマや出勤に縛られないことで、モチベーションが維持されやすい
エージェント制度は、時間や場所に縛られない働き方を実現できる点が魅力です。とくに最近は、SNSやオンライン接客を活用したスタイルが一般化してきたこともあり、会社としても従来のような「常駐・店番型」の営業スタイルにこだわる必要がなくなりつつあります。
地域密着・紹介営業の強化につながる
エージェント制度を導入すると、「個人の人間関係や信頼を軸にした営業スタイル」がより強くなります。
たとえば以下のようなケースがあります。
地域に根ざしたエージェントが、知人や家族から紹介を受ける
地元のカフェやコミュニティに顔を出すことで自然に相談が増える
地域情報に詳しいからこそ、希望に合った提案ができる
エージェント1人ひとりの人脈や経験を「営業資産」として活用することで、会社全体として紹介営業の比率が高まりやすくなります。
コスト効率とスピード感を高められる
エージェント制度のメリットは、人件費や店舗費用の削減にも効果がある点です。
正社員をフルタイムで雇う場合、毎月の人件費に加えて、社会保険料や福利厚生費、交通費などさまざまなコストがかかります。
一方、エージェント制度であれば、完全歩合制・業務委託であるため、成約ベースの報酬のみで済むという大きなメリットがあります。
コスト面の違いは、以下のとおりです。
また、従来のような「会議をしてから動く」ではなく、エージェントが現場判断で即行動できる体制が整うため、顧客満足度の向上にもつながります。
不動産会社がエージェント制度を導入することで、人材確保・地域密着・コスト削減といった複数のメリットを得られます。もちろん制度設計や運用の工夫は必要ですが、時代に合った営業体制を模索している企業にとっては、非常に有効な選択肢となるでしょう。
まとめ|不動産エージェントの現実を知り、納得して始めよう

今回は、不動産エージェントの仕組みや収入の実態、法律面の注意点や現実的な集客方法について解説しました。
自由な働き方や高収入が期待される一方で、知識不足や集客の工夫がないままでは成果につながらないという現実があります。とくに重要なのは、安定的な成果を出すための仕組み化と、信頼を積み重ねる姿勢です。
また現代の不動産エージェントにとって、効率的かつ再現性のある集客ルートを持つことは不可欠です。地域特化型ポータルの活用は、そうした課題に応える有効な手段といえます。
なかでも「不動産連合隊」は、都道府県単位の構造で競合が少なく、地元ユーザーとの接点を効率よく生み出せる点が大きな強みです。さらに、自社サイトへの無料送客や専門ポータルへの同時掲載機能など、独立型エージェントでも扱いやすい設計となっています。
これから不動産エージェントとして成果を高めたい方や、集客基盤を整えたい不動産会社様は、ぜひ一度「不動産連合隊」へお問い合わせください。
不動産エージェントに関するよくある質問
不動産エージェントって怪しい副業でしょうか?
エージェント制度自体は合法的な働き方のひとつであり、怪しい副業ではありません。国土交通省の宅建業法に則って、正しく活動している会社も多数あります。
注意すべきなのは、制度の中身をよく理解せずに始めてしまうことです。仕組みや契約内容、サポート体制をしっかり確認した上で、自分に合う制度を選べば問題ありません。
不動産エージェントでの副業は、会社にバレないでしょうか?
副業としてエージェント活動を行うこと自体は可能ですが、勤務先の就業規則によっては制限されている場合があります。とくに「競業禁止」や「副業申請が必要」と定めている企業もあるため、必ず事前に社内規定を確認しましょう。
また、税務上や社会保険の手続きなどから完全にバレないようにするのは現実的ではありません。会社に隠れて行動するよりも、きちんとルールを守った上で堂々と活動する方が、精神的にも安心です。
不動産エージェントは違法になるリスクはありますか?
エージェント自体は合法の働き方ですが、無免許営業や名義貸しは重い罰則があります。
また、SNSやポータルでの募集広告は表示規約・おとり広告禁止に従う必要があります。表示義務(賃料・敷金・面積・取引態様等)や実在性の確保は必須です。迷ったら所属先の法務・業法担当に事前に相談しましょう。