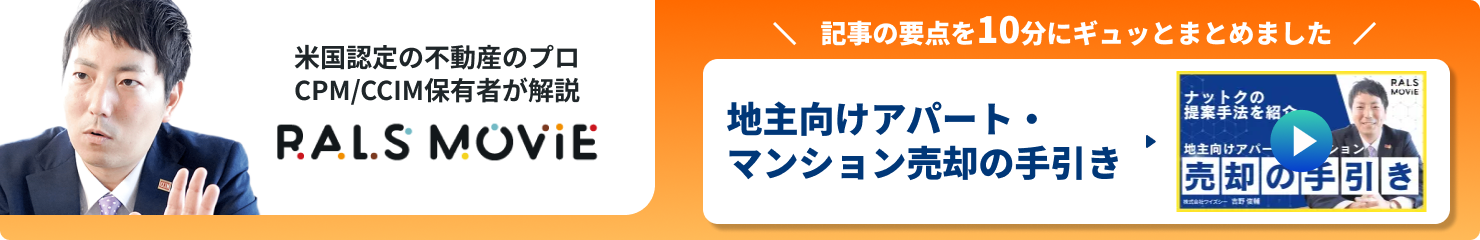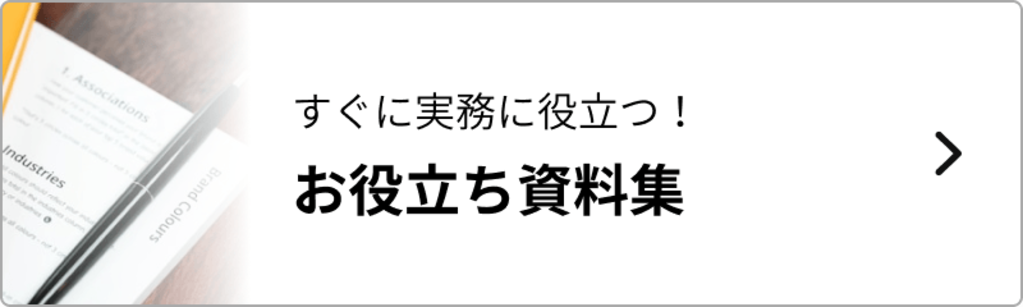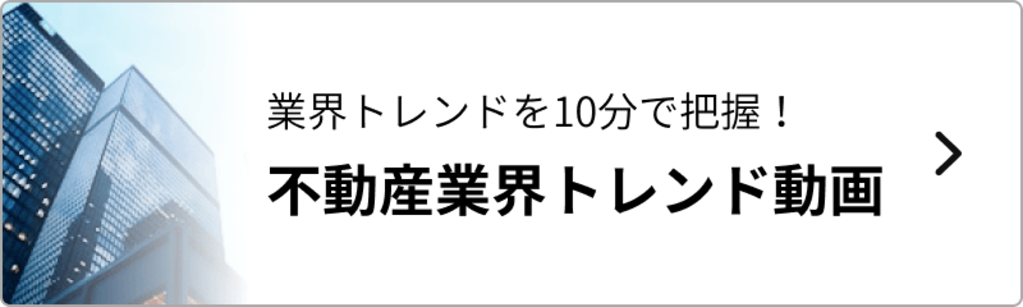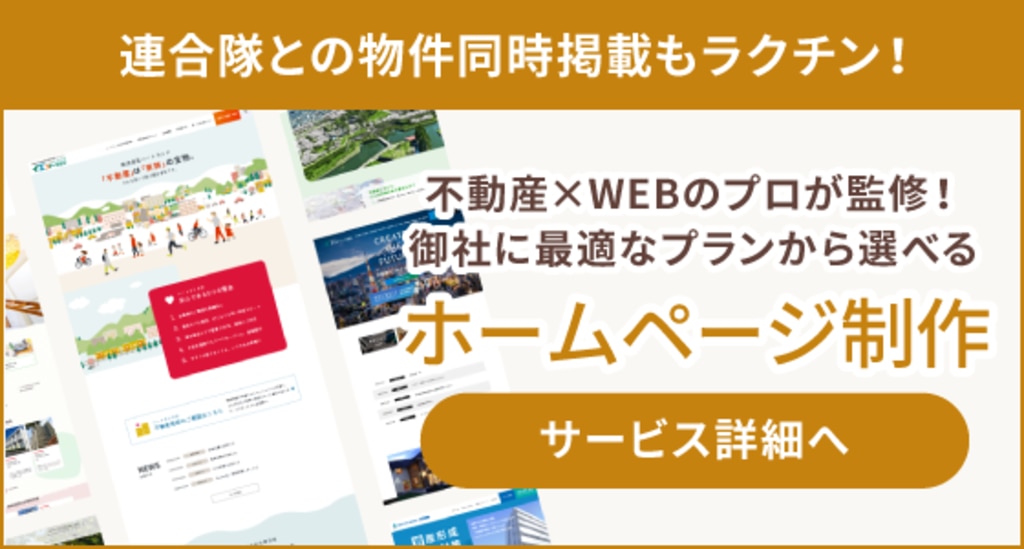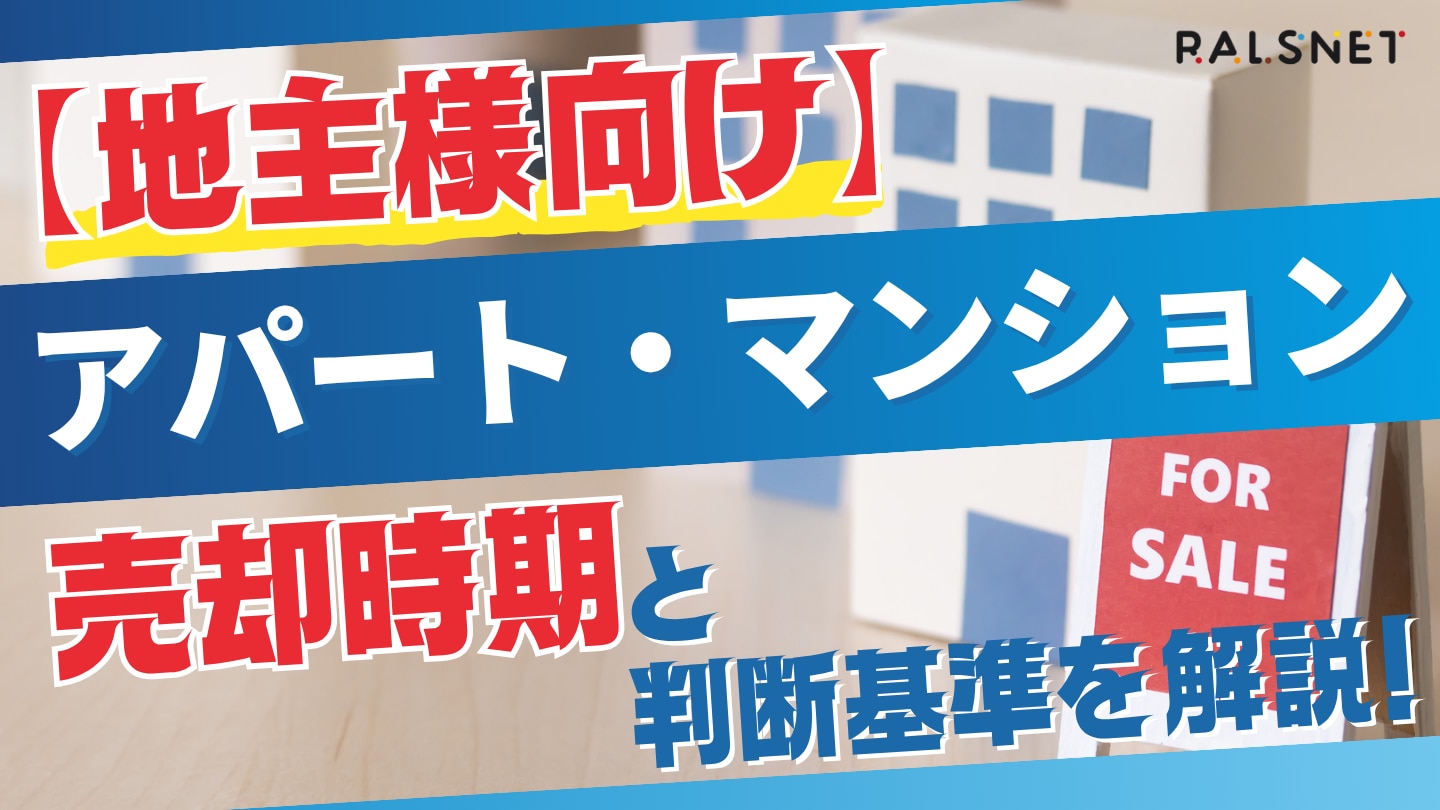
【地主様向け】アパート・マンションの売却時期と判断基準を解説!
長年所有してきたアパートやマンションの売却時期を判断するのは、地主様にとって重要です。現在の不動産市場や賃貸経営を取り巻く環境の変化を考慮すると、売却時期について考える時期に来ているでしょう。本記事では、地主様が後悔のない売却ができるよう、現在の不動産市場から建物の寿命や修繕コスト、物件価格の算出方法などを解説します。地主様にアパートやマンションの売却を提案する際に、参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.現在の不動産市場と地主様が抱える悩み
- 2.売却時期の提案前に知っておきたい建物の寿命
- 3.避けて通れない修繕費|周期と概算コスト
- 3.1.修繕工事の項目とタイミング
- 3.2.長期修繕計画で見る概算コスト
- 3.3.所有目的に合わせた修繕の考え方
- 4.物件の「本当の価値」を知る3つの価格算出方法
- 4.1.収益還元価格
- 4.2.積算価格(担保評価)
- 4.3.土地の実勢価格
- 4.4.「最も高い」価格が売却価格の目安
- 5.地主様の売却判断を促す「具体的な根拠と判断材料」の提示
- 5.1.今後の大きな支出発生時期と費用想定
- 5.2.事業承継の予定有無
- 5.3.総合的な判断の重要性
- 6.まとめ|地主様が売却時期で後悔しないための選択を提案しよう!
現在の不動産市場と地主様が抱える悩み

現在の不動産市場は、地主様が所有物件について深く検討すべき転換期を迎えています。まずは、現在の不動産市場と地主様が抱える悩みを把握しておきましょう。
値上がり傾向にある不動産市場
現在は、不動産の売却に適した時期といえます。とくに、分譲マンションの価格上昇が市場全体の相場を押し上げており、不動産価格が「上がっている」と言われる主な理由です。
しかし、収益物件は利回りによって価格が決まる「利回り商品」であるため、価格には限界値があります。そのため、いずれは横ばいになっていくでしょう。さらに、今後予測される金利上昇や修繕費の高騰を考慮すると、築年数が新しいほど市場での売却価格は高くなります。
地主様特有の長期保有志向と事業承継の悩み
先代から賃貸経営を事業承継してきた地主様にとっては、「不動産を売らずに長く所有し続ける」あるいは「築年数が古くなったら建て替えを行う」という考え方が一般的です。そのため、「売却する」という判断は非常に重い決断となります。
しかし、ご自身の年齢が上がっていくにつれて、相続や事業承継の問題も避けては通れません。最近では、「保有すべきか、売却すべきか」の判断材料を求めるご相談が増えており、多くの地主様が悩みを抱えている現状があります。
売却時期の提案前に知っておきたい建物の寿命

建物には「物理的寿命」と「経済的寿命」という、2つの寿命があります。
- 物理的寿命:建物が物理的に使用できる期間
- 経済的寿命:経済的観点から見た価値が失われるまでの期間
たとえば、RC造(鉄筋コンクリート造)の建物は、物理的には100年以上持つ(物理的寿命)と言われています。実際に、1920年代に建てられた戦前の技術による鉄筋コンクリートマンション(同潤会上野下アパート)が、約84年も存続しました。現在の技術で建てられた鉄筋コンクリートマンションであれば、100年以上持つことは十分に考えられるでしょう。
一方で、「30年で1世代」という考え方もあり、2世代で60年が経過すると時代背景が大きく変わります。社会情勢やライフスタイルの変化により、物理的に存続可能であっても、実際には60年程度で建て替えられる(経済的寿命)ケースが多くなります。この「経済的寿命」を理解することが、適切な売却時期を判断する上で重要です。
参考:建物の寿命と耐用年数
:文化探訪
避けて通れない修繕費|周期と概算コスト
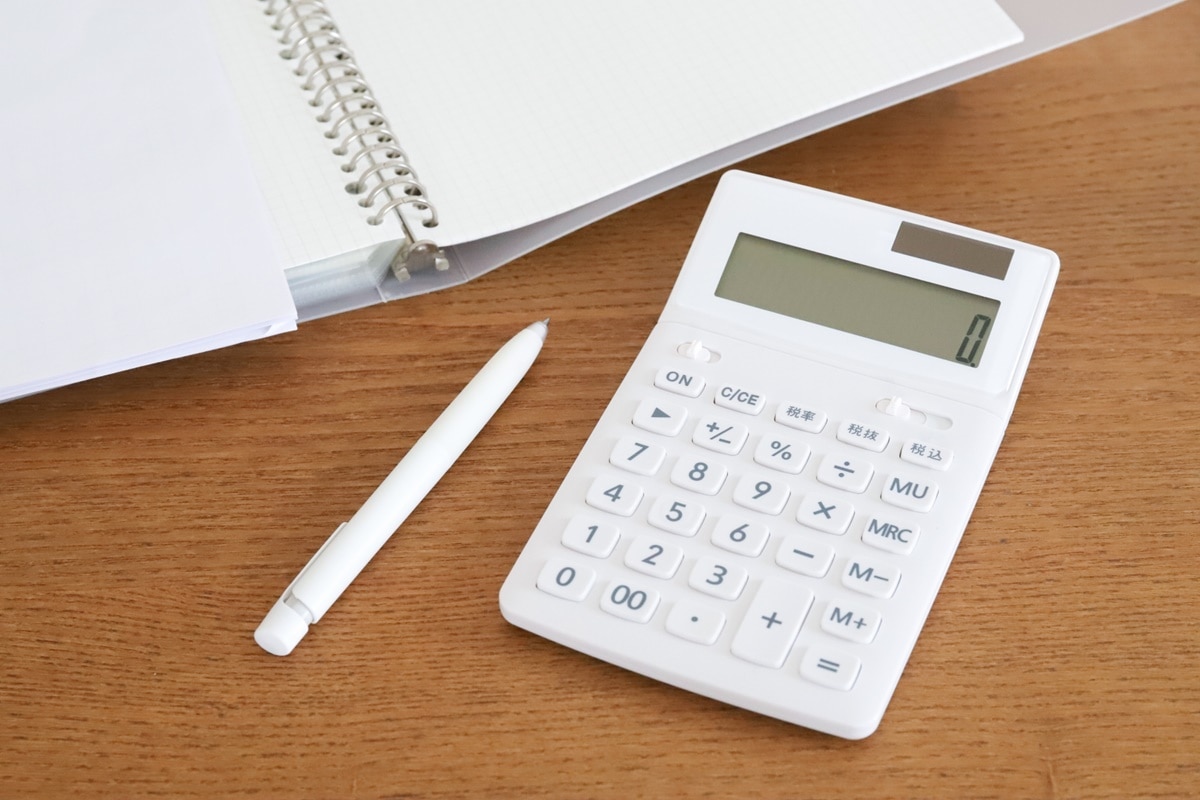
建物を長く維持するためには、避けて通れないのが修繕費です。修繕費だけではなく、周期を把握することも収支計画を立てる上で非常に重要です。
修繕工事の項目とタイミング
建物の経済的寿命が60年であることを考えれば、時期を見て必要な修繕を行う必要があります。賃貸物件における代表的な修繕工事とタイミングは、以下のとおりです。
- 大規模修繕工事:外壁塗装や防水工事など(15~20年に1回)
- 鉄部塗装工事:手すりや階段などの鉄部のサビ防止(大規模修繕工事の合間)
- 設備更新:給水ポンプや給排水管の更新(5~10年に1回)
- 室内工事:リノベーションや設備の入れ替えなど(退去時)
安全性の確保を最優先に考えれば、これらの修繕は必要不可欠だと言えます。
長期修繕計画で見る概算コスト
長期修繕計画は、将来かかる修繕コストや修繕リスクを説明するための重要な資料です。とくに、規模の大きいRC造のマンションでは、大規模修繕工事に1,000万円単位のお金がかかることも珍しくありません。放置すれば建物が朽ち果ててしまうため、維持のために投資が必要となる「保有リスク」と言えるでしょう。
大規模修繕工事の費用を簡易的に計算する方法として、㎡単価10,000円~20,000円に謄本上の延床面積を掛けるという方法があります。大規模修繕を行う前に費用の目安として、把握することが可能です。ただし、あくまで簡易的な計算方法なので、複数の会社へ相見積もりを行いましょう。
所有目的に合わせた修繕の考え方
賃貸物件はオーナー様がご自身で住むわけではないため、必ずしも周期通りに修繕を行う必要はありません。オーナー様の所有目的に合わせて、必要な修繕を行うことが重要です。
たとえば、すぐに売却する予定があるにもかかわらず大規模修繕工事を行うのは、現実的ではないと考える方も多いでしょう。同様に、建て替えが想定されている物件で大規模修繕工事や給排水管の更新を行うことも、費用対効果の面で疑問が残ります。
築年数が古い物件の場合は、修繕資金を備えるよりも売却や立ち退きの準備、建て替え費用の準備を検討する段階にあると考えるべきでしょう。
賃貸経営の収支予測と修繕リスクの重要性

賃貸経営の継続を判断する上で、今後の収支予測は必須です。長期的な視点で収入と支出のバランスを見極めなければ、長期的な賃貸経営は難しいでしょう。たとえば、約1億円ほどの収益が見込める規模の一棟マンションでは、長期的に見た修繕リスク(大規模修繕工事を含む)は数千万円になることもあるでしょう。
一方、収益不動産の価格は、基本的に「年間家賃収入 ÷ 相場の利回り」で決まります。築50~60年のような古い物件の場合、利回り12%という相場も珍しくありません。利回りを考慮した価格で評価することも重要です。
このように、収支予測や修繕リスクなどを把握すれば、賃貸経営の継続性や売却を判断する材料になるでしょう。
物件の「本当の価値」を知る3つの価格算出方法

アパートやマンションなどの1棟収益物件の価格を決定する際には、複数の評価方法を組み合わせて「本当の価値」を見極めることが重要です。主に3つの価格算出方法が存在します。
収益還元価格
収益還元価格は、「年間家賃収入 ÷ 相場の利回り」で算出する方法です。投資家が物件を評価する際に重視する指標であり、収益物件の基本的な価値を判断できます。
積算価格(担保評価)
金融機関が融資を出す際の判断材料になるのが、「積算価格(担保評価)」です。積算価格は「土地の評価額 + 建物の評価額」によって算出できます。
- 土地の評価額:路線価 × 土地面積(㎡)
- 建物の評価額:再調達価格 × 延床面積(㎡) × (残存耐用年数 ÷ 法定耐用年数)
※再調達価格:1平方メートルあたりの建築費(目安)
※残存耐用年数:「法定耐用年数 - 築年数」
※法定耐用年数:RC造47年・木造22年など
ただし、築年数が古い場合は、積算価格がゼロと判断される場合があることを覚えておきましょう。築50年以上のRC造の場合は、建物の法定耐用年数(47年)を超過しているため、積算評価上の価値がゼロになってしまう可能性があります。
土地の実勢価格
土地の実勢価格とは、市場で実際に取引される価格です。別の算出方法として積算価格があるものの、実際の市場価格より安く評価される傾向があります。とくに、需要の高い都心部では価格差が顕著になります。そのため、土地の価値を正確に把握するためには、以下の情報を詳しく分析することが重要です。
- レインズやポータルサイトで売りに出されている事例
- 国土交通省が発表している取引価格や公示価格など
これらの情報を分析して、用途地域や建ぺい率、容積率が類似する物件の実勢価格を割り出します。その単価に調べたい土地の面積を掛けたのが、適正な実勢価格です。もし、建物に価値が残っていれば、その分を加味した価格になります。
「最も高い」価格が売却価格の目安
1棟アパート・マンションの売却価格を決定する際には、「収益還元価格」「積算価格」「土地の実勢価格」の3つの価格を算出し、その中で最も高い価格を選ぶのが基本的な考え方となります。
たとえ築年数が古くても家賃収入があったり、土地の価格が高かったりすることで、投資家から人気を集める場合もあるでしょう。そのため、3つの価格から物件の価値を多角的に評価し、適切な売却価格を導き出すことが重要です。
地主様の売却判断を促す「具体的な根拠と判断材料」の提示

地主様の売却判断は、投資家の方と比べて長い年月をかけて事業承継されてきた経緯があるため、意思決定に時間がかかる傾向にあります。売却をスムーズに進めるためには、明確な根拠と具体的な判断材料を提示しましょう。
今後の大きな支出発生時期と費用想定
建物の経済的寿命が60年という目安、修繕の周期や概算でかかる費用を具体的に伝えることが重要です。とくに、今後発生する大きな支出の時期と費用を想定して提示することで、地主様は将来的な収支への影響を具体的にイメージできます。賃貸経営を継ぐ予定がないのであれば、このような大きな支出が発生する前に、早い段階での売却を検討するよう促せるでしょう。
事業承継の予定有無
現在の家賃収入や事業承継の予定有無など、地主様ご自身の状況や将来設計を加味した上で、売却の必要性を検討していただくことが重要です。相続や事業承継を視野に入れ、売却判断を促す必要があるでしょう。
総合的な判断の重要性
不動産価格や修繕費、金利が上昇している今、「賃貸経営を継続するか・建物を保有し続けるか・売却時期をどうするか」を真剣に検討する時期が来ています。売却を提案する際は、こうした市場の状況と根拠を丁寧に説明し、最終的な判断はオーナー様に委ねる姿勢で臨むことが大切です。
まとめ|地主様が売却時期で後悔しないための選択を提案しよう!

地主様のアパート・マンション売却は、単なる物件の売買以上の意味を持つことが少なくありません。長年の歴史や思いが詰まった大切な資産だからこそ、後悔のない選択をしていただくためのサポートが求められます。
そのためには、現在の不動産市況を正確に伝えることが大切です。また、建物の経済的寿命や今後の修繕周期と概算費用、今後の収支見込み、3つの価格(収益還元価格・積算価格・土地の実勢価格)を考慮した査定価格の提示も忘れてはいけません。
これらの明確な根拠と判断材料を提供することで、地主様はスムーズに、そして納得して売却の意思決定ができるようになるでしょう。