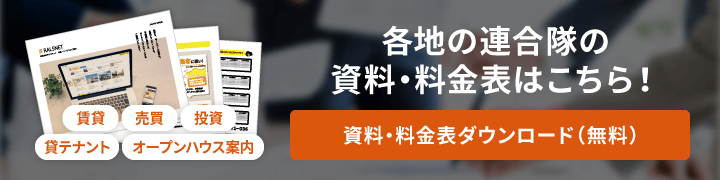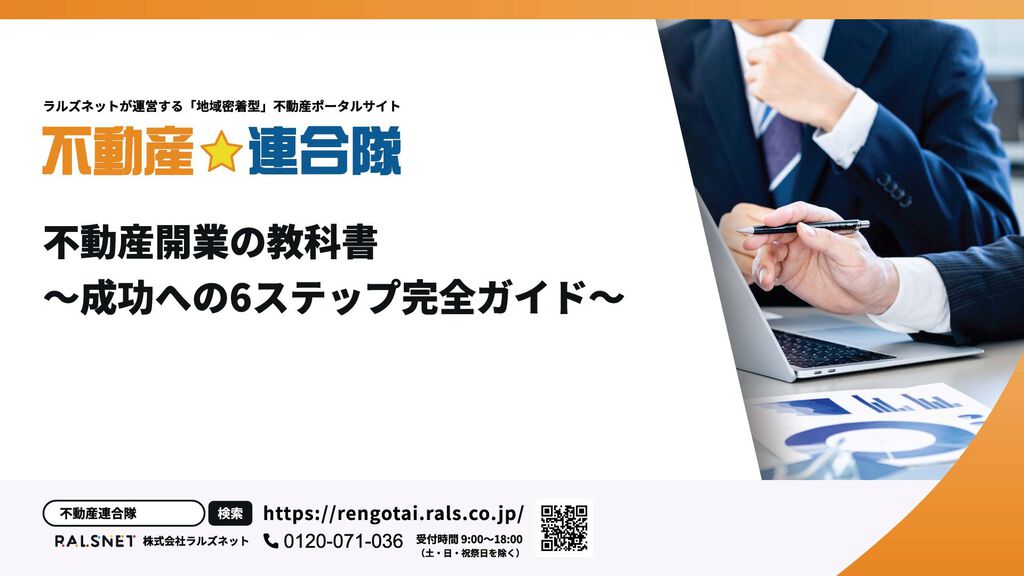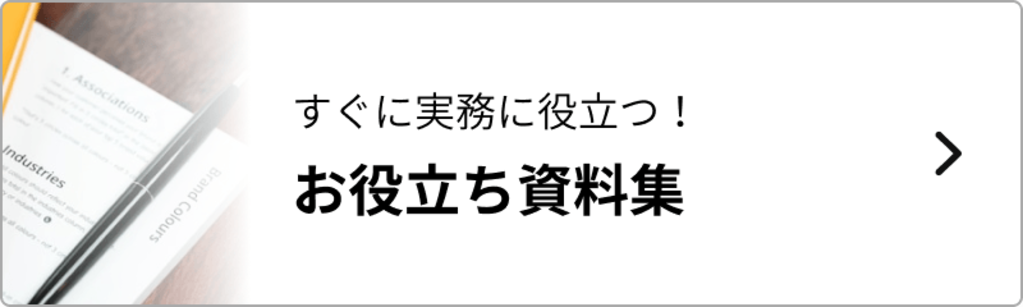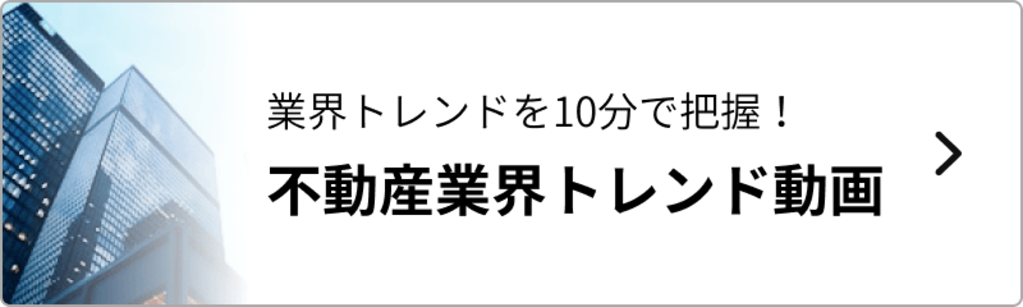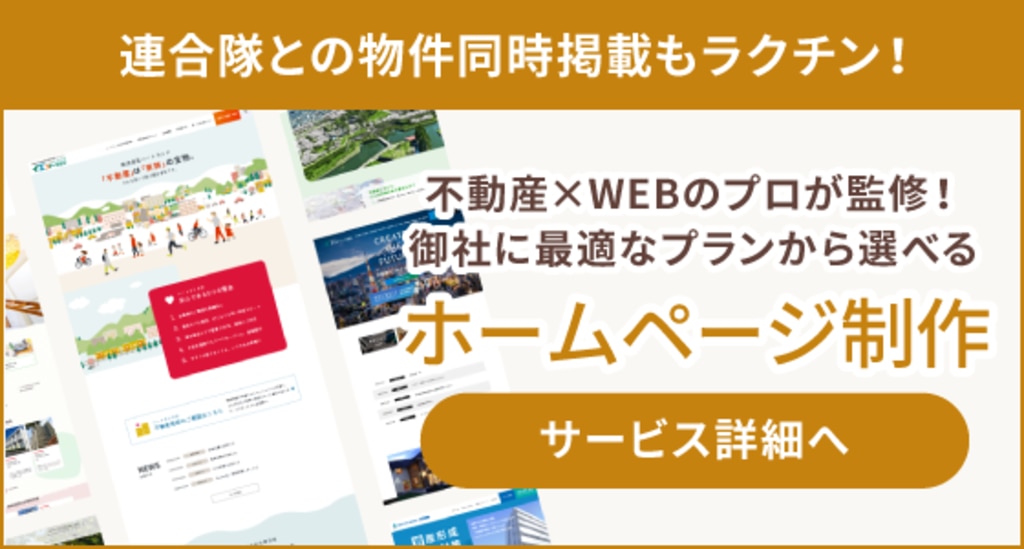2025年省エネ基準適合が義務化|不動産業界がすべき対応を解説!
2025年4月から、 すべての新築建築物に対して「省エネ基準適合」が義務化されます。これまでは努力義務だった省エネ性能が、いよいよ法律で義務化される時代に入りました。
とくに住宅や建物を扱う不動産業界や建築業界にとっては、「省エネ基準適合」が当たり前となる今、設計や営業のあり方そのものを見直す必要があります。これまで対象外だった小規模建物も含め、義務化の影響は非常に広範です。
「どこまでの建物が対象になるの?」
「今のままの設計や営業で通用するのだろうか?」
このような戸惑いや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、制度の内容と対応策を正しく理解すれば、大きなチャンスにもつながります。
「省エネ基準適合」の制度変更を不安に感じている方は、ぜひ最後までご覧いただき、「チャンス」に変えるヒントをつかんでください。
目次[非表示]
- 1.省エネ基準適合とは?基本からやさしく解説
- 2.2025年省エネ基準適合義務化の背景|法改正は必要?
- 3.2025年省エネ基準適合義務化の重要ポイント|法改正の内容
- 3.1.小規模住宅や店舗も含めて原則「すべての新築」が対象に
- 3.2.設計段階から省エネ基準に適合していないとNG
- 3.3.建築確認申請と「適合性判定」の関係性に注意
- 3.4.不適合だと“確認済証”が下りない可能性も
- 4.2025年省エネ基準適合義務化による不動産・建築業界への影響
- 4.1.営業現場に求められる説明力
- 4.2.中古・未対応物件は売れにくくなる?
- 4.3.集客に効く「省エネ検索対応」
- 5.2025年省エネ基準適合義務化の実務対策とチェックリスト
- 5.1.最新制度の理解と社内教育
- 5.2.外部パートナーとの連携
- 5.3.補助金提案・表示義務への備え
- 6.2025年省エネ住宅の補助金内容を解説!
- 7.2025年省エネ基準適合義務化をチャンスに!
- 8.2025年省エネ基準適合義務化のよくある質問
省エネ基準適合とは?基本からやさしく解説

省エネ基準適合とは、 建物がエネルギーをどれだけ効率よく使えるかをチェックし、国が定めた基準を満たしているかどうかを確認するしくみです。この基準は、住まいや建物の設計段階で判断され、建築確認の前に「適合していること」が求められます。
省エネ基準には、大きく分けて2つの考え方があります。ひとつは「性能基準」で、建物全体のエネルギー消費量を計算して基準と比べる方法です。
もうひとつは「仕様基準」で、あらかじめ定められた断熱材や窓、設備の組み合わせで基準を満たす方法です。たとえば、断熱材の厚み、窓のガラスの種類、エアコンの効率などが評価のポイントになります。これらを適切に設計することで、夏は涼しく、冬はあたたかく、光熱費も抑えられる住まいが実現できます。
これまでは、こうした省エネ基準適合は主に大規模な建物が対象でした。しかし、2025年4月からは、一般の住宅や小規模店舗など、 すべての新築建物が対象になります。つまり、省エネ基準は特別な選択ではなく、「当たり前の基準」になっていくのです。
2025年省エネ基準適合義務化の背景|法改正は必要?

省エネ基準が義務化される背景には、日本全体が取り組んでいる「 カーボンニュートラル」への大きな目標があります。建築物のエネルギー性能が国際的に遅れていることや、地球温暖化の深刻化も、制度改正の大きな要因です。
ここでは、今回の法改正がなぜ必要なのか、どのような目的で行われるのかをやさしく解説します。
カーボンニュートラルと建築分野の責任
日本では「2050年カーボンニュートラル」を目指して、 社会全体のCO₂排出量をゼロにする方針です。その中でも住宅やオフィスといった建築物に関わる部門は、非常に大きな割合を占めています。
環境省「 2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について」の発表によれば、家庭部門が約16%、業務その他部門が約19%を占めており、あわせて約35%が建築物由来のCO₂排出です。
家や建物の省エネ性能を高めることは、国全体の脱炭素化に直結しています。
たとえば、断熱性能が低い家では、冷暖房を多く使うことでエネルギーがムダに消費されます。その積み重ねが、環境負荷を大きくする原因です。
こうした背景から、建築分野での省エネ対策は「 できるだけ早く・確実に進めるべき分野」として、制度改正が進められています。
日本の住宅・建物の省エネ性能は国際的に遅れぎみ
日本の建物は品質が高いイメージがありますが、省エネ性能については、 ヨーロッパや北欧の国々と比べて後れを取っているのが現状です。たとえば、ドイツでは1990年代から高い省エネ基準が義務化されており、新築住宅のほとんどが高断熱・高気密です。
日本では、これまで省エネ基準の適合は努力義務で、小規模な住宅は適用外とされてきた背景があります。その結果、築年数が浅くても断熱性能の低い住宅が多く流通しており、「光熱費がかかる」「快適さが足りない」といった課題が残っています。
このままでは、海外の省エネ基準との差がさらに広がり、日本の建物が将来的に「価値の低い資産」と見なされるおそれもあるでしょう。
法改正の流れと2025年施行の目的
現在の省エネ関連法は、2013年に制定された「 建築物省エネ法」がベースになっています。その後も段階的に改正が進められ、2022年の改正では「2025年にすべての新築建築物に省エネ基準適合を義務化すること」 が決まりました。この法改正の目的は、単に環境のためだけではありません。
以下の生活に密接するメリットがあります。
|
エネルギー価格が高騰する中で、省エネ住宅へのニーズは高まっています。義務化により、すべての建物が「省エネが当たり前」の基準になることは、長期的に見てユーザーにも大きなメリットになります。
2025年省エネ基準適合義務化の重要ポイント|法改正の内容

2025年4月から、すべての新築建築物に「省エネ基準への適合」が義務付けられます。これまで努力義務にとどまっていた住宅や小規模な建物も含め、法的な対応が求められるようになります。何がどのように変わるのかを理解することが大切です。
建築・不動産業界が押さえておくべき4つのポイントを解説します。
小規模住宅や店舗も含めて原則「すべての新築」が対象に
これまでは、 延べ床面積300㎡未満の住宅や店舗は、省エネ基準への適合が「努力義務」でした。実質的には適用されないケースも多く、制度の対象外と考えていた方も多いかもしれません。
2025年4月以降は、小規模な建築物も原則すべて対象になります。たとえば、木造の一戸建て住宅や10坪程度の店舗でも、省エネ基準に適合していなければなりません。ただし、 国土交通省の資料によると、エネルギー消費への影響が少ない建築物として、政令で定める10㎡以下のものや、現行制度で適用除外とされている建築物については、適合義務の対象外とされています。
「うちは関係ない」と思っていた事業者や設計者も、今後は例外ではなくなるのです。
設計段階から省エネ基準に適合していないとNG
省エネ基準への適合は、 建築確認申請の前に証明されている必要があります。つまり「建ててから確認する」のではなく、「設計の時点で基準をクリアしていること」が求められます。そのため、設計事務所や工務店は、住宅のプランニングの初期段階から、省エネ性能を意識した設計を進めなければなりません。
とくに注意が必要なのは、仕様基準で用いる 断熱材や窓のグレード、設備の選定です。これらが基準を満たしていなければ、そもそも確認申請の前段階でストップしてしまいます。
建築確認申請と「適合性判定」の関係性に注意
対象となる建物によっては、「省エネ適合性判定」を受ける必要があります。これは、 設計内容が省エネ基準に合っているかどうかを、第三者機関が確認する手続きです。たとえば、300㎡以上の非住宅建築物(オフィス・工場など)は、原則としてこの判定を受けなければなりません。
一方で、300㎡未満の住宅や店舗については、設計者が自ら基準適合を確認する「 自己適合確認」が認められています。判定が必要かどうかで、準備すべき資料や手続きの流れが大きく変わるため、早めの確認が重要です。
不適合だと“確認済証”が下りない可能性も
省エネ基準に適合していない場合、建築確認申請が通らず、「確認済証」が交付されない可能性があります。確認済証は、 建築を正式に進めるうえで必要不可欠な書類であり、これがないと着工できません。
つまり、省エネ基準は「守らなくてもいい目安」ではなく、「守らなければ建てられない基準」へと位置づけが変わったのです。
今後は不動産取引や広告の場面でも、省エネ性能を表示する流れが強まっていく見込みです。基準に適合していない建物は、建てにくくなるだけでなく、売れにくくなるリスクも高まると言えるでしょう。
2025年省エネ基準適合義務化による不動産・建築業界への影響

2025年省エネ基準の義務化は、設計や施工のルールが変わるだけでなく、営業活動や物件の価値、集客にも大きな影響を与えます。不動産・建築業界では、「どう提案するか」「どう物件を選ばれるか」がこれまで以上に問われるようになるでしょう。
ここでは、実務面での具体的な影響を3つのポイントで整理します。
営業現場に求められる説明力
制度改正により、営業スタッフは「この物件は省エネ基準に適合しています」と説明する機会が増えます。顧客から「この建物は断熱性どうなの?」「光熱費は安くなるの?」と聞かれることもあるでしょう。
これまで省エネ性能に触れずに接客していた現場では、 知識の差が顧客の信頼に直結する時代に入ります。
たとえば、同じような条件の住宅でも、省エネ性能の違いをうまく説明できる営業は、比較されても選ばれやすくなります。逆に「よくわかりません」と答えると、信頼を失いかねません。制度対応だけでなく、スタッフの教育体制もこれからの差別化ポイントになります。
中古・未対応物件は売れにくくなる?
新築物件の省エネ基準が引き上げられることで、 相対的に基準を満たしていない中古物件は、資産価値が下がる可能性があります。購入希望者が「どうせ買うなら省エネ性能が高い物件がいい」と考えるのは自然な流れです。
最近は光熱費の上昇が家計に直結するため、省エネ性能への関心は高まっています。今後は、「築浅だけど断熱性能が低い」「リフォームしないと暑い寒い」といった物件は、避けられる傾向が強まるかもしれません。
中古物件を扱う不動産会社も、 省エネリフォームの提案や、インスペクション(建物調査)による性能表示への対応が求められます。
集客に効く「省エネ検索対応」
大手ポータルサイトや物件検索サービスでは、今後ますます 「省エネ性能」で絞り込む機能が強化されていくと予想されます。たとえば、「断熱等級4以上」「ZEH対応」「一次エネルギー消費量○%削減」などの条件で探す人が増えれば、基準に満たない物件は検索結果にすら表示されにくくなります。
省エネに対応していない=ネット集客の入り口から外れる、という状況になる可能性があるのです。表示内容の見直しや、物件スペックの明確化も、これからの集客戦略では欠かせない対応になります。
2025年省エネ基準適合義務化の実務対策とチェックリスト

省エネ基準適合の義務化は、現場にとって大きな制度変更ですが、正しく準備すれば「対応できない内容」ではありません。
ここでは、今のうちから備えておきたい実務対応のポイントを3つの観点で整理します。制度の理解・外部との連携・提案力の強化という流れで見ていきましょう。
最新制度の理解と社内教育
まず大切なのは、「 2025年4月以降、何がどう変わるのか?」を正確に理解することです。
そのうえで、設計や営業など関係するすべての部署で情報を共有し、社内で共通認識を持つことが重要です。たとえば、営業スタッフが「省エネ適合って何ですか?」と聞かれた時に答えられなければ、信頼を失いかねません。
設計側と連携して、使用する断熱材や設備が基準を満たしているか、誰がいつ確認するのかなど、 社内フローの明確化も必要です。
「知っている人がやる」のではなく、「誰でも基本対応ができる状態」にすることが、制度対応の第一歩です。
外部パートナーとの連携
省エネ基準への対応は、自社だけで完結できるとは限りません。たとえば、第三者機関による適合性判定が必要な場合や、性能計算が複雑な建物では、設計事務所や省エネ関連の 専門家との連携が不可欠です。
建材メーカーや設備業者とも、早い段階から打ち合わせをしておくと安心です。「その窓は基準を満たしますか?」「この断熱材は仕様基準に合っていますか?」といった確認を、設計初期に済ませておくことで、手戻りを防げます。
関係者同士で「誰が・どこで・何を判断するか」を共有し、スムーズな連携体制を整えておくことが、制度開始後の混乱を防ぐカギとなります。
補助金提案・表示義務への備え
制度対応を「ただの義務」と捉えるのではなく、「付加価値」として提案に活かすことも重要です。 国や自治体の補助金制度は、顧客にとって大きな魅力になります。
たとえば、省エネ住宅の新築やリフォームに対して、数十万円〜数百万円の補助金が出る制度もあります。「この仕様なら補助金の対象になりますよ」と提案できれば、成約率のアップにもつながるでしょう。
また、 今後は省エネ性能の「表示」が求められる場面も増えていきます。
ポータルサイトへの掲載時や、契約時の説明でも、省エネ性能が明記されることで、比較検討されやすくなります。省エネ性能は「コスト」ではなく「選ばれる理由」になる時代です。その価値を伝える営業・広報の準備も、制度対応の一部と言えるでしょう。
2025年省エネ住宅の補助金内容を解説!

省エネ基準適合の義務化にともない、国や自治体は多くの支援制度を設けています。「初期費用がかかる」「断熱性能を上げるにはコストが不安」という声に応える形で、複数の補助金が用意されています。
とくに注目したいのは、以下の4つの制度です。それぞれ対象・内容が異なるため、事前にチェックしておくことが大切です。
補助金内容|子育てグリーン住宅支援事業
子育てグリーン住宅支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯が対象の新築住宅に対し、 最大100万円(条件により変動)の補助が出る支援策です。省エネ基準に適合する住宅が条件となっており、「ZEH水準」「長期優良住宅」などの認定を受けると、より手厚い補助を受けられます。
注文住宅や建売住宅を検討している若年層向けにおすすめです。
参照| 子育てグリーン住宅支援事業
補助金内容|給湯省エネ2025事業
給湯省エネ2025事業は、高効率な給湯器を導入することで、 最大15万円程度の補助が受けられる制度です。対象となるのは、エコキュートやエネファーム、ハイブリッド給湯機など、省エネ効果の高い機器です。新築時だけでなく、リフォームでも利用できるため、既存住宅の性能向上を考えている方にも活用しやすい制度でしょう。
「光熱費を下げたい」と考える顧客への提案材料としても有効です。
参照| 給湯省エネ2025事業
補助金内容|先進的窓リノベ2025事業
先進的窓リノベ2025事業は、断熱性の高い窓へ交換することで補助が出る制度で、戸建て・集合住宅どちらにも対応しています。補助金額は、窓の大きさや断熱性能によって異なりますが、1件あたり 数十万円〜最大200万円程度の補助も可能です。
「冬に寒く、夏に暑い」と感じているお住まいでは、窓の断熱改修が効果的であり、非常に人気の高い制度です。
参照| 先進的窓リノベ2025事業
補助金内容|賃貸集合給湯省エネ2025事業
賃貸集合給湯省エネ2025事業は、賃貸住宅のオーナー向けの補助制度です。賃貸集合住宅における省エネ給湯器の導入に対し、1戸あたり 5〜10万円の補助が出る予定となっています。対象機種や要件を事前に確認したうえで、複数戸をまとめて申請できるのが特徴です。
今後は、賃貸でも「光熱費が安いかどうか」が選ばれる要素になるため、オーナーにとっては差別化のチャンスになります。
参照| 賃貸集合給湯省エネ2025事業
2025年省エネ基準適合義務化をチャンスに!

今回は、2025年から始まる省エネ基準適合の義務化について、その背景や具体的な対応策、補助金制度までを解説しました。
制度の変化に「難しそう」と感じた方もいるかもしれませんが、見方を変えればこれは“ 選ばれる物件・選ばれる不動産会社”になる大きなチャンスです。集客の差が結果につながる不動産業界では、制度に対応していることそのものが「強み」になります。
2025年省エネ基準適合義務化のよくある質問
2025年の省エネ基準義務化でリフォームも対象になりますか?
いいえ、今回の義務化は新築建築物が対象です。ただし、補助金制度では省エネリフォームにも使える支援があります。リフォーム提案の際は補助金の活用も検討しましょう。
マンションでも2025年から断熱基準は義務化されますか?
はい、新築のマンションも対象になります。住戸単位での断熱性能を確保し、省エネ基準を満たす必要があります。
ZEH(ゼッチ)は2025年から義務化されますか?
いいえ、ZEHは義務化ではありませんが、国の推進対象となっています。ZEH水準で建てると補助金対象になるなどのメリットがあります。
非住宅の建物も省エネ基準の義務化の影響を受けますか?
はい、オフィスや店舗などの非住宅建築物も義務化の対象です。延べ床面積に応じて、第三者による適合性判定が必要になる場合があります。
省エネ仕様基準は共同住宅にも適用されますか?
はい、共同住宅も省エネ仕様基準に適合する必要があります。仕様基準を満たせば、複雑な性能計算を行わずに対応できます。
2030年までに国土交通省が目指すものは何ですか?
2030年までに、新築住宅・建築物の平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能を確保することが目標です。今後さらに基準は高まる方向です。
家づくりをする時にカーボンニュートラルを実現できますか?
はい、省エネ設計+再エネ活用(太陽光発電など)で実現可能です。長期的には光熱費の削減や資産価値の維持にもつながります。